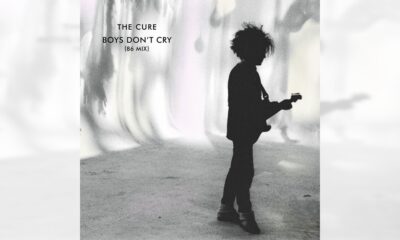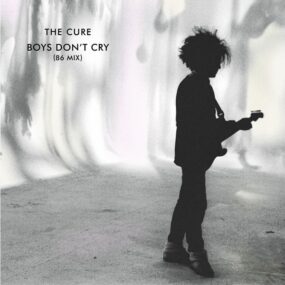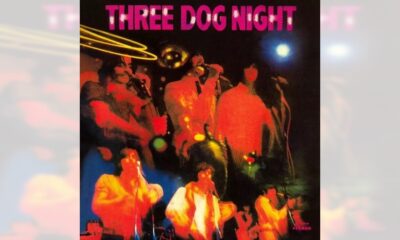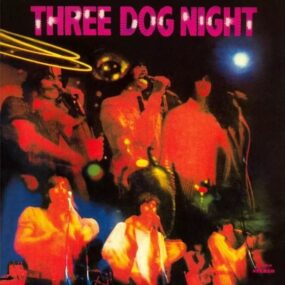Stories
60年代の大物ロック・ミュージシャンたちはいかにして70年代へと適応していったか


1960年代後半に盛り上がりをみせた反体制文化の夢が崩れ去ったあと、その文化を音楽で彩ってきたアーティストたちはみな、同じ問題に直面した。つまり、「さて、次はどうすべきか?」ということだ。
そして、60年代を代表するロック・ミュージシャンたちはそれぞれに違った答えを導き出し、70年代に入って最初に発表したアルバムでそれを表現してみせた。ザ・フー、ザ・ローリング・ストーンズ、そして新たにソロとなった元ザ・ビートルズの二人。彼らは各々のやり方で、理想主義や冒険心に満ちた60年代から現実主義の新時代へと移り変わる厄介な端境期を乗り越えたのである。
<関連記事>
・ザ・フー『Life House』解説:難解過ぎて発売されなかった“SFロックオペラ”
・スペインとロシアでローリング・ストーンズ『Sticky Fingers』のジャケが変わった理由
・ストーンズ、18年振りのスタジオアルバム『Hackney Diamonds』を10月に発売
・ザ・ローリング・ストーンズが18年振りの新作発表会見で語ったこと
ザ・フー
60年代、ザ・フーはさまざまな実験を通してグループとして発展していった。それは1966年に発表した先駆的なエレクトリック・オペラ「A Quick One, While He’s Away」に始まり、1967年には皮肉に満ちたコンセプト・アルバム『The Who Sell Out』をリリース。そして1969年には、アルバム全編を通して本格的なロック・オペラが展開される『Tommy』を生み出した。
その中で彼らは、サイケデリック・ムーヴメントの先端に加わったり (「Armenia City In The Sky」)、想像力豊かな寓話を紡いだり(「Silas Stingy」)、サーカスの一日を音で表現したり(「Cobwebs And Strange」)、モータウンのヒット曲からバットマンのテーマ曲まであらゆる音楽を独自のアレンジで演奏したりしていたのである。
そんなザ・フーが70年代に入って最初にリリースしたアルバムが『Who’s Next』である。同作はついに実現することのなかった、あるプロジェクトを基に作られたアルバムだ。そのプロジェクトは、新時代の到来にあたって崩れ去っていった60年代の夢物語を見事に象徴しているといえよう。
ピート・タウンゼントはもともと、SFロック・オペラ作品『Life House』の構想を膨らませていた。そのコンセプトは、『Tommy』が童謡レベルに思えてしまうほど独創的なものだった。最新技術を駆使して実現される予定だった同プロジェクトにおいては、アルバムのほかに映画や、バンドと観客が相互に交流する定期的なライヴも行われることになっていた。
その時代には野心的すぎる構想が次々に生まれては消えていったが、『Life House』もそれらと同じく、結局は“地に足のついていない企画の域”を超えられなかった。それでも、このプロジェクトのために作られた楽曲の多くはそのまま『Who’s Next』の収録曲になった。その新たなアルバムは“自己完結型の楽曲を集めた昔ながらのロック・アルバム”という、当時としてはむしろ元のアイデア以上に挑戦的な作品となったのである。しかし、この作品で彼らの何かが変化したことは、その中身を聴くまでもなく誰の目にも明らかだった。
『Tommy』のアルバム・ジャケットは、ドラッグによる幻覚から生まれたかのような奇妙なデザインだった。他方、『Who’s Next』のジャケット写真は、荒廃した採掘場のボタ山の上に立つメンバーたちの姿を捉えている。そこに写る彼らは、コンクリートの柱に向けて用を足した直後のように見える。
この写真を撮影したイーサン・ラッセルによるとこれには、似たようなモノリス(石柱)が登場する1968年の映画『2001年宇宙の旅』の名シーンを茶化す意味合いもあったのだという。これも、ヒッピー的な理想主義がもっとみすぼらしいものに取って代わられたことの一例だといえよう。
ヒッピー時代の理想の崩壊を巧みに表現した楽曲として、「Baba O’Riley」以上のものはなかなかないだろう。ピート・タウンゼントは2021年、ギター・プレイヤー誌のクリストファー・スカペリーティの取材の中で、「10代の荒地 (teenage wasteland)」という歌詞の一節について解説している。
彼によるとそのフレーズは「ウッドストックでの10代の若者の荒廃ぶり」を表しているのだという。「誰もがドラッグでラリっていたんだ」と彼は話している。
また、「Won’t Get Fooled Again」も似たようなアプローチの楽曲だ。“ヒッピー革命”のもたらした結果に対する幻滅が表現された同曲で彼らは、「歴史は少しも変わっていない (History ain’t changed)」と分析。さらに、「以前の左派もいまや右派になった/ヒゲがたった一日で伸びてしまうようなものさ (The parting on the left is now a parting on the right/And the beards have all grown longer overnight)」と皮肉っぽく歌ってもいる。
上述した2曲においては、そのサウンドも彼らの大きな変化を示していた。両曲とも、ギター/ベース/ドラムというグループの基本構成に、タウンゼントによる実験的な電子音が加わっているのだ。そこでは、フィリップ・グラスさながらのミニマリズム的な反復音も聴くことが出来る。
ザ・ローリング・ストーンズ
ザ・ローリング・ストーンズの作風はほかのバンドと比べると、70年代に入って劇的に変化したというわけではない。かといって、特筆に値しないということも決してない。1967年作『Their Satanic Majesties Request』でストーンズは、サイケデリック・ロックの世界にどのグループよりも堂々と身を投じた。しかし、そのあとで彼らは、自分たちのルーツに回帰した二つのアルバムで60年代を締めくくった ―― それが『Beggars Banquet』と『Let It Bleed』の2作である。
特に、60年代が幕を下ろす数週間前にリリースされた後者は、彼らにとって70年代への助走といえるような作品になった。だが、同作のシュールなアルバム・ジャケットは、サイケデリック・ムーヴメントの影響を色濃く残している。
その奇抜なジャケット写真は、メンバーの友人であったロバート・ブラウンジョンが手がけたもの。そこにはピザ、時計、タイヤなどが層になった奇妙なケーキらしきものが写っており、それらは昔ながらの蓄音機風のレコード針が乗ったストーンズのレコードの上に浮かんでいるのだ。
それとは対照的に、アンディ・ウォーホルがデザインした1971年作『Sticky Fingers』の有名なジャケットは無骨で、セクシーさを大胆に押し出したものだった。またぐらが写ったそのジャケットは、(オリジナル盤では)ジッパーを下ろすと後ろの下着が露わになる構造になっていたのだ。また、肝心の収録曲もストーンズの新たな一面を“露わに”していた。彼らは、アコースティックの演奏を織り交ぜた泥臭いサウンドはそのままに、同作で自分たちのダークな部分をさらけ出していたのである。
1969年7月にこの世を去ったブライアン・ジョーンズが参加していないアルバムは、ストーンズにとって同作が初めてだった。ジョーンズはグループでも指折りのブルース愛好家だったが、あまのじゃくな性格で、ストーンズを思いがけない音楽性へと導いた張本人でもあった。彼が楽曲の雰囲気を決定付けるマリンバを叩いた「Under My Thumb」は、その早い時期の例である。当時のストーンズの面々は、特別な才能を失ったと同時に大切な友人を失った悲しみに暮れていたのだ。
「Sister Morphine」や「Dead Flowers」といった楽曲には、そんな物悲しいムードが漂っている。まるで悪夢のような雰囲気の前者は、ドラッグか死(あるいはその両方)を強く求める入院患者の苦しみを歌った短調の楽曲。そのような内容の曲になったのは、当初は作曲者にクレジットされていなかったマリアンヌ・フェイスフルの関与によるところが大きい。
2013年、彼女はガーディアン紙のデイヴ・シンプソンにこう話している。
「私の実体験がそのまま歌われているわけではないけど、表現されている気持ちに偽りはないはず。ブライアン・ジョーンズが亡くなったあと、私は自殺を図ってシドニーの病院に入院したの。あの時期は酷かった」
1973年にジョーンズと同じく帰らぬ人となったグラム・パーソンズは、『Sticky Fingers』の制作が始まるころまでにキース・リチャーズと親友同士になっていた。実際、「Wild Horses」や「Dead Flowers」などには、パーソンズによる悲哀に満ちたカントリー・サウンドの影響が滲んでいる。またミック・ジャガーは、カントリー・シンガーとして確かな実力があると思えたことはない、と自分でも認めている。
そのためか「Dead Flowers」は少々大げさな歌い回しになっているが、あまりに露骨なヘロイン使用の描写「俺は注射針とスプーンを持って地下室に下りる (I’ll be in my basement room with a needle and a spoon)」から死を連想させるコーラス・パートまで、同曲には暗いムードが充満している。
ポール・マッカートニー
ストーンズのかつてのライバルは、グループとして60年代を終えることができなかった。ザ・ビートルズの主たるソングライターであったジョン・レノンとポール・マッカートニーは、1970年にソロ・デビュー作をそれぞれ発表。それらはいずれも、余計な装飾を排し、各々のやり方で自らをさらけ出したアルバムだった。そのうち『McCartney』は、彼らが“ファブ・フォー”として最後に制作した『Abbey Road』とはあまりにかけ離れた作風だった。
ザ・ビートルズのラスト・アルバムである同作 (『Let It Be』の方があとにリリースされているが、レコーディングはこちらがあとだった) は、タイトルにもなっている伝説的なスタジオで制作された。妥協を許さぬジョージ・マーティンの下で作り上げられた楽曲は、洗練されたサウンドに仕上がっていたのである。
それとは逆にポールのソロ・デビュー作は、これ以上“手作り感”を出すには自宅の庭で録音するしかない、というほど素朴な作風だった。実際、彼はそのほとんどを自宅で録音している。最小限の機材のみを使用し、演奏もエンジニアとしての役割もすべて自分自身で担ったのである。
結果として出来上がったのは、不格好ながら気取りのないサウンドの作品だった。同作には、素朴なガレージ・ロック調のインストゥルメンタル・ナンバー「Valentine Day」や、打楽器を中心に据えた茶目っ気のある1曲「Kreen-Akrore」など即興風の愛すべき楽曲が並ぶ。
だがその中に、愛に満ちた「Every Night」や、物憂げな「Junk」、卓越した名曲「Maybe I’m Amazed」など、マッカートニーのキャリアにおける代表曲も混じっているのだ。そこから感じられるのは、1970年当時のマッカートニーが、とにかく自らを飾ることなく思いのままに音楽を作ろうとしていることだった。
ジョン・レノン
ポールの『McCartney』の8ヶ月後にリリースされた『Plastic Ono Band (ジョンの魂)』の制作で、レノンはアビー・ロードに舞い戻った。バンド編成で録音された同作には、共同プロデューサーとしてフィル・スペクターも参加。しかし、彼は珍しく抑制の効いたサウンドを志向した。そんな同作はマッカートニーのアルバム以上にビートルズ時代の作風とかけ離れたものになったが、それは自らの心の傷を包み隠さず表現したレノンの作曲アプローチによるところが大きかった。
60年代と、その時代を代表するビートルズというバンドとの決別を固く誓ったレノンは、悩める自らの心の傷口を開いた。そして、その内側にあるものをじっくりと見つめるとともに、作品を通してそれをリスナーにもさらけ出したのである。
ドラムにリンゴ・スターも参加した同作では、一切の装飾を排したアレンジが施された。そのサウンドに乗せてレノンは自分自身をバラバラに解体し、一つ一つの問題を掘り下げていったのである。
例えば、「Mother」では原初療法を通じて、共に暮らせなかった両親にまつわる問題と向き合った。また、「I Found Out (悟り)」では反体制文化の幻想からの脱却が、「God」では”ビートルズの元メンバー”以上の存在になろうともがく彼の苦悩がそれぞれテーマとなっている。そして後者の最後のヴァースでレノンは、新たな時代への適応について歌っている。彼はその想いを、60年代に活躍したどのロック・アーティストよりも簡潔に表現していた。
I was the dreamweaver
But now I’m reborn
I was the walrus
But now I’m John
And so dear friends
You’ll just have to carry on
The dream is over
かつての俺は夢追い人だった
だけど俺は生まれ変わったんだ
かつての俺は セイウチだった
でも 俺はこうしてジョンになった
だから親愛なる友人たちよ
とにかく進んでいくしかないんだ
あの夢はもう終わったんだから
Written By Jim Allen
ザ・フー『Who’s Next – 50th Anniversary (BluRay/Graphic Novel SDE) (10CD)』
2023年9月15日発売
10CD / 2CD
 ザ・ローリング・ストーンズ『Hackney Diamonds』
ザ・ローリング・ストーンズ『Hackney Diamonds』
2023年10月20日発売
① デジパック仕様CD
② ジュエルケース仕様CD
③ CD+Blu-ray Audio ボックス・セット
④ 直輸入仕様LP
iTunes Store / Apple Music / Amazon Music
- ザ・フー『Life House』解説:難解過ぎて発売されなかった“SFロックオペラ”
- スペインとロシアでローリング・ストーンズ『Sticky Fingers』のジャケが変わった理由
- ストーンズ、18年振りのスタジオアルバム『Hackney Diamonds』を10月に発売
- ザ・ローリング・ストーンズが18年振りの新作発表会見で語ったこと
- ザ・フーのベスト・ソング20選【動画付】
- 『Tommy』ある男の想像の産物であり、ある男が見る素晴らしい光景
- ザ・フーにとっての『White Album』、1971年の傑作アルバム『Who’s Next』
- ザ・ローリング・ストーンズが18年振りの新作発表会見で語ったこと
- ザ・ローリング・ストーンズはどのようにロックンロールを変えたか?
- ストーンズの「ベロ・マーク」の誕生と歴史
- Abbey Road:ザ・ビートルズと横断歩道、そして8トラック・レコーダー
- ポール・マッカートニー、全163曲/80枚の7インチ・シングル・ボックス発売
- ビートルズ後のポール・マッカートニーによるベストソング20曲
- ポール・マッカートニーのベスト・コラボレーション11
- ジョン・レノンの初のソロ作『ジョンの魂』発売50周年記念盤発売
- 人気ポッドキャスト番組が、ジョン・レノンの誕生日にあわせて名曲 「God」のエピソード公開
- 全米チャートデビュー163位から1位に上り詰めた名作『Imagine』
- ワンテイクで録音されたジョンとヨーコの「平和を我等に」