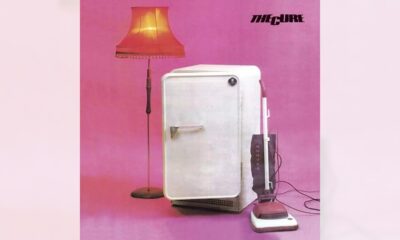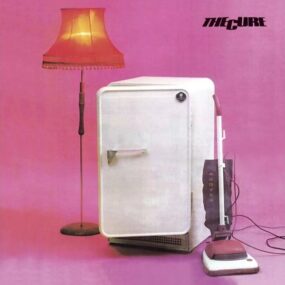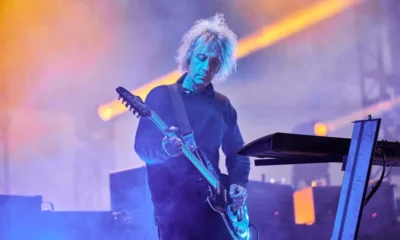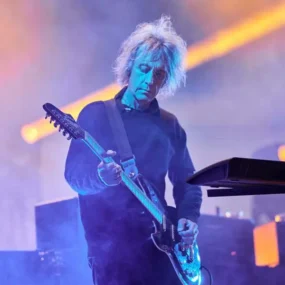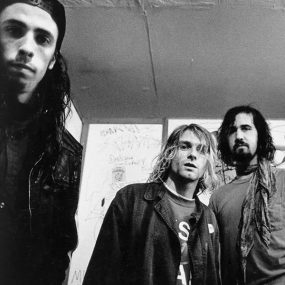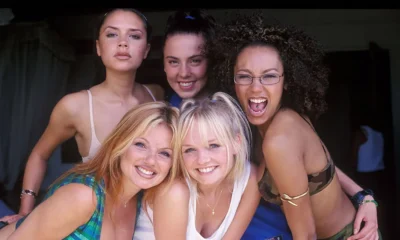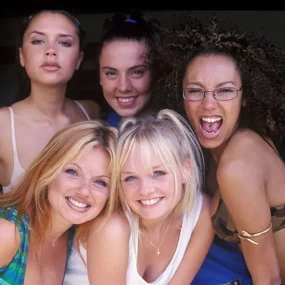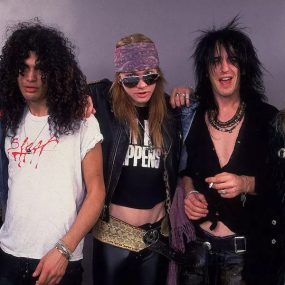Stories
ナイン・インチ・ネイルズの経歴:原始的で知的、真っ暗な闇とまばゆい光を併せ持つバンド


オハイオ州クリーヴランドでトレント・レズナーにより創設されたナイン・インチ・ネイルズ(Nine Inch Nails)は、独自のスタイルの先駆者であり続けてきた。
初期には広くインダストリアル・ロック・バンドに分類されていた彼らだが、根幹にある理念を変えることなくアルバム毎にコンセプトを変化させ成功を収めてきた。ファンの熱狂ぶりを見ると、彼らの人気はカルト的なものに過ぎないなどという見方が馬鹿馬鹿しく思えてくる。実際、彼らの作品のアメリカ国内での売上は1,100万枚以上にのぼり、全世界では3,000万枚を超えているのだ。
また、自身の作品やオルタナティヴ・ミュージック全般を説得力のある言葉で支持する点もレズナーの特徴だ。当時の”空白の世代”あるいは”X世代 (1965年~1970年代生まれ)”の代弁者のような存在である彼は、既成の方法論を力強い言葉で批判する。
そんな彼をタイム誌は”もっとも影響力のある米国人”の1人に、スピン誌は”音楽界でもっとも重要なアーティスト”の1人に、ローリング・ストーン誌は”史上最高のアーティスト”の1人にそれぞれ選出しているのだ。そんな彼らの経歴を振り返ってみよう。
<関連記事>
・『The Downward Spiral』解説:この傑作が長年に渡り語り継がれる理由
・ナイン・インチ・ネイルズの遍歴と名曲
・ナイン・インチ・ネイルズによる『トロン』のサントラは映画音楽を変えるのか
・レズナーとアッティカス・ロス: 飛躍的進化を遂げた作曲家コンビの経歴
名前の謎とデビューアルバム
ナイン・インチ・ネイルズが進化を続けるにつれ、その名前の由来は様々な憶測を呼んできた。だがこの点に限ってはレズナーも具体的な説明を避けており、“略すのが簡単で覚えやすい言葉を選んだ”と語るにとどまっている。
リスナーがこの名前を何らかの宗教的シンボルだと解釈するのは自由だが、その響きが彼らの音楽の全体的な印象と合致しているのは確かだ。初期のアルバムにみられる陰鬱でハードコア色の濃いサウンドは、作品を追うごとに多幸感溢れる荘厳な装飾に彩られるようになっていくのである。
もともとクリーヴランドでエンジニア/テープ技師として働いていたレズナーは、上司を説得してスタジオの空き時間を利用する許しをもらい、プリンスからの影響が微かに感じられる数曲のデモを自主制作。そして『Purest Feeling』と題されたこのデモ・テープから楽曲を選り抜いて作られたデビュー・アルバムは『Pretty Hate Machine』と名付けられた。
レズナーは英国人エンジニアのエイドリアン・シャーウッドやフラッドと密に連携し、インダストリアル・ゴシック調のシンセポップ・サウンドと歪んだ音のダンス・グルーヴを融合。一方でリフとフックを取り入れた楽曲構成にこだわった点からは、彼がニュー・ウェーヴの影響を受けていたことが読み取れる。同作より「Down In It」「Head Like A Hole」「Sin」などの重要トラックはオハイオ州内のみならず、特にUKで大きな注目を集めた。そうしてレズナーは、米国におけるポスト・ロックという新たなジャンルの旗手になったのである。
1989年にリリースされた同作のオリジナル盤はかなりの枚数を売り上げ、のちに米国内でトリプル・プラチナに認定。レズナー自身もロラパルーザでのナイン・インチ・ネイルズのパフォーマンスにより一気に知名度を高め、ペリー・ファレルが生み出した所謂“オルタナティヴ・ネーション”の牽引役になった。
2010年にリリースされた『Pretty Hate Machine』のリマスター版は、ボーナスとしてフレディー・マーキュリー作の「Get Down, Make Love」を加え、パッケージにも力が入った決定版といえる内容になっている。
2ndアルバム『The Downward Spiral』
続くEP『Broken』(1992年)は現代ロック史においてもとりわけ大きな期待の中でリリースされた。さらに、その勢いのまま同年発表されたEP『Fixed』もファンの熱狂を維持したが、ナイン・インチ・ネイルズが既存の枠にはまらないバンドであることを真に証明したのは2ndアルバムの『The Downward Spiral』だった。
“負のスパイラル”に陥った男の人生を描いた同作は、デヴィッド・ボウイやピンク・フロイドの影響を受けて制作された1作だ。「Hurt」や「Closer」などの人気楽曲を含むこのアルバムで、レズナーは刺激的な独自のサウンドを確立。引き続きフラッドと手を組んだ彼は新旧の技術を駆使し、その両方から際立った個性を引き出した。
そして、反技術主義とも単純な未来主義とも違う視点を持った同作は、「Heresy」「March Of The Pigs」「Big Man With A Gun」のように虚無主義を意図的に打ち出した楽曲を収録していたこともあって大きな反響を呼んだ。あとになって振り返れば、同作は意図して挑発的な内容に仕上げられたというより、剥き出しの感情をありのままに表現した結果なのだろう。
またエイフェックス・ツイン、リック・ルービン、デイヴ・ナヴァロ、J.G.サーウェルらが参加した同作のリミックス・アルバム『Further Down The Spiral』も、“親アルバム”とセットで聴くべき名品である。
アラン・モウルダーとの『The Fragile』
ナイン・インチ・ネイルズが新たなスタジオ・アルバムを引っ提げてカムバックを果たしたのはそれから5年後のこと。その『The Fragile』(1999年)でレズナーは、プロデュース面での相談相手としてアラン・モウルダーを起用した。モウルダーの几帳面なアプローチと音作りに関する知識は、計100分を超える楽曲群を作り上げたトレントの豊かな発想を具現化する上での助けになった。
またも全体を貫くコンセプトを持ち、メロディー面での驚きに満ちた『The Fragile』の狙いは、無秩序から秩序を生み出すことにある。「Somewhat Damaged」(幾分ダメージを負った)で幕を開け、「Ripe (With Decay)」(熟して [腐敗していく])で幕を下ろす構成も、そのことを物語っているといえよう。
CD2枚にまたがる同作には素晴らしいサウンドが満載で、リリース当時こそ完全には理解されなかったかもしれないが、現在ではナイン・インチ・ネイルズのファンに愛好される作品になっているようである。
そして1つ確かなのは、破滅の道を突き進んでいるように見えるときであっても、レズナーは一流のゲストを活かすことにいつだって長けているということだ。例えば、是非とも一聴すべきこのアルバムにはギタリストのエイドリアン・ブリュー、デヴィッド・ボウイのバンドでピアノを弾いたこともあるマイク・ガーソン、ヒップホップ界の巨匠であるドクター・ドレー、名エンジニアのボブ・エズリンらが参加しているのである。
21世紀のナイン・インチ・ネイルズ
レズナーがこのころまでに大きな人気を獲得していたことを物語るように、続く『With Teeth』(2005年)もアメリカ国内で初登場1位をマーク。さらに同作からは「Only」「Every Day Is Exactly The Same」「The Hand That Feeds」という3つのシングルが、ホット・モダン・ロック・トラックス・チャートで首位を獲得した。
彼は目立った活動のない期間があると、私生活における問題やシンプルな創作面でのスランプを理由に挙げることが多い。だがレズナーが人生の経験を積んでこそそれを作品に落とし込めるタイプのアーティストであることは誰の目にも明らかで、彼ほどリスナーの共感を集める人物は21世紀のロック界においても珍しい。そして多数のボーナス・トラックを同時収録した『With Teeth』は、依存症との闘いやその克服を鮮烈に描いた1作である。
一方、人間の生き様を描いた同作とは対照的に、続く『Year Zero(イヤー・ゼロ〜零原点…)』(2007年)では冷ややかな政治批評が展開された。デジタル時代の利点をフルに活かしたこの作品は、同名の代替現実ゲームとともに発表されたことで大きな注目を集めた。
その巧妙なマーケティング戦略とディストピア的なテーマからオーウェルの『1984年』の世界観との類似点を指摘されることもあったが、それもレズナーの狙い通りだった。また、彼は刺激的なメッセージに負けない強力な楽曲が必要であることも忘れておらず、中でも「My Violent Heart」や「Capital G」はトレントの楽曲史上屈指の説得力を備えている。
そのあと個人での活動期間(当の本人はこれを”失踪劇”と呼んだ)を経て、ナイン・インチ・ネイルズは『Hesitation Marks』(2013年)でシーンに復帰。バンドの復活は大いに歓迎され、『Hesitation Marks』(何のためらい[Hesitation]もなく、最高レベルの評価[Marks]を与えられる傑作だ)も批評面で絶賛された。
レズナーがアレッサンドロ・コルティーニとコラボし、ピノ・パラディーノ、トッド・ラングレン、リンジー・バッキンガムといったミュージシャンを招いた同作は、成熟した魅力に満ちた1作である。
外せない周辺作品
ナイン・インチ・ネイルズが生み出す作品は、大きな価値と重要性を持ったものばかりだ。企画盤などの周辺作品からも見逃せない傑作をいくつか紹介しておこう。
リミックス・アルバム『Things Falling Apart』は賛否が分かれた作品だが、ライヴ音源を含んだ2枚組アルバム『And All That Could Have Been』はまったく驚異的な作品だ。そこにはバンドのカタログの中でも特にハードコア色の強い楽曲をピアノとアコースティック楽器で再構築したヴァージョンのほか、ここ数十年の音楽界でも最高峰の完成度と発想力を誇るトラックの数々が収められている。
トレント・レズナーとナイン・インチ・ネイルズは現代の音楽界に消えることのない足跡を残した。デヴィッド・ボウイはそのリーダーであるレズナーを“現代のヴェルヴェット・アンダーグラウンド”と評したが、彼の作品には1つずつ聴いて探究していく価値が十分にある。
彼の音楽を初めて聴く人には最高の刺激が待っているし、彼のキャリアを追ってきた人やよく知っている人も必ずカタログの中に新たな喜びを見つけられるはずなのだ。
休むことを知らないレズナーは、これまで映画、ビデオ、ゲーム開発といった分野にも進出してきた。彼が自らのスタイルに関して妥協することは滅多になく、時折向けられる厳しい批判を気にかけることもない。その代わりに、彼は豊富な人生経験や客観的知識を作品に落とし込んできた。その音楽は時によって原始的だったり、知的だったり、真っ暗な闇に包まれていたり、逆にまばゆい光を放っていたりするのだ。そして、その中に退屈なものなど1つもない。いまこそ、ナイン・インチ・ネイルズの世界に足を踏み入れよう。
Written By Max Bell

ナイン・インチ・ネイルズ『TRON: ARES (Original Motion Picture Soundtrack)』
2025年9月19日発売
CD&LP / iTunes Store / Apple Music / Spotify / Amazon Music
- ナイン・インチ・ネイルズの遍歴と名曲
- ナイン・インチ・ネイルズが新作映画『トロン:アレス』の音楽を担当
- ナイン・インチ・ネイルズ、3年ぶりのワールドツアー“Peel It Back Tour”の日程を発表
- ナイン・インチ・ネイルズ、T・レックス、デペッシュ・モードらがロックの殿堂入り
- 『The Fragile』解説:商業的な成功した不機嫌と陰気をまとったアルバム
- 『The Downward Spiral』解説:この傑作が長年に渡り語り継がれる理由
- レズナーとアッティカス・ロス: 飛躍的進化を遂げた作曲家コンビの経歴