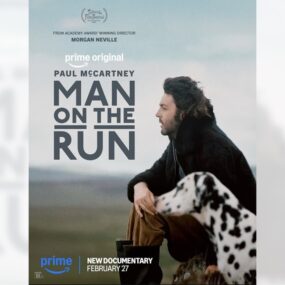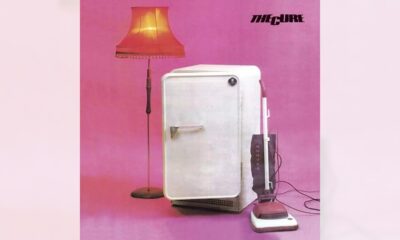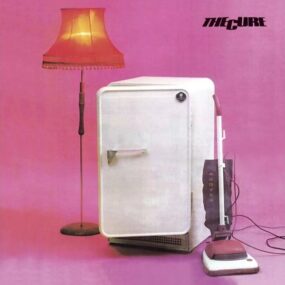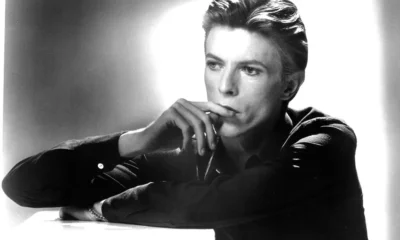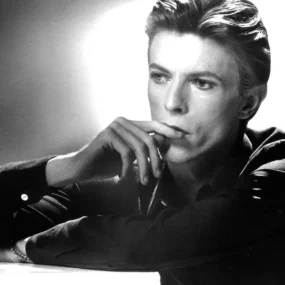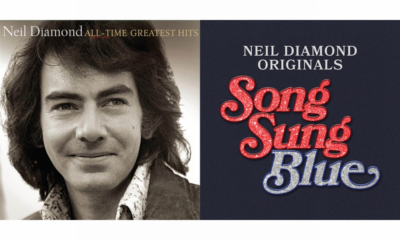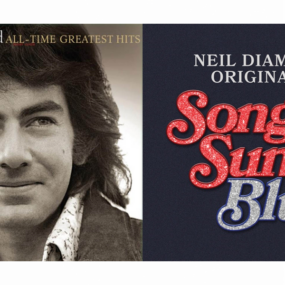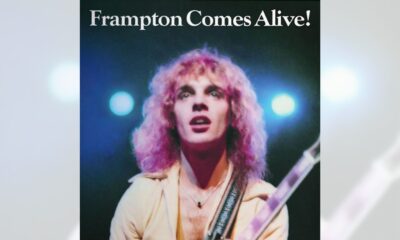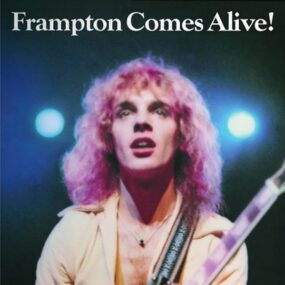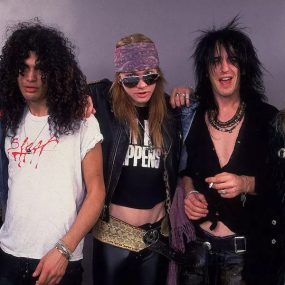Stories
小さいけれども力持ち:ロックで主役となったフルート


ロックンロールの第一世代が羽ばたいた1950年代、フルートはスクエアダンスのタキシードと同じくらい平凡な存在だった。とはいえ1960年代後半から1970年代半ばにかけてロックが成長して守備範囲を広げていったとき、フルートという風采の上がらない楽器がロック史の中に驚くほどしっかりとした居場所を確保した。
金切り声を挙げるストラトキャスターや泣き叫ぶハモンド・オルガンに囲まれながら、地味なフルートが誰もが予想しなかったほどの高さまで飛んでいったのである。
<関連記事>
・プログレッシヴ・ロックのベスト30曲
・最高のサイケデリック・アルバム・ベスト30
サイケ・ポップの爆発
ロカビリーやドゥーワップが流行していた時代、木管楽器の活動といえばサックスに始まりサックスに終わるという状況だった。とはいえそれから10年後になると、バリエーションが広がり始めた。ブリティッシュ・インヴェイジョンが進むうちに、英米の野心的なビート・グループがクラシックの影響を受けたチェンバー・ポップ・アレンジを導入し、バロック風の音作りを目指すようになったのである。
そうしたアレンジは、チェンバロや弦楽四重奏などで飾られていた。その結果、あのスリムで銀色に輝く楽器にも扉が開かれ、そのような楽器がロックの世界にまで出しゃばってモグリ営業をするようになった。
1965年、ビートルズの哀愁を帯びた「You’ve Got to Hide Your Love Away」を物憂げなフルートの旋律が彩った。そうしてビートルズが新たな方向性を示すと、大勢のバンドが我も我もと後に続いた。
その後1年半のあいだに、フルートはさまざまな曲を飾るようになった。その例としては、ニューヨークのバロック・ポップの第一人者、レフト・バンクの「Walk Away Renee」、ローリング・ストーンズの「Ruby Tuesday」、アソシエーションの「Along Comes Mary」、そしてビーチ・ボーイズの代表作『Pet Sounds』に収録されたいくつかの曲が挙げられる。
それでもこの時点では、フルートが食い込んでいた場所は、バンド外のミュージシャンが奏でるオーケストラ編曲の中にとどまっていた。たとえバンドの側がフルートの導入を要請したとしても、せいぜいその程度だったのである。
とはいえチェンバー・ポップは1967年後半には本格的なサイケデリック・ミュージックへと移行し、その結果、状況が変わり始めた。そして、そうした音楽に影響を与えるのはクラシックだけではなかった。
もちろん、ジャン=ピエール・ランパルのような人は、クラシックの世界からやってきたフルートのスーパースターだった (ただし注目すべきことに、1968年にもなるとそのランパルでさえ開放的になり、ラヴィ・シャンカールとレコーディングするようになる) 。とはいえ1960年代、流行に敏感なフルート奏者たちの天国になっていたのはジャズだった。ハービー・マン、ユセフ・ラティーフ、ラサーン・ローランド・カークらはみな、フルートがジャズ・バンドの主役を張れることを証明していた。そんな彼らが、今度はロックのフルート奏者たちに影響を与えていった。
その一方で、ムーディー・ブルースのレイ・トーマスのようなミュージシャンは明らかにクラシックをお手本としてフルートにアプローチしていた。このバンドはもともとR&Bバンドであり、1965年のデビュー・アルバムではマルチ・インストゥルメンタリストであるトーマスのフルートは1曲にしか登場していない。
とはいえ1967年の先駆的なアルバム『Days of Future Passed』はコンセプト志向のサイケ・ポップ組曲を収録しており、トーマスのフルート演奏が主役として前面に出るようになった。とりわけ不朽の名曲「Nights in White Satin」では、ロックの歴史に残る有名なフルート・ソロが披露されている。
最前線に踊り出たフルート
それとは対照的な道筋をたどったのがイアン・アンダーソンだ。1970年代にジェスロ・タルがプログレ・バンドに変貌したとき、アンダーソンはフルート奏者の地位を本格的なロック・スターの座にまで押し上げ、有名になった。
彼はジャズ/ブルース出身のミュージシャンであり、ローランド・カークのオーバー・ブローという風変わりなスタイルに多大なる影響を受けた (オーバー・ブローは、フルートの音に奏者の声を混ぜるという奏法だった) 。その影響はタルの68年のデビュー作『This Was』にはっきり表れている。このアルバムには、カークの「Serenade to a Cuckoo」のカヴァー・ヴァージョンが収録されていたのである。
またトラフィックでサックスとフルートを担当していたクリス・ウッドは、それ以前はジャズ/ブルース・バンドのスティーヴ・ハドリー・カルテットで演奏していた。トラフィックの1967年のデビュー・アルバム『Mr. Fantasy』では、「Dealer」、「Giving to You」、「No Face, No Name, No Number」といったサイケデリックな楽曲をウッドのフルートが盛り上げている。
このバンドが1970年の『John Barleycorn Must Die』でフォーク・ロックに転じたとき、彼のフルートはより重要な役割を担うことになった (たとえばアルバム・タイトル曲での彼のソロは必聴だ) 。その後のアルバムではジャズ色の濃いプログレ志向が強まり、フルートの活躍の場がさらに増えた。
アメリカでも、ニューヨークのブルース・プロジェクトがジャズ/ブルース的な手法でフルートをたびたび前面に出していた。このバンドのファースト・アルバム『Live at The CaféAu Go Go』 (1966年) は大部分の曲がブルース・ロックであり、木管楽器は見当たらなかった。しかしさまざまな要素を盛り込んだ次のアルバム『Projections』では、ベーシストのアンディ・クルバーグがフルートの腕前を披露し始めた。
その例としては、フォーク調のバラード「Steve’s Song」や、今にも爆発しそうなインストゥルメンタル曲「Flute Thing」が挙げられる。後者は1967年に開催された画期的なイベント、モンタレー・ポップ・フェスティヴァルでも演奏された。また1994年にはビースティ・ボーイズがアルバム『Ill Communication』の「Flute Loop」でサンプリングしている。
同じように、アメリカ西海岸のキャンド・ヒートは、最初の2枚のLPで筋金入りのブルース・ロック・バンドとしての地位を確立していた。
しかし3枚目のアルバム『Living the Blues』 (1968年) で少し開放的になり、ジム・ホーンを起用して「Going Up the Country」に陽気なフルートの音色をちりばめた。そのおかげもあって、この曲はキャンド・ヒートの一番の人気曲になった。この曲はウッドストックのドキュメンタリー映画でも目立つ場面で登場し、ヒッピーのアンセムとして永遠の地位を確保した。
一方、イギリスのブルース・ロックのパイオニア、ジョン・メイオールは自らの伝説的なバンド、ブルースブレイカーズを解散させてからはサウンドを一新し、『The Turning Point』ではアンプラグドの方向へと向かった。
これは1969年にニューヨークのフィルモア・イーストで録音されたライヴ・アルバムであり、ここで演奏していた新しいバンドはアコースティック中心の編成で、ジョン・アーモンドの木管楽器がフィーチャーされていた。そのアーモンドのフルートが鋭い音色を響かせたシングル「Room to Move」はFMラジオで人気曲となり、このアルバムはメイオールにとってアメリカで最もヒットした作品となった。
1970年になると、アーモンドとヴォーカリスト/ギタリストのジョン・マークはメイオールのバンドから離れ、マーク=アーモンドというユニット名でフォーク、ジャズ、ロック、R&Bを強烈にミックスしていった。そこでもフルートは、不可欠な役割を果たしていた。
プログレッシヴ・ロックで重用されたフルート
トラフィックやジェスロ・タルといったバンドが1960年代末に始めた動きは、1970年代前半になるとさらに勢いを増した。プログレッシヴ・ロックが成層圏を駆け上がり、サイケデリックの冒険趣味に超絶技巧や音楽大学卒の教養を融合させたのである。フルートにとって、ロックのサブジャンルの中で最高の安息地となったのはおそらくこのプログレだったのではないだろうか。
ピーター・ガブリエルは後に伝説的なソロ・アーティストの地位を獲得するが、それ以前はジェネシスのメンバーだった。かつてのジェネシスは、プログレの中でも最初期の、最も影響力のあるバンドのひとつだった。そして当時のガブリエルは、このバンドに欠かせない要素としてフルートを演奏していた。1971年の「The Musical Box」や翌年の長大な組曲「Supper’s Ready」はプログレというジャンルを確立した大曲であり、彼はそうした曲の中にフルートの音色を織り込んでいた。
一方キャメルは、1973年のアルバム『The Snow Goose』によってイギリスのプログレの一流バンドになった。主としてインストゥルメンタルの曲で構成されたこのアルバムは繊細でメロディアスな内容になっており、そこではギタリストのアンドリュー・ラティマーがフルートを演奏していた。そのおかげもあって、可愛らしいほどに牧歌的な「Rhyader」のような曲には絶妙な味わいが加わっている。
フルートといえば、カンタベリー・ロックも忘れてはいけない。この一派はプログレの複雑さ、ジャズっぽい流麗な演奏、そして風変わりなユーモアをブレンドしており、フルートにも活躍の場をたくさん提供していた。
カンタベリーを代表するバンドとしては、キャラヴァンとソフト・マシーンが挙げられる。前者の主要メンバーであるパイ・ヘイスティングスの弟ジミーは、1971年の「Golf Girl」や1973年の「Memory Lain, Hugh/Headloss」のようなキャラヴァンの曲で明るいフルートの音を響かせている。彼はまた、1970年代初期にソフト・マシーンが録音した2つの名曲にも参加していた。
バップの影響に話を戻すと、カンタベリーとスペース・ロックを融合させたゴングも注目すべき存在だった。このバンドの目まぐるしい演奏では、フランス人ミュージシャンのディディエ・マレルブのとんでもなくスウィングするフルートが欠かせない要素となっていた。彼のフルートは、1973年の愛らしいくらいにイカレた曲「Oily Way」といった曲で前面に出ている。
また先に述べたように、初期ジェスロ・タルのイアン・アンダーソンはジャズの影響を受けていた。それにもかかわらず、「Locomotive Breath」のような不朽の名曲で彼は切迫感あふれる演奏を披露し、そのおかげでフルートはついに本物のロック用の楽器として定着した。
ジェスロ・タルは『Aqualung』や『Thick as a Brick』のようなコンセプト・アルバムが大ヒットした結果、世界中のアリーナを飛び回る人気グループとなった。そうしたライヴのステージで、アンダーソンはソロを吹くときに片方の足を上げていた。そのポーズも、そして彼の刺激に満ちたフルートのフレーズも、クラシック・ロックを象徴する要素となっていった。
ほかの国でも人気を集めるヨーロッパのバンドと言えば、フォーカスも挙げなければいけない。フォーカスはオランダを代表するバンドのひとつとなったが、そうした成功を勝ち取るうえで大きな役割を果たしたのが「Hocus Pocus」だった。
この曲は、鋭く鳴り響くギター・リフからコミック・オペラのようなファルセットへ、さらにはキーボード奏者タイス・ファン・レールが吹くローランド・カーク風の狂乱のフルートへと猛スピードで切り替わっていく。そんな分類不可能な曲調のおかげで、これは世界的なヒットとなった。
とはいえ、ファン・レールは単なる宮廷道化師ではない。フォーカスの最初のシングル「House of the King」のような優雅なインストゥルメンタル曲では、彼は叙情的なフルートを吹いている。この曲は、長年に渡ってイギリスのテレビ番組でテーマ曲として使われていた。最近では、スティーヴ・クーガンのコメディ番組『Saxondale』でも流れていた。
1970年代になると、それまで日陰に追いやられていたほかの楽器の奏者たちも華々しい舞台に出るチャンスを得た。一握りの向こう見ずなエレクトリック・バイオリニストたちにも、運が向いてきた。やがて持ち運び可能なショルダー・キーボードが登場すると、鍵盤奏者たちも大胆な気分になり、リード・ギタリストを嬉々として脇に押しのけた。とはいえ、1960年代に大きな転機が訪れるまでは、フルート奏者が極めつけの負け犬だった。
ロックのスポットライトをほんの少しでも浴びようとしても、フルート吹きには可能性がほとんどなかった。その点では、ほかのどの楽器もフルートよりマシだった。しかし不滅のロックンロール吟遊詩人であるチャック・ベリーも言うように、「何がどうなるかわかりゃしない (It goes to show you never can tell) 」のである。
Written By Jim Allen