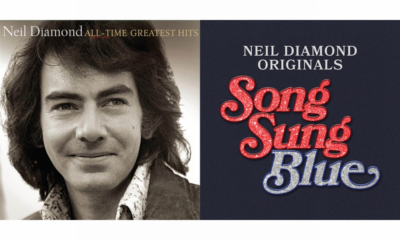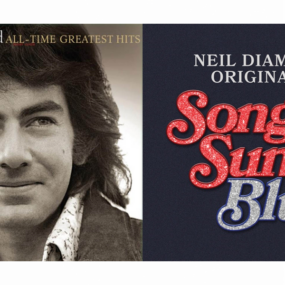Stories
レゲエのプロテスト・ソング傑作11曲:社会/国/権力/戦争/大麻規制/差別について声を上げた曲たち


レゲエのプロテスト・ソングにはさまざまなものがある。たとえば差し迫った危機を不良少年やファンたちに警告したものもあれば、大麻を合法化しようと訴えたものもある。あるいは、政界の闇の勢力と戦おうとしたものもある。いずれにせよ、そうしたプロテスト・ソングの傑作は発表当時たくさんの人の心を動かした。そして今も、聴く人の心に響き続けている。
そうしたプロテスト・ソングの永遠の名曲を今回は11曲紹介しよう。
<関連記事>
・ボブ・マーリー:アルバム制作秘話
・レゲエが世界中のジャンルに与えてきた歴史と見過ごされがちな影響
1. アルトン・エリス&ザ・フレイムズ「Cry Tough」(1967年)
60年代、ルード・ボーイ(ルーディ)と呼ばれる不良少年たちは、持ち上げられることもあれば、こき下ろされることもあった。しかしほとんどの場合、持ち上げられる存在だった。ジャマイカのキングストンのミュージシャンたちは、観客の中にルーディがちらほら混じっていることに気付いていた。そうしたシャープな着こなしのバッド・ボーイたちは、銃撃、強盗、爆破といった悪事をジャマイカのあちこちで行っていた。ジャマイカの音楽では常に時事問題が扱われる。そしてルーディは、音楽の中で持てはやされていた。観客の中にいるルーディは、敵ではないというわけだ。
一部のアーティストは、ルーディを抑圧的な社会システムに反抗する若者として描いていた(たとえばウェイラーズの「Jailhouse」)。また、デズモンド・デッカーの「007」などでは、やがて軍隊による鎮圧が始まるだろうという暗い予測が描かれていた。とはいえデッカーはあくまで観察者というスタンスであり、どちらかに肩入れするということはなかった。しかし1967年にアルトン・エリス&ザ・フレイムズが発表した「Cry Tough」は、立場を明確にしていた。
エリスはルーディを嫌っていた。「Cry Tough」以前にも、彼は「The Preacher」で“ルード・ボーイが嫌いな牧師”について歌っている。また「Don’t Trouble People」では、“人を困らせちゃいけない”とルーディを諭していた。さらに「Dance Crasher」では、ケンカをしたいのなら代わりにボクシングをしろと忠告する。
そして「Cry Tough」では、ロイド・チェンバースが歌う葬いの歌のように深く悲しげなバック・コーラスに乗って、エリスは暗い警告を行った(「ひとりの人間がこの世の中よりもタフになれるものだろうか?」)。これはルーディに理性を教えようとする最後の試みだった。言うまでもなく、それは失敗に終わった。エリスは一部のルーディから脅迫を受け、こうしたメッセージを歌うことを止めてしまう。しかしルーディの名前の多くが忘れ去られても、時流に逆らった勇敢なるアルトン・エリスの名は忘れられることはない。そして「Cry Tough」は、今もレゲエのプロテスト・ソングの傑作として語り継がれている。
2. ジュニア・バイルズ「Beat Down Babylon」(1971年)
ジャマイカのラスタファリアンは自分たちを虐げる「バビロン」、つまりバビロン的な「シットステム」(腐った社会システム)と戦っており、それをテーマとしたレゲエの曲もたくさんある。ただし「バビロン」の代表格である警察と実際に戦うというテーマの曲は、あまり多くはない。その珍しい例のひとつが、1971年にリー・ペリーがプロデュースしたジュニア・バイルズの「Beat Down Babylon」になる。
バイルズは遠回しな言い方をしなかった。ぶっきらぼうなリズム・トラックをバックにして、彼は「奴らをむち打つ」と歌う。なぜなら自分が「飢えて」おり「救済を死ぬほど求めている」からだ。その救済は、抑圧されているあいだは訪れることがない。この曲は革命の火付け役になるかもしれないとバイルズは歌っていた。ある意味、彼は正しかった。この曲はジャマイカでたちまちヒットし、同じリズム・トラックを使った曲がさらに14曲も生まれたのだ。また、この曲をきっかけに、「アイ・アンド・アイ」といったラスタファリアン特有の言葉も世間に広がっていった。バイルズはそうした革命を目にすることなく、暮らしはずっと貧しいままだったが、この素晴らしいシングルがレゲエにもたらしたものは、はかりしれないくらい大きい。
3. ボブ・マーリー&ザ・ウェイラーズ「Rebel Music (3 O’Clock Roadblock)」(1974年)
ボブ・マーリーの名盤『Natty Dread』には、「Get Up, Stand Up」や「War」といった有名な曲が収録されている。そうした曲の陰に隠れがちなのがこの「Rebel Music (3 O’Clock Roadblock)」だ。「Get Up, Stand Up」も「War」もレゲエのプロテスト・ソングの傑作だが、この曲「Rebel Music (3 O’Clock Roadblock)」には特別な重要性がある。なぜなら、これはマーリーやその他のジャマイカ人が耐え忍んできた抑圧を世界に向けて説明した曲だからだ。
当時ジャマイカは、休暇を過ごすのにもってこいの楽園の島というのが一般的な印象だった。しかしボブ・マーリーは貧困層の現実を描き出し、その言葉に耳を傾けるファンを世界中で獲得しつつあった。政治的な緊張、暴力、政治的な嫌がらせ、人種間の対立、持てる者と持たざる者、ドレッドとスキンヘッドの争い、貧困層のすぐそばで暮らす富裕層…、こうしたすべてが重なり、70年代のジャマイカでは耐えがたい抑圧が生み出されていた。それでもマーリーは、「オープン・カントリー」という言葉を使いながら、不平等から来る状況の醜さとジャマイカという島の美しさを対比させていた。
彼は一言たりとも無駄にしなかった。この歌には言葉が詰め込まれているわけではないが、メッセージははっきりとしている。彼はマリファナたばこを1本持っていて、それは誰を傷つけるわけでもないが、夜それを消さなければ逮捕されて痛めつけられるだろう。彼は単に自由になりたいだけだが、そんな自由も許されていない。「俺は出生証明書もないのに」という最後のくだりは、現実のバカバカしさをさらに浮き彫りにしていた。
マーリーは、「Burning And Looting」でも同じテーマを別の角度から描き出している。こちらは、彼の作品の中でもかなり暗く怒りに満ちた歌のひとつだ。ジャマイカでは、抗議の手段としてバリケードや火を付けたタイヤも使われていた。しかしこの歌は、ごく限られた言葉でより多くのことを語っている。レベル・ミュージック(反抗の音楽)とは、一体どういうものだろうか? それを定義したのが「Rebel Music (3 O’Clock Roadblock)」である。
4. ジミー・クリフ「Vietnam」(1969年)
とある評論家から、最高のプロテスト・ソングを挙げてほしいと質問されたボブ・ディランは、ジミー・クリフの「Vietnam」と答えた。その評論家は、きっと当惑しながらその場を離れたに違いない。
1969年に発表されたこの曲は、クリフの個人的な体験から生まれた。ベトナム戦争に召集された友人から、この夏は帰国できそうだという手紙が来た。しかしその友人の母親がやって来て、こう言った。戦地から電報が届いた……と。それは、すべての母親を悲しみのどん底に突き落とすような知らせだった。曲の締めくくりに、クリフはこの戦争は終わらせなければならないと訴える。
この曲は彼の最大のヒット曲ではないし、最高のレコードでもなかった。しかしあの時代を代表するレゲエのプロテスト・ソングの傑作だった。ここでは、誰もが共感できる物語を通して大切なことが表現されている。
5. ジュニア・マーヴィン「Police And Thieves」(1976年)
「Police And Thieves」が何の前触れもなく登場したとき、こんな噂が流れた。ジュニア・マーヴィンという歌手は無名の人間で、あるとき歌のイメージを頭の中で受信した。そこでリー・ペリーにかけ合って、それを録音させてもらった……。
しかしこの噂は真実からは程遠い。録音当時マーヴィンは既に8年間も活動しているレゲエ界のベテランであり、従来の芸名はジュニア・ソウル。あるときクラブで歌っていたところ、リー・ペリーに誘われてスタジオ入りした。そしてペリーがリズム・トラックを準備しているあいだに、歌詞を書き上げたという。とはいえ、確かにマーヴィンの「Police And Thieves」には映像的なイメージがあふれている。武装警官と強盗が抗争を繰り広げ、一般人が恐怖におののく……という物語は、聖書の黙示録にも似た当時のジャマイカの雰囲気をよく伝えている。
この曲は同じ1976年の夏にロンドンでも人気を博し、カリブ諸国の文化を堪能できるイベント、ノッティング・ヒル・カーニバルを象徴する歌となった。このカーニバルで参加者と警官との衝突が大きな暴力沙汰に発展し、まさに歌詞そのままのような状況になったのである。
この曲は1977年にザ・クラッシュがカヴァーし、レゲエを代表するプロテスト・ソングのひとつという地位を確たるものにした。またマーヴィンのヴァージョンも1980年に全英チャート似姿を見せ、マーヴィン本人もイギリスの有名なテレビ番組『トップ・オブ・ザ・ポップス』でパフォーマンスしている。
6. ピーター・トッシュ「Legalize It」(1976年)
「Legalize It」は、ジャマイカでピーター・トッシュ自身のレーベル、インテル・ディプロから発表された。これは、元ウェイラーズのトッシュらしい単刀直入な反抗の歌だった。ここで彼が要求するのは、マリファナの合法化。“判事や医者は自分たちではマリファナを吸っているのに、それを違法にしているのは欺瞞だ”……トッシュはそう主張している。さらに彼は、マリファナは医療でも役に立つし、動物の緊張を緩和させる薬としても使えるとその効用を訴えた(ラスタファリアンの用語では、マリファナは「羊が食べるパン」と言われている)。
これはあまり繊細とは言えない曲だが、トッシュは対決的なアプローチを選ぶことが多かった。レゲエではマリファナを扱った曲はたくさんある(そのひとつ、1970年にリリースされたウェイラーズの「Kaya」のオリジナル・ヴァージョンにはトッシュも参加していた)。しかし彼は、マリファナの合法化をこうしてあからさまに要求するという大胆な手法を選んだ。
当時の彼はウェイラーズを1974年に脱退し、ソロ・デビュー・アルバムの発表を控えて注目を集める立場にあった。そのアルバムは1976年に発表され、「Legalize It」を冒頭1曲目に配置し、アルバム・タイトルもこの曲から採られた。しかしマリファナは……ジャマイカやほとんどの西欧諸国で違法なままだ。
7. ココア・ティー「No Blood For Oil」(1990年)
1990年に第一次湾岸戦争が勃発したとき、それに抗議する曲はあまり生まれなかった。しかしジャマイカの歌手ココア・ティーは、その戦争を徹底的に批判することになった。プロデューサーのマイキー・ベネットと組んだ彼はこの不吉な曲を作り上げ、紛争の核心にまで切り込んだ。しかしこれはジャマイカのラジオでは放送禁止になり、イギリスでも違法な放送局でしか流れなかった。
ココア・ティーがこの戦争を扱った曲はこれだけではない。この曲より前に発表した「Oil Ting」は彼が望んでいたような注目を集めなかった。そこで、さらに上を行く「No Blood For Oil」を作ったのである。レゲエ・アーティストは時には暴力を肯定しているとして非難されがちだが、その中には真面目な主張をする者もいる。とはいえ、ココア・ティーほどはっきりと意見を表明する勇気を持った者は数少ない。「No Blood For Oil」は、このテーマを扱ったレゲエのプロテスト・ソングの中でトップクラスの傑作といえる。同じテーマの他の例としては、グレゴリー・アイザックの「Rude Boy Saddam」が挙げられるだろう。
8. デルロイ・ウィルソン「Better Must Come」(1971年)
デルロイ・ウィルソンの傑作プロテスト・ソングは、こんな歌詞で幕を開ける。「俺は長いあいだ頑張ってきたけれど、いまだに成功していない」。とはいえ彼は、60年代中期からジャマイカの大物歌手のひとりとなっていた。ただし、だからといって彼はその地位に見合った豪邸や高級車を持っていたわけではない。レゲエ歌手の報酬はたいていごくわずかだった。
しかしこの「Better Must Come」で、デルロイはもっと大きな問題を扱おうとしていた。ここで彼は、自分を「抑えつけ」、「弱みにつけこむ」勢力がいると指摘する。そして自分が「最底辺」でないことを神に感謝していた。バニー・リーがプロデュースしたリズム・トラックをバックにしたデルロイのメッセージ・ソングは、ジャマイカで大ヒットした。この国では、貧しい者は仕事をなかなか見つけられず、金もなかなか稼げないのに対し、富める者は左うちわで暮らしていたのだ。
この曲は、1972年のジャマイカ総選挙でマイケル・マンリーの人民国家党のキャンペーン・ソングに採用された。社会主義者であるマンリーはこの選挙で勝利し、総理大臣になったが、その勝利にこの歌が貢献したことは間違いない。さて、ジャマイカの虐げられた人たちの生活は向上しただろうか? まあ、貧困はやはり身近なままだ。しかしデルロイ・ウィルソンがそれを変えたいと心の底から願っていたことは間違いないだろう。
9. ミリー「Enoch Power」(1970年)
保守党の右翼政治家イーノック・パウエルがイギリスへの移民流入を激しく非難し「血の川演説」として知られる演説を1968年に行ったとき、イギリスのコメンテーターの多くがこの演説を非難した。しかし当時イギリスのメディアには、黒人やアジア系の人間がほぼ皆無だった。それゆえメインストリーム・メディアはこうした層の声をほとんど報じなかったし、採り上げようともしなかった。なぜならパウエルが槍玉に挙げていたのはイギリスに移住してくる移民だったからだ。とはいえ、そうした移民たちが何も意見を持っていないというわけではない。しかしその意見が必ずしも予想の範囲内に治まるとは限らない。
イギリスで作られたレゲエのプロテスト・ソングの傑作には、このパウエルの演説を採り上げたものがいくつかある。たとえばフレディ・ノーツ&ザ・ルーディーズの「The Bull」では、DJのロイド・ザ・マタドールが「乱暴な雄牛」であるパウエルに立ち向かっている。またローレル・エイトケンも「Run Powell Run」という曲をリリースしている。さらには何の情報も記載されていない白いレーベルで出回ったシングル「Enoch Daughter」というのもある。ここでは、ある男が黒人女性と「気持ちいいこと」をしたら、その女性がパウエルの娘だとわかった……という卑猥な物語が語られる。陳腐な手法だと言う人もいるかもしれない。しかしここで忘れてはいけないのは、イギリスで黒人が人種差別にずっとさらされ、それが日常になっていたということだ。広く世間の人の耳に入ることはあまりなかったかもしれないが、口汚く罵倒されることは黒人にとって決して珍しいことではなかった。
そうして登場したのが「Enoch Power」だった。1970年、ミリーはニック・ドレイクの「Mayfair」のカヴァー・ヴァージョンを収録したシングルをリリースし、そのB面で「Enoch Power」を発表した。そう、このミリーは1964年に「My Boy Lollipop」をヒットさせたミリー・スモールその人である。
ミリーは次のような物語を描いていく。
イギリスがひどく人手を必要としていたころ、彼女の家族はこの国にやって来て、一生懸命働いた。週末はようやく休息をとり、くつろぐことができる。近所の人も最初は一緒に踊っているが、やがて音がうるさいと苦情を言い始める。スキンヘッドたちはレゲエが大好きだったのに、「イーノック・パワー(イーノックに力を)」と連呼し始めた。スキンヘッドもレゲエを作っている人間と実際に話をしてみれば、共通点がたくさんあるとわかるだろうに……。ミリーは自ら作った歌詞を心を込めて歌っているが、彼女の声はミックスの中に埋もれており、歌詞の内容は聞き取りづらくなっている。このレコードはヒットしなかったが、レゲエのプロテスト・ソングの傑作として今も評価されている。これは、イギリスにいる黒人の声がほとんど無視されていた時代に、彼らの意見を映し出した曲だったのだから。
10. ザ・スペシャルズ「Ghost Town」(1981年)
これはプロテスト・ソングというよりは、国の実情を記録した歌というべきかもしれない。結成当初のスペシャルズが、当時のイギリス都市部の重苦しい情景を不気味な歌詞で描き出しているのだ。とはいえこれは大変な人気曲となり、全英チャートの首位に達した。この曲をジョン・コリンズと共作したジェリー・ダマーズは、サッチャー政権の推し進める新自由主義政策によってイギリス全土でたくさんの人たちが苦しむ様子を見てきた。そして状況が悪くなるに従い、スペシャルズのライヴでも暴力沙汰が起こり、それを目の当たりにしていた。
この曲は、安っぽいシンセサイザーの薄気味悪い音を効果的に使ったアレンジで始まる。ミステリアスな中近東風のリフは、プリンス・バスターのあまり知られていない曲「Seven Wonders Of The World」から借用したものだった。その上に被さる歌詞はたくさんのことを伝えているような印象を受けるが、実のところ具体的な表現は少ない。ただ、働き口の少なさ、互いに争う若者たち、何もしてくれない政府についての論評があるだけだ。それでもなお、メッセージははっきりと伝わってきた。
さて、スペシャルズはこの作品をリリースしたことで社会から感謝されただろうか? その答えは「ノー」。この曲は、1981年の夏に暴動を扇動したとして批判された。しかし「Ghost Town」はこの年を象徴する曲であり、この時代を代表するレゲエのプロテスト・ソングの傑作として今も聴き継がれている。
11. ホーム・T、ココア・ティー、シャバ・ランクス「Pirates’ Anthem」(1989年)
1989年、イギリスの合法的なラジオ局にもレゲエを放送する番組がいくつかあった。とはいえ、レゲエ・ファンの大部分は海賊ラジオ局でレゲエを聴いていた。海賊放送というものは、まさにレゲエの優れたプロテスト・ソングを流すために存在するような形態であり、イギリスの大都市には、海賊ラジオ局が満ちあふれていた。彼らは、逮捕され、機材や貴重なレコードを没収され、多額の罰金を課される危険を承知で、放送を続けたのである。「俺たちは、みんなが聴きたがってるものを放送したいだけなのに」。この曲「Pirates’ Anthem」ではそう歌われている。
「Pirates’ Anthem」は、イギリスのレーベル、クリーンスリーヴズ・レーベルの発案で生まれた。あるとき、海賊ラジオ局の英雄たちを称讃するレコードが存在しないと気付いたのだ。そこでクリーンスリーヴズのスタッフは、関係が深いプロデューサーのガシー・クラークに話を持ち込んだ。クラークは配下のソングライター・チーム、ホープトン・リンド&マイキー・”ホーム・T”・ベネットに曲作りを任せ、海賊ラジオ局のDJが自ら歌っているような感じの曲ができあがった。
これは、クラークならではの簡素でありながら非常に洗練されたダブ・サウンドで録音されている。歌っているのはホーム・T、ココア・ティー、シャバ・ランクスという当時の人気レゲエ歌手たち。シャバは、「DJひとりじゃイギリス全部はカバーしきれない」という歌詞を付け加えている。ここで歌われている「DJひとり」というのは、おそらくデヴィッド・ロディガンのことだろう。ロディガンは、イギリスのラジオ局でレゲエのキャンペーンを繰り広げていたほとんど唯一の存在だった。彼は、イギリス通産省(違法放送局の摘発を担当していた)に対する反抗心も露わにしていた。局をひとつつぶしても、今度は5つ増えるだろう……そう語っていたのである。
この曲はイギリスでは大人気になった、少なくとも海賊ラジオ局では。言うまでもなく合法的な放送局はこれを黙殺した。しかし「Pirates’ Anthem」は、レゲエのプロテスト・ソングの傑作である。なぜなら、これは陽気で好戦的な曲であり、まさに必要とされていたときに発表された曲だからだ。
Written By Reggie Mint
- レゲエ関連記事
- ボブ・マーリーアルバム制作秘話
- レゲエがユネスコによって世界文化遺産に正式登録
- レゲエとジャマイカ:ラスタファリと植民地から生まれたもの
- 英国レゲエ発展記:キングストンからロンドンへ
- ボブ・マーリー:アルバム制作秘話
- ルーツ・ミュージック:ボブ・マーリーの家系図
- ボブ・マーリーはどのようにして銃撃から生き残り、偉業を成し遂げたのか




-400x240.jpg)
-285x285.jpg)