Classical Features
ベートーヴェンはロックスターである。その理由を楽曲と生涯から辿る by 水野蒼生【連載第1回】


2020年はクラシックの大作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生誕250周年の年。そんな彼は現代でいうとロックスターだった?
巨匠カラヤンを輩出したザルツブルクの音楽大学の指揮科を首席で卒業し、その後国内外で指揮者として活躍。一方で、2018年にクラシックの楽曲を使うクラシカルDJとして名門レーベル、ドイツ・グラモフォンからクラシック音楽界史上初のクラシック・ミックスアルバム『MILLENNIALS-We Will Classic You-』をリリース。先日にはベートーヴェン・トリビュートの新作アルバム『BEETHOVEN -Must It Be? It Still Must Be-』を発売するなど、指揮者とクラシックのDJという両輪で活躍している水野蒼生さんによる寄稿、その連載第1回です。
「ジャジャジャジャーン!」
これを読むだけでメロディが勝手に頭に浮かび、その険しい顔を一目見ればその名前がわかる。
ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン。
好き嫌い、関心のありなしに関わらず彼を知らずして一生を終えることは難しい、世界中でもっとも有名な作曲家の一人。しかし彼がどんな人生を送り、なぜ有名になったかを知る人は少ない。ということで、ベートーヴェンの人生を彼の名曲とともに紹介し、どのようにして超有名作曲家になったのかをこの連載で紐解いていこう。

1770年12月、ドイツ(当時の神聖ローマ帝国)のボンに生まれたベートーヴェン。12歳の時からプロとして活動を始めたと言われ、その評判はもはや地元ボンには収まらなくなっていく。新たなステップを目指し、ベートーヴェンは22歳の時に音楽の都ウィーンへ行くことを決意する。
故郷で世話になった友人や恩人たちからの寄せ書きを大事に抱え馬車に乗り込んだベートーヴェンは、「また何倍にも成長した姿で故郷に帰ってこよう」そう心に誓っていたであろう。そして1,000キロも先の当時の文化最先端をいく都ウィーンを目指す。ここから、少年ベートーヴェン が「楽聖」と呼ばれる歴史的大音楽家になるまでの壮絶な物語が始まる。
セルフプロモーション:身だしなみとダンスを習う
何日も馬車に揺られてウィーンにたどり着いたベートーヴェンだが音楽の都ウィーンではまだまだ無名。そんなに簡単にスターへの道はひらけない。まずは売り込み、セルフ・プロモーションが必要だ。どこに呼ばれても恥ずかしくない服と靴を買って、当時の社交会には欠かせない舞踏会のためにダンスの先生も探したりと準備は万端。そんな最初のセルフ・プロモーションは成功し、音楽界に精通する貴族のサロンに何度も何度も出演し、徐々にファンを増やしていく。ピアノ・レッスンの依頼も増えていって収入もなんとか安定してきた。
この頃のベートーヴェンの最大の武器は実は作曲ではなくピアノ。特に即興演奏では右に出るものはいなかったと言われており、ウィーンで既に活躍している名のあるピアニストたちがこぞって即興対決を挑んだが、見事ベートーヴェンはそれらを返り討ちにしていったという。
そしてタイミングが味方した
ベートーヴェンがウィーンに進出した時期(1790年代)は、彼のような若い音楽家がこれからキャリアを積んでいく上ではある意味とてもいいタイミングだった。1791年の暮れ、それまでウィーンに君臨していた大スターのモーツァルトが死んだのだ。モーツァルト亡き後のウィーンの音楽シーンは城主のいない城同然と言える状況で、35歳という若さでこの世を去った大スターの空席を埋めたがるウィーンの市民たちは、次なるスターの誕生を期待してアンテナを張っていた。そんな時期のウィーンに颯爽と現れ、持ち前の即興演奏で周囲を驚かせるベートーヴェンの姿はまさにウィーン市民にとっても注目する存在だったのだろう。
初のヒット曲
ウィーンに来てから6年目の1798年。この頃になるとベートーヴェンはウィーンの人気アーティストの仲間入りを果たし、すでに劇場でのワンマン・コンサートを何度も成功させている。他にもアーティスト同士の交流も増え、欧州数都市のツアーも敢行していたりと、ウィーンだけでなく広く注目を集めていた。そんなベートーヴェンがこの年に発表した自作曲が、ピアノソナタ第8番「悲愴」だ。
この曲はベートーヴェン初のヒットナンバーとなり、発表されるとほぼ同時に大きなセンセーションを巻き起こした。出版された楽譜は飛ぶように売れ、それと同時に保守的な音楽関係者からの格好の非難の的にもなった。否定的な意見が多出するということは作者のファンの枠を飛び越えてこの作品がマスに広がっていったことのひとつの証拠とも言えるだろう。いつの時代もヒット作というものは大きく賞賛されるだけアンチも集まってくるものだ。
「悲愴」大ヒットの理由
「悲愴」の音楽的内容は突出して奇を衒うこともなく、それまでのベートーヴェンの作風から大きく逸れているという訳でもない。その数年前に発表された彼のピアノソナタ第5番を聴いてみるとよく分かるが、この曲は「悲愴」にとてもよく似ている。全ての楽章のキーも一致しているし、展開の仕方、雰囲気まで同じなので「悲愴」はピアノソナタ第5番のアップデート版とも言えるかもしれない。しかしこの第5番はここまでのセンセーションを生むことはなかった。この2曲の間にどんな差があり、その差がどのように作用して「悲愴」がヒットしたのかを考えてみよう。
「タイトル」という概念
ベートーヴェンがこのヒット曲「悲愴」に仕掛けたそれまでとは違った唯一とも言える特異点は、タイトルにある。当時の音楽界では歌詞のない音楽にタイトルをつけることは実はとても稀なことだったのだ。現代でタイトルが知られているこの時代の作品(モーツァルトの交響曲第41番「ジュピター」やハイドンの交響曲第104番「ロンドン」など) のほとんどは作曲家自身の命名ではなくリスナーや楽譜出版社が勝手につけた愛称。ベートーヴェンにおいてもそれは同じで、あの有名な「運命」や「月光」も同じように後世に広まったニックネームなのだ。
そんな、タイトルをつけるという文化がなかった時代にベートーヴェンは自分のピアノソナタに「Grande Sonate pathétique(悲愴的大ソナタ)」と自ら呼び名を与えたと言われている(*本人は了承しただけという説もあり)。当時出回っているほかの機械的な名前の作品の中で、はっきりとしたタイトルのあるこの作品は一際印象に残ったに違いない。そこに作曲家自身のマーケティングの意図があったかは分からないけれど、結果的にこの作品は歴史的大ヒットを巻き起こし、いま現在でも「悲愴」というタイトルのままベートーヴェンの代表曲として広く知られている。ベートーヴェンはその後も交響曲第3番「英雄」や交響曲第6番「田園」などいくつかの作品には自ら名前をつけていて、後の世代に広まる楽曲に名をつけるという文化に大きな影響を与えたとも言えるだろう。
明るい未来はやって来ない
こうしてベートーヴェンはピアニストとしても作曲家としても広く知られるようになり、その名はウィーンだけでなくヨーロッパ全土にも伝わった。ウィーンにたどり着いたその日から順風満帆にキャリアアップを果たしてきたベートーヴェン。他者から見てもその飛ぶ鳥を落とす勢いの若手音楽家の未来は明るく、約束されているように見えたことだろう。
そんな希望に満ちた若きベートーヴェンの前に彼の最大の宿敵「運命」が立ちはだかる。大ヒット作「悲愴」を発表したのと同じ年の1798年、28歳の若さにして聴力の低下が始まった。
Written by 水野蒼生

水野蒼生『BEETHOVEN -Must It Be? It Still Must Be-』
2020年3月25日発売
CD / iTunes / Apple Music / Spotify
- 水野蒼生 アーティスト・ページ
- ベートーヴェンはロックスターである。その理由を楽曲と生涯から辿る by 水野蒼生【連載第2回】
- ベートーヴェンはロックスターである。その理由を楽曲と生涯から辿る by 水野蒼生【連載第3回】
- ベートーヴェン生誕250周年のために浦沢直樹がイラストを描き下ろし
- ベートーヴェン「運命」に合わせて聴覚障害のヒップ・ホップ・ダンサーが躍るMV公開
- 生誕250年を迎えるベートーヴェンの《運命》に合わせて聴覚障害のヒップ・ホップ・ダンス
- ロイヤル・ウェディングに大抜擢されたチェリスト、シェク・カネー=メイソンの35の事実
- ロシア人ソプラノ歌手のアイーダ・ガリフッリーナが、ワールドカップ 開会式に出演
- アンドレア・ボチェッリ、復活祭にミラノの大聖堂で無観客コンサートを実施
- クラシック関連記事一覧
- アンドレア・ボチェッリの20曲
- 史上最高のデュエット100曲











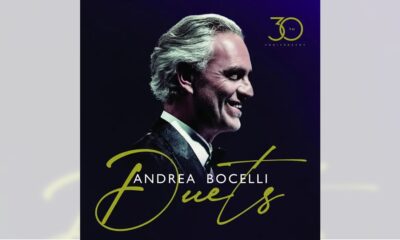
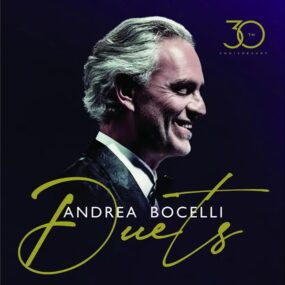










1 Comment