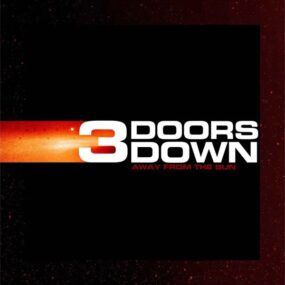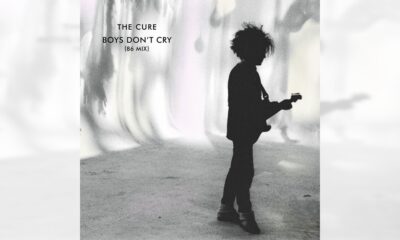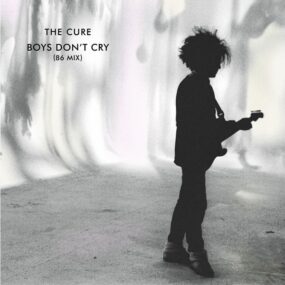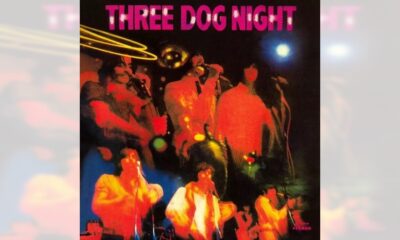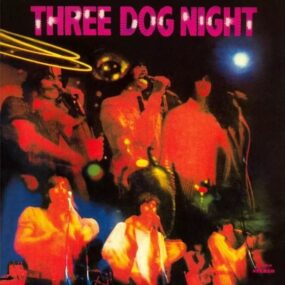Stories
ラインホルト・マックの功績:ドイツ人プロデューサーによるクイーンとビリー・スクワイアの成功作


1980年、プロデューサーのラインホルト・マックはクイーンの代表作である『The Game』を手がけたのち、間髪入れずビリー・スクワイアのブレイク作『Don’t Say No』の制作に参加。マック独自のスタイルは、二組の得意とするパワフルなハード・ロック・サウンドをポップの領域へと導いた。そうして完成した二つのアルバムは当時の音楽シーンのトレンドを決定づけ、そのサウンドと同じくらいスケールの大きな成功を収めたのである。
そこに至る物語は、ジョルジオ・モロダーがドナ・サマーの官能的なディスコ・ナンバー「I Feel Love」の制作を手助けしたスタジオから始まる。そのミュージックランド・スタジオをミュンヘンに設立したのはモロダーだが、マックはその建設に協力し、伝説的なプロデューサーであるモロダーのお抱えエンジニアとして同地で働いていたのだ。
そうしてマックはディープ・パープルやレッド・ツェッペリンらのアルバムに関わり、ハード・ロック界での実績を積んでいった。またそれと同時に彼は、エレクトリック・ライト・オーケストラ (ELO) のシンフォニックなポップ・サウンドを形にする上でも極めて重要な役割を果たした。
<関連記事>
・クイーン『The Game』制作秘話:新プロデューサーの起用やシンセの導入
・映画『ボヘミアン・ラプソディ』が伝えるクイーンについての10の事実
クイーン『The Game』
1979年のある日、モロダーはロサンゼルスでとある噂を口にした。それは、クイーンが次なるアルバムをミュンヘンでマックと制作したがっているという話だった。マックにとってこれは初耳だったが、彼は真偽を自ら確かめるため海を渡った。
そうして対面したフレディ・マーキュリーは当初どっちつかずの態度だったというが、最終的には、ホテルの部屋で書いたばかりの「Crazy Little Thing Called Love (愛という名の欲望)」をマックに披露してくれたのだった。そのあと二人はスタジオでの作業に着手し、ベースのジョン・ディーコンとドラムのロジャー・テイラーも間もなくこれに加わった。マックは2002年、Izotope.comにこう語っている。
「だいたい6時間後には、トラックを録り終わっていた。ギター・ソロはあとからオーヴァーダビングした。ブライアンは、そのパートでテレキャスターを使わせた俺をいまでも恨んでいるよ」
とはいえマックは、グループにとって初の全米1位シングルとなった同曲の賑やかなロカビリー・サウンドに貢献。そうしてクイーンの面々の支持を得た彼は、メンバーたちと並ぶ『The Game』の共同プロデューサーに選ばれたのである。
このセッションからは、さらなる大ヒット曲も生まれた。それが、シックの影響を受けたロジャーのベースラインを中心に進むディスコ・ロック・ナンバー「Another One Bites The Dust (地獄へ道づれ)」である。全米1位に輝いたクイーンのシングルは上述の「Crazy Little Thing Called Love」と、一度聴くと耳から離れないこの楽曲の二つしかない。そんな同曲は、実験的な試みから生まれたのだという。マックはこのように話す。
「“Another One Bites The Dust”はドラム・ループを基にして作ったんだ。この曲にはメインのリフもあれば、逆回しにしたピアノの音や、クラッシュ・シンバルの音、手拍子、ちょっとしたギターのフレーズなんかも入っている。いまではサンプル音源のライブラリに必ず入っているような素材さ。……彼らだけだったら、こんな風にレコーディングをしようなんて考えもしなかっただろうね」
ブライアンも1982年のオン・ザ・レコードの取材でこれに同意している。
「あのときから、自分たちが普通だと思うこと以外にも挑戦してみるようになったんだ。……俺たちはある意味、スタジオでの作業の進め方を一から見直した。それはマックが俺たちとは違うバックグラウンドを持っていたからだ。それまで俺たちは、物事には一つのやり方しかないと思っていた。例えばバック・トラックを録るときも、うまくいくまで繰り返し録り続けることしか知らなかったんだ。……マックの最初の功績は、こんな言葉をかけてくれたことだ。”そんな風にやる必要はない。全部途中からやり直せるよ。30秒時点でミスをしても、同じテンポで演奏してさえくれれば、編集で繋げられるから”ってね」
マックはクイーンの音楽の壮大さに磨きをかけながら、その激しさをいっそう強化することにも成功した。
「俺の心はいつだって、たくさんの余白を残すことと、これでもかと詰め込むことのあいだで揺れ続けている。全部の音をほかの作品より大きくするというのが、俺の大好きなことの一つだったんだ。もちろん、悪趣味にならない範囲内での話だから、あまり気づかれないけどね」
マックはまた、グループの大きな強みや特徴を損なうことなく、クイーンを新たな方向性へと導いた。例えば70年代のクイーンのアルバム・スリーヴには必ず、シンセサイザーの力を借りることなくオーケストラのような壮大なサウンドを作り上げたことが自慢げに宣言されていた。だが『The Game』の1曲目に配された「Play The Game」は、最新鋭のオーバーハイム・シンセサイザーによる宇宙的なサウンドで幕を開けるのだ。
キャッチーなフレーズが満載のパワー・ポップ・ナンバー「Need Your Loving Tonight (夜の天使)」から荒々しいファンク・ロック・チューンの「Dragon Attack」に至るまで、マックは”シンプルなサウンドのクイーン”の形を提示してみせた。だがそれと同時に、『The Game』はクイーンがそれまでに作ってきたアリーナ・ロック・アンセムにも劣らぬほどスケールの大きなサウンドに仕上がっている。
そうした功績を考えれば、マーキュリーが「Dragon Attack」にマックへの賛辞を盛り込んだのも不思議ではない。彼は同曲の中で”Gonna use my stack/It’s gotta be Mack (俺のアンプを使うのさ/やっぱりマックがいなきゃ) “と得意げに歌い上げるのだ。
ビリー・スクワイア『Don’t Say No』
ブライアン・メイは『The Game』の制作中、ビリー・スクワイアのソロとしての2ndアルバム『Don’t Say No』のプロデュースを頼まれたが、やむなくこれを辞退していた。ビリー・スクワイアは当時30歳ながらロックンロール界ではベテランの域に達しており、70年代にはパイパーのフロントマンとして知られざる名作を2作残していた。
1980年のソロ・デビュー作『Tale Of The Tape』がそれなりの注目を集めたことで彼はスターへの階段の入り口には立ったが、同作からもヒット曲は生まれず。それゆえ、次作がスクワイアの命運を分けるアルバムになることは明らかだった。
当初スクワイアはブライアン・メイに同作のプロデュースを依頼したが、ギタリストであるブライアンは『The Game』と、クイーンとして担当した映画のサウンドトラック盤『Flash Gordon』の制作に忙殺されていた。そのため彼は、マックをプロデューサーに起用するよう熱心に推薦したのである。ビリー・スクワイアはのちにギター・プレイヤー誌にそう語っている。
「『The Game』を聴いて、求めていた人を見つけたと確信したよ。クイーンをプロデュースする前、彼はELOのレコードのエンジニアを何度も務めていた。ELOのドラムのサウンドは素晴らしかったし、ジェフ・リンの歌声に存在感があるのもマックの手腕の賜物だ。それにクイーンの『The Game』での彼の仕事は、サウンド面であらゆる可能性を広げたと言っていい。だからミュンヘンから彼に来てもらって、一緒に制作を始めたんだ」
二人はニューヨークにある伝説的なスタジオ、パワー・ステーションで『Don’t Say No』の制作に着手した。そこはブルース・スプリングスティーンやダイアー・ストレイツから、マドンナ、シックまで様々なアーティストたちがレコードを制作してきた場所だ。ビリー・スクワイアはこう語る。
「 (そこには) 目を見張るほど広い、木造の大聖堂みたいな部屋があった。俺がやっていたこととは不似合いな音響の部屋さ。アルバムを聴けばその効果を分かってもらえるだろう」
マックはその部屋の音響を最大限に活用した。そうすることで自然な質感を保ちながら、スケールの大きいアリーナ級のサウンドを作り出したのである。しかし彼は、収録曲に特別なアクセントを加えるためであれば高度な技術を駆使することも厭わなかった。
無骨なサウンドの「The Stroke」はスクワイアをスターダムへと押し上げるヒット曲になったが、その力強いビートには逆回しになったドラムの音も入っている。こうした装飾は、皆無ではないにせよロックのレコードには珍しいものだ。ビリーはこう言う。
「テープを逆さまにして、逆回しにしたまま (ドラマーの) ボビー・シュイナードにドラムを叩いてもらうのはどうかと俺が提案したんだ。マックはそれを聴いてすぐ”別のトラックでもやろう”と言った。結局ボビーは6回くらい同じことをやった。そうやってあのサウンドを作ったんだ
自信に満ちたビリー・スクワイアのテナー・ヴォイスは、フレディ・マーキュリーとロバート・プラントの歌声の中間に位置するようなものだった。そのため、両者と仕事をしたことのあったマックは、彼とスクワイアが形にしていった力強いトラックにその歌声をどう当てはめれば良いかを心得ていた。
それにマックは『The Game』のときと同様、ギターをサウンドの中心に据えながらも、随所でシンセサイザーを効果的に使用した。例えば『Don’t Say No』のオープニング・ナンバーである「In The Dark」は、「The Game」と同じように、湧き上がるようなSFテイストの音で幕を開ける。また、「The Stroke」に続いて全米チャートのトップ40に入った同曲では、アラン・セント・ジョンがうねるような音色のシンセで特徴的なリフを弾いているのだ。
『Don’t Say No』は冒頭から休みなくロックを鳴らし続けるマシンのような作品だ。哀愁に満ちたバラード「Nobody Knows」は、8曲目でようやく登場するのである。だが同作には荒々しいギターと同じ分だけ、紛れもなくポップなフレーズがふんだんに盛り込まれている。一度聴くと耳から離れない「My Kinda Lover」のコーラス・パートや、インパクト抜群の「I Need You」のベースラインはその好例といえよう。
そしてマックは、見事なほど大胆な電子機材のエフェクトや、いい具合に風変わりなベースの音色などでそうした演奏を完璧に引き立ててみせた。しかもそのミックスにおいては、トラックのすべての楽器の音に大きな広がりが感じられる。それはまるで、一つの部屋程度の空間ではなく、3つのベッド・ルームに、二つのバス・ルーム、しっかり整った地下室まであるような空間の広がりなのだ。
マックによれば、その鍵は何より”シンプルに仕上げること”にあるのだという。『The Recording Engineer’s Handbook』という本の中で彼はこう語っている。
「一番シンプルなものだけが伝わるんだ。目玉焼きを作っていたら、家のどこにいてもそれが分かるのと同じようなことさ。だけどフランス料理のシェフがたくさんの材料を使って料理をしても、誰かが何かを料理しているということくらいしか分からない。それが何なのかまでは伝わらないんだ」
80年代初頭、マックはその秘伝のレシピによって、クイーンやスクワイアが作ろうとしているものを世界中に伝える役目を果たしたのである。
Written By Jim Allen
クイーン『The Game』
1980年6月30日発売
CD&LP / iTunes / Apple Music / Spotify / YouTube Music
- クイーン アーティスト・ページ
- クイーンのデビュー盤がデラックス盤で発売
- クイーン「The Night Comes Down」:ブライアンによる優雅な佳曲
- クイーン+アダム・ランバート来日公演初日レポ:才能に情熱が加わった圧巻のステージ
- クイーン+ポール・ロジャース、2005年ツアーからの貴重ライヴ映像が公開
- ブライアンとロジャーが語る、クイーンのライヴでの技術進化と観客の変化
- クイーン初期のアンコール定番曲はエルヴィス・プレスリーの「監獄ロック」
- クイーンのブライアンとロジャーが語るライヴでのアンコールの哲学とファンの重要性
- クイーン、1985年“ロック・イン・リオ”での「Love Of My Life」