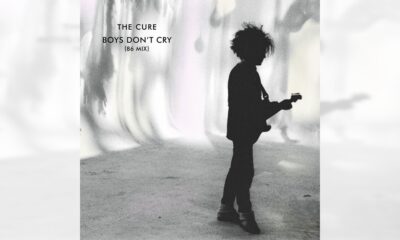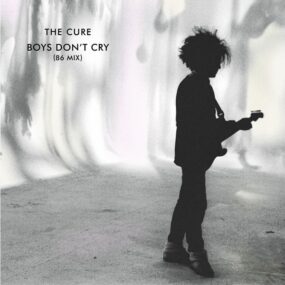Stories
80~90年代「カセット・テープ」を売ったアーティスト達


「カセットテープでのダビングは音楽業界の収入を減らし破滅させる。我々は君達の助けを得るためにあえてこちらの面を空にした」
これがデッド・ケネディーズのカセットEP 『In God We Trust,Inc』で、何も録音されていない裏面に明記されている文言だ。この声明には、自分のカセットにミックスや録音をするアウトサイダー的な背景が含まれている何かがある。実際80年代にこうしたカセットテープでのダビングが音楽業界を破滅に追い込む程のことはなかったが、カセットテープというフォーマットが、これまでメインストリームが耳を貸さなかったような声を与えることになった。
特にプロトゥールスやガレージバンドといった現代の宅録テクノロジーをあえて避け、古いカセットデッキのプレイと録音ボタンを同時に押すことでレコーディングするアーティストにとって、これは事実である。ここでは、このジャンルを語る上で取り上げられる特定のアーティストと、なぜか忘れ去られているアーティスト、双方に敬意を送りたいと思う。
■ダニエル・ジョンストン
テキサス州、オースティンでカセットを売って名を馳せたダニエル・ジョンストンを語らずにローファイ・テープ・ヒーローズについて語ることは出来ない。その手書きのアルバムカバー、耳に付くファルセット、そして子供のおもちゃの様なオルガンの音が即座に彼のそのチャーミングでポップな感性とを結びつけた。カート・コバーンがお気に入りのアルバムに『Yip/Jump Music』を挙げ、『Hi,How Are You』のアルバムカバーのTシャツを着るや否や、レコードレーベルの熾烈な獲得合戦が始まった。この頃、本人はまだ精神病院に入所中の出来事であった。トム・ウェイツ、イールス、フレイミング・リップスなど数多くのアーティストが彼の作品を賞賛し、またトリビュート・カバーアルバムにも参加した。
■ザ・マウンテン・ゴーツ
ローファイ・レコーディング・アーティストの中でも最も多作なアーティストといえばザ・マウンテン・ゴーツだろう。バンド結成時からの唯一のメンバーでありソングライターであるジョン・ダーニエルは、1991年からバンドが消滅するまでほぼ毎年作品を残した。初期の作品は、様々な手法が取られていたが、最も知られているのはパナソニックのカセットレコーダーで録音された 『Full Fource Galesburg』と『All Hail West Texas』であろう。シンプルな構成に短い曲であったが、ダーニエルはストーリーを歌いあげる曲もあり、深みのある歌詞を書いた。彼は楽曲それぞれのキャラクターに感情移入していた。
ゼロ年代中期になると「We Shall All Be Healed」に代表される、自叙伝的な楽曲を作るようになる。さらに、住まいを転々としていたこともあり、「Going To Alaska」、「Going To Chino」、「Going To Wisconsin」等といった「Going To」作品が数多くある。他にも「Alpha+数文字」シリーズ(“Alpha Sun Hat” “Alpha Rats Nest”等 )といったものが初期作品の中には存在する。筆者はザ・マウンテン・ゴーツの作品やソングライティングに関することのみで一冊書けてしまえるのだが、入門盤として『We Shall All Be Healed』がパーソナルで抜けのいいアルバムとしてオススメする。また、徹底的なローファイ体験を望むのであれば、オープニングトラックに「The Best Ever Death Metal Band in Denton」が収録されている『All Hail West Texas』が傑作である。
■ジュリー・ルイン
ローファイ・シーンの上級者ですら、天才キャスリーン・ハンナがビキニ・キル解散後、ル・ティグレ結成までの間に活動していたジュリー・ルインのことは見落としがちだ。現在活動している彼女のバンド「ザ・ジュリー・ルイン」と混同しないように注意しつつ、このジュリー・ルインの作品はキャスリーン・ハンナが40ドルで買ったドラムマシーンを使い、全てを彼女のベッドルームで作曲、レコーディング、プロデュースされたものだ。後にパンク・フェミニスト・エレクトロニック・バンド 「ル・ティグレ」で花開く原型がここにあるように聞こえるかもしれない。確かに、特別な何かがこの作品で顔を覗かせている。
自伝的ドキュメンタリー映画 「The Punk Singer」でキャスリーンは語る。「私は、本当に女性達に向かって直接歌いたいと思っていたの。ベッドルーム・カルチャーというか。女の子が寝室で作ったような音にしたかった。女の子の寝室は、時に本当にクリエイティブな空間になり得るの。寝室の唯一の問題は、完全に切り離されてしまうこと。じゃあ、どうしたら他のこっそりと寝室で、こっそり秘密を書き出して、こっそり曲を書いてる女の子たちとこの切り離された寝室から繋がれるのか? ジュリー・ルインのアルバムは、寝室で作られた音のように聞こえつつ、でもただ捨てられてしまったり、日記に書き記されるだけではなく、ちゃんと人々と分かち合えるものにしたかったの」
■ベック
まだ『Sea Change』もなく、「Devils Haircut」になる前のベックは謎のカセット音源を作ってはロサンジェルスやニューヨークで売りさばいていた。幼少期をLAで過ごした彼は、兄とビート・ジャズを聴き漁るか、ヒップホップを聴きながらブレイクダンスを習う少年だった。ある時点から彼はブルースを発掘し、ニューヨークへと移り住むとアンチ・フォーク・シーンに傾倒する。彼は、最も平凡なネタでも自由な言葉遊びで、他にはない魅力を持った歌詞の書き方を編み出した。すると彼はまたロサンジェルスに戻り、他のバンドも出演するバーや喫茶店に謎な小道具を持ち込み、フォークソングを歌いつつパフォーマンス・アートを繰り広げることで、次第に評判になっていった。
この時期のベックは、カセットを量産していた。ある時、何者かがラップ・ア・ロット・レコードのプロデューサーであるカール・スティーブンソンとボング・ロード・レコードのトム・ロスロックをベックに紹介し、彼らは「Loser」をリリース。そのあとは皆さんご存知だろう。そして、現在でも『Stereopathetic Soulmanure』収録曲でファンにも人気の「Satan Gave Me A Taco」に代表されるカセット期のローファイなベックを聞くことができる。ベックは、未だに自分のようなアウトサイダーなアーティストへの敬意を失わず、ジャンルを捻じ曲げるような実験的ホームレコーディングを続けている。事実として、彼が最も称賛されたアルバム『Odelay』に収録されている「Where It’s At」の中で使われている「That was a good drum break」というサンプルは、次に紹介するアーティストの作品が元ネタになっている…
■ザ・フロッグス
ロックンロール・バンドの中でもローファイの美学を持ちつつ最も卑猥なバンドとしてザ・フロッグスは話題であった。ジミーとデニオン・フレミオン兄弟によってミルウォーキーで結成され、エディー・ヴェダー、ビリー・コーガン、そしてカート・コバーンなどの数多く熱心なファンを獲得していたが、ブレイクするには至らなかった。彼らの曲はどれも短く、キャッチーでありながらも意味をなさず、歌詞は性、人種差別や宗教といったタブーとされる内容を取り上げていた。そうした扇動的な歌詞の内容のせいもあって、ザ・フロッグスの評価は愛されるか嫌われるかハッキリとしていた。当人達は自分達の曲を冗談交じりのつもりでいたが、多くの人は真に受けて批判した。また、フォーク・ロック的な音であるにもかかわらず、あえてグラム的な派手な衣装を着ていた。兄弟の片方は2メートル近いコウモリの羽を生やし、ステージも派手な演出や多くのカツラを被るなどしていた。90年代に入ると彼らのキャリアはピークを迎え、パール・ジャムとマッドハニーのツアーの前座を飾り、ロラパルーザのセカンドステージに出演、ビリー・コーガンがゲスト出演することも多々あった。チャック・ベリーの「Reelin’ & Rockin’」のカバーを含む彼らの3枚目のアルバム『My Daughter, The Broad』は80年代後期の、バンドの即興的ホームメード感がよく表れている作品だ。
■MOTO
マスターズ・オブ・ザ・オヴィアスことMOTOは、唯一結成時からのメンバーであるポール・カポリーノ率いるニューオリンズ出身のガレージ・バンド。彼らも、自分達の名を知らしめる為に自宅でのテープ録音からキャリアをスタートさせ、のちに「ジョークのセンスのいいラモーンズ」と形容されるようになる。初めはデモテープとして録音した音源を、カポリーノは充分な出来だと判断すればそのまま流通にのせていた。曲は異常なほどキャッチーで、随所にジョイ・ディヴィジョン、ブラック・フラッグ、またはザ・ビートルズの影響が伺える。
彼らの曲はこれまた異常な速さで、ライブにおけるカプリーノの曲を始めるカウントが「ワン、ツー、スリー、フォー」の代わりに「用意、構え、撃て」と言わんばかりである。例えば 「Dance Dance Dance Dance Dance To the Radio」や 「Dick About It」といった全く真面目な内容でなくとも、一度聴くと一日中口ずさんでしまう。ユーモアを失いがちなパンクの中で、MOTOは政治的なキレを備えた厨二病ギャグを届けてくれた。
80年代のテープ・カルチャーは、劣悪な音質こそ信頼の証とされた90年代にその美学の栄光を極めた。アナログ録音をしなくなってしまった昨今でも、ウェイヴス、ザ・モルディー・ピーチズ、スレイ・ベルズ等を始めとするノイズ・ロック、ローファイ、アンチ・フォーク・バンド達によってゼロ年代中期においてまたDIYレコーディングの精神は引き継がれている。また、インディー・アンダーグラウンド・シーンの証であったテープ・シェアリングも、この数年でエミネム(The Slim Shady LP )やブリンク182等のビッグ・アーティスト達がカセット・フォーマットでの再発や、カリフォルニアを拠点にしているバーガー・レコードやロンドンを拠点にするポスト・ポップ・レコードといった、小さなレーベルもこのカルト的なマーケットに参入している。このカセットという音楽媒体は死んだと思ったら、実は息を吹き返し、さらにはカセットに特化したフェスが西海岸の San Francisco Tape Music FestivalやオランダのCassette Indoor Festivalなどで行われるまでになっているのだ。
By Joe Dana
♪プレイリスト『オルタナ&インディー』:Spotify