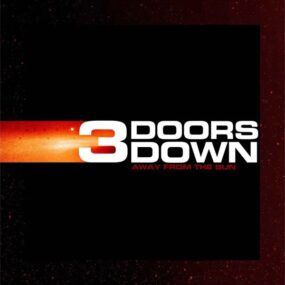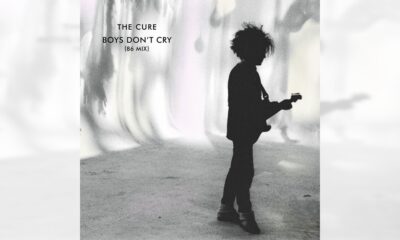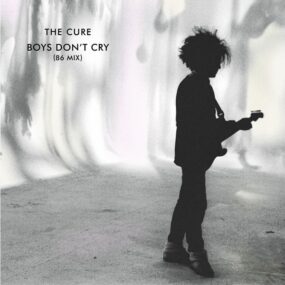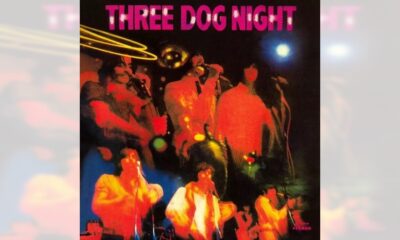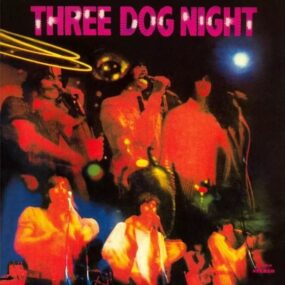News
【特集】グラム・ロックがいかに世界を変えたか:その誕生と退廃を振り返る


70年代の英国は、活気を失い単調になってしまった場所だったと言えるかもしれない。いわゆる“サマー・オブ・ラヴ”の熱狂はとうに色褪せ、それと入れ替わったのが、緊張の高まる北アイルランド情勢や、経済的・政治的危機、そして英国の良き時代は過ぎ去ってしまったという感覚であった。
そこに希少な彩りを添え、従来とは全く異なる種類の文化的進化を引き起こしたのが、グラム・ロック(米国では“グリッター・ロック”という名称がより一般的)だ。グラムは、当時の複雑で退屈な時代精神に対する反発の現れでもあった。そしてまた、音楽シーンには依然として立ち向かわねばならない堅固な境界線が存在していることが、グラムによって一層浮き彫りになったことも、その隆盛の理由のひとつである。
グラム・ロックを押さえつける力が強くなればなるほど、流行に敏感なロック少女達の熱は高まったように思われた。確かにこれは、刺激的で胸が躍る音楽についての話だが、だが同時にそれはまた、アイデンディティの表出や、目を見張るような衣装を身にまとうということ、また不可欠な要素として、挑発的な性的緊張から生まれるスリルについての話でもある。
<関連記事>
・アメリカで唯一100万枚を売り上げたロキシー・ミュージックの『Avalon』
・ブライアン・イーノの20曲
・改名し、時代の寵児となったマーク・ボランと『Electric Warrior』
成熟の途上にあったロック市場を土壌にしてグラムは発酵した。当時のロック市場で支配的だったのは、まるで政治家のような真剣な雰囲気であった。長髪にデニムというファッションに身を包みながらも、自らの音楽作品には極度なほど真面目な若者達は、60年代後半のフラワーパワー・ムーヴメント以降、大きな影響力を及ぼし優位性を享受していたが、ここに至るまでの間に、活き活きとした輝きはすっかり失われてしまっていたようだった。
しかしグラム・ロッカー勢は、その種の人々や、またその前のヒッピー族とは対照的に、世界を変えたいなどとは思っていなかったのである。彼らの望みは、そこから逃避すること。そしてゾクゾクするようなスリルの中で、正道を外れながらパフォーマンス・アートの領域に近づき、豪華で強烈で奇抜で芝居がかった大仰なものを生み出すことであった。
マーク・ボランとT.レックス 魅惑のスーパースターたち
チャック・ベリーやリトル・リチャードといったアクトの派手さは、恐らくグラム・ムーヴメントの起源だったと言える。だが、ミック・ジャガーがそういった50年代アイコンのスタイルの多くを自分のものにしていた一方、正真正銘、グラム・ロック初の本物のスターとなったのは、マーク・ボランであった。音楽業界で成功を掴むことに60年代の大部分を費やしていたロンドンっ子のマーク・フェルドは、1970年を迎える頃、マーク・ボランと改名。自らバンドを率いることにした。そのボラン&T・レックスは、次第に注目を集め始めていく。
その年の秋、ポップなシングル「Ride A White Swan」が全英チャートを駆け上がり、最高位2位を記録。翌年には全米チャートでも小さな足掛かりを得た。10分で書き上げたことで知られる次のシングルは、グラム・ロック特有のサウンドが炸裂する「Hot Love」で、6週間にわたって全英チャート首位の座を堅持。オスカー・ワイルド風の粋なダンディさと、労働者階級らしい不良っぽさとを兼ね備えた、マーク・ボランの痺れるようなスタイルは、BBCの音楽番組『トップ・オブ・ザ・ポップス』の視聴者を釘付けにし、次々と大ヒット曲を連発。それによって彼は真のスーパースターとなった。
マーク・ボラン最大の世界的ヒット曲「Get It On」や、「Jeepster」「Telegram Sam」「Bang A Gong (Get It On)」「Metal Guru」そして「Children Of The Revolution」は、1971年から72年にかけて英国のサウンドトラックとなったのである。
米国での成功にはむらがあったものの、マーク・ボランは国際的な称賛を謳歌し、厳しいレコーディング・スケジュールの合間を縫って、過酷なツアー日程とプロモーション活動をこなしていた。その中には、リンゴ・スターが監督した1972年の映画『ボーン・トゥ・ブギー』への出演も含まれている。
このような仕事のペースからしても、やがて彼が燃え尽きてしまうのは避けられなかったことだろう。70年代半ば、人気に陰りが見え始めた頃、マーク・ボランの体調は徐々に悪化。1977年に自動車事故でこの世を去った彼は、傑作の数々を世に送り出し偉業を成し遂げた人生に、30歳にも手が届かないうちに終止符を打った。
デヴィッド・ボウイとジギー・スターダスト
短い間ではあったが、グラム・ロック・ムーヴメントの中心を占めていたもう1人の“カメレオン”は、デヴィッド・ボウイだ。もちろん、彼ほど並外れた才能の持ち主であれば、ひとつ所に留まることなく、すぐに様々な別方向へ向かうことになるのは必然だ。しかし、ジギー・スターダストという自身のベルソナで、あの時代の感覚を完全に表現した戯画(カリカチュア)性を彼は生み出したのである。
ニューヨークのアーティスト、アンディ・ウォーホルの前衛的な作品から多大な影響を受けたデヴィッド・ボウイは、自身について “様々な事象を感知することが出来る触覚型の思考者”と描写。そして芝居がかった仮の名である「ジギー・スターダスト」を自称し、1972年に「Starman」や「The Jean Genie」といったヒットを続けざまに世に送り出した。
そこには、同年にブレイクを果たしたグラム・スター達から取り入れた、多くのアイディアが反映されている。中性的なルックスでありながらも、リフを多用したポップとロックのブレンドにより、彼は10代の若者だけでなく、より保守的な大人の音楽ファンをも惹きつけた。
1973年夏を迎える頃になると、デヴィッド・ボウイはグラム・ロックから脱却し、次の方向に進む準備が整った。そしてジギーは、伝説のハマースミス・オデオン公演で引退する。
『トップ・オブ・ザ・ポップス』に出演し「Starman」を披露した際、デヴィッド・ボウイがギタリストのミック・ロンソンに腕を回した官能的で思わせぶりなパフォーマンスは、数十年経った今でも、あの時代全体のカルチャーを象徴する瞬間となっている。確かにあれは、挑発的であった。
マーク・ボランの友人だったデヴィッド・ボウイの主張によれば、ジギー・スターダストのインスピレーションの源は、その大部分が50年代のロッカー、ヴィンス・テイラーだったとのことだが、マーク・ボランのT・レックスもまた、そのペルソナを形作るのに一役買ったのは明らかだった。事実を言えば、伝説的なプロデューサーであり、デヴィッド・ボウイが最も尊敬するコラボレーターの1人であるトニー・ヴィスコンティは、この期間、両者とそれぞれ仕事をしている。
このように、デヴィッド・ボウイは他の人々からアイディアを借りたのかもしれないが、彼自身がシーンに多大な影響を与えたことは疑う余地がない。彼は長い間、英国のカルト・バンド、モット・ザ・フープルのファンだった。
1972年3月、スイスでのライヴを最後に彼らが解散する予定だと聞いたデヴィッド・ボウイは、自身が書いた新曲のひとつをバンドに提供すると申し出て、代わりに解散を思いとどまらせることに成功する。それは(短期間だが)功を奏し、新たなレーベルと契約した彼らは、デヴィッド・ボウイがプロデュースした先行シングル「All The Young Dudes(すべての若き野郎ども)」をリリース。全英シングル・チャート最高位3位の大成功を収め、グラム・ロックを代表する歴史的名曲となった。
そしてデヴィッド・ボウイとミック・ロンソンが共同プロデュースした、同名アルバム『All The Young Dudes』を発表。これまでも過激なライヴで評判を得ていたモット・ザ・フープルであったが、バンドは内紛が続き、更に6曲のヒットを飛ばしながらも、メンバーは回転ドアのように入れ替わり続け、1974年末、遂にバンドは解散に至った。
スレイド:スキンヘッドからグラムになり大成功を収めたバンド
こういったヒット曲が次々と生まれたことにより、グラム・ロックは得点を積み重ね、やがてグラム・サウンドは全英チャート入りへの早道だと見なされるようになる。1972年頃になると、週間チャートは、注目を浴びるためにグラムのフックとルックスを取り入れたアーティストで溢れかえるようになった。
そんな中でスレイドは、つい1969年まではスキンヘッド・バンドだったものの、1971年の終わりには「Coz I Luv You」で全英1位を獲得。スキンズ・ファッションのアイテムであるサスペンダーを外した代わりに、肩まで長髪を伸ばし、シルクのジャケットを着込むようになっていた。いみじくもこの4人組は、以前リトル・リチャードのカヴァー曲でちょっとしたヒットを飛ばしていたが、当時の変貌は全く次元が違っていたのである。
現代において想像するのは難しいかもしれないが、スレイドは当時、英国のポップ界に大ブームを巻き起こした一大事件であった。
学校の先生達を憤激させるような誤ったスペルのタイトルで、敢えて無教養さを打ち出した痛快なナンバー「Take Me Bak ‘Ome」と「Mama Weer All Crazee Now」、そして「Cum On Feel The Noize」だ。(「Cum On Feel The Noize」は1983年に米国メタル・バンド、クワイエット・ライオットがカヴァー。その後1995年には、ブリットポップの悪童ことオアシスが再びカヴァー。オアシスのギタリストだったノエル・ギャラガーは当時、ブラーのフロントマンであるデーモン・アルバーンの揶揄に反撃するため「Quoasis」のTシャツを着用していた)。更に「Skweeze Me, Pleeze Me」は全て、僅か24ヶ月の間に全英チャート1位を制覇。ヒットを連発するに従い、彼らの衣装は益々カラフルになっていった。
だが、1973年末に発表した「Merry Xmas Everybody」という永遠のクリスマス定番曲が、バンドのピークであったことがやがて判明、数年後、パンクが勃興する頃には、彼らの成功はほぼ終わりを迎えることになる。だがこれほどまでに愛されたグループが、表舞台から姿を消していた期間は長くは続かなかった。80年代初めには逞しくも全英チャートでリバイバルが起き、その後スレイドは、散発的なレコーディングとツアー・スケジュールを享受している。
スウィート:スレイドの対抗馬
スレイドの対抗馬として張り合っていたのが、スウィートだ。チャートの数字ではスレイドに敵わなかったものの、メイクアップ競争では良いライバルであった。この4人組がテレビ初出演したのは、BBCの『トップ・オブ・ザ・ポップス』の向こうを張って制作された、民放ITVの『リフト・オフ』で、彼らは1971年に「Co-Co」や「Funny Funny」といった軽めのナンバーで本領を発揮。そして1973年初頭には、アンセミックな「Blockbuster」で全英チャート1位の座を5週間に渡って維持し、そのキャリアはピークに達する。
主にシングル・ヒット専門バンドと見なされていた彼らが契約していたのは、ニッキー・チンとマイク・チャップマンのソングライター/プロデューサー・コンビであった。彼らは英国のヒット・チャートを支配するグラム・ポップ・サウンドに塾達。同じくチン=チャップマンが書いたシングル「Blockbuster」は、従来のヒット曲よりも若干ハードなロック・サウンドをしており、バンドのメンバー全員で自分達の曲を演奏した最初のレコードでもあった。
更に「Hell Raiser」「Ballroom Blitz」「Teenage Rampage」と、全英2位のヒットを3連発して成功を収めたももの、自立を望むバンド側と、彼らを操ろうとしていたソングライター/プロデューサー・チームとの間の軋轢は不可避なものに。アーティストとしての幅広い主体性をバンドが求めたため、協力関係は解消された。
1975年の「Fox On The Run」(近年、映画『ガーディアンズ・オブ・ギャラクシー』で使用されリバイバルヒット)で好調なスタートを切ったにもかかわらず、やがてヒットは枯渇し始める。ヨーロッパ大陸での成功は続いていたものの、1978年の「Love Is Like Oxygen」が、彼らにとって最後の花道となった。
ロックだったエルトン・ジョン
今では想像を逞しくする必要があるかもしれないが、エルトン・ジョンもキャリアの初期には、グラム・ロックのサウンドや見た目に手を出している。後年のキャリアでは、よりソフトなバラードが支配するようになったものの、この時代のヒットには「Saturday Night’s Alright (For Fighting)」や、言うまでもなく「Crocodile Rock」といったストンプが含まれていた。
重要なのは、エルトン・ジョンがいかにもグラムらしく見せつつも、彼の滑稽で芝居がかった側面が、ムーヴメントの滅亡に加担していたことだ。
ザ・フーの傑作ロック・オペラ『Tommy』が1975年に長編映画化された際、“ピンボールの魔術師”役を演じたのが、ロケットマンことエルトン・ジョンである。イングランド南部の壮麗な劇場で撮影されたこの作品における、エルトン・ジョンの姿は実に印象的であった。巨大なドクター・マーチンのブーツに、サスペンダー、そしてお約束のギラギラ光るシャツ。エルトン・ジョンのトレードマークであるメガネは特大サイズで、舞台照明が当たるとキラキラ輝き、彼の名高いイメージの形成に一役買った。
同じ年に彼が発表したアルバム『Captain Fantastic And The Brown Dirt Cowboy』には、スウィートやスレイドのようなアクトが採用しても支障がないようなタイプの楽曲やジャケット・アートワークが含まれている。
新たなスター、スージー・クアトロ
グラムの方程式はシンプルに思えたかもしれないが、このジャンルのコレクターに尋ねれば、グラム・ロックの成功の陰には、数え切れないほどの失敗作があったと教えてくれるだろう。RAKを始めとする様々なレーベルが、例えばアイアン・ヴァージンや、スクリーマー、ジミー・ジュークポックスといったアクトに飛びついた。しかし、彼らのリリースした曲は、現在ではお決まりの “ジャンクショップ・グラム”(※直訳すると“中古盤屋グラム”)に分類され、いずれもチャート入りに失敗。
一方、ティーンエイジャー集団のハローは、当時の代表的なもうひとつのグラム・レーベルBellから「Tell Him」と「New York Groov」の2曲のヒットを飛ばしたが、それ以前のアンセム「Another School Day」は見過ごされていた。
チン=チャップマンの圧倒的な力により、RAKは新たなスター、スージー・クアトロを輩出。1973年にはシングル「Can The Can」で全英チャートを制覇した。スージー・クアトロの初期の作品はロックのジャンルにしっかりと収まっており、彼女はプログレッシヴ・バンドのクレイドルでもしばらく活動。興味深いのは、こういったロック指向のアクトが、サウンドにグラム・ロックの飾りを散りばめることによって、どれほど簡単に巨大な成功を収めたかということだ。
その成功は主にヨーロッパ全土に渡っていたが、スージー・クアトロがエルヴィス・プレスリーの「All Shook Up」をカヴァーした際には、プレスリー本人からも褒められ、これは1974年にアメリカでマイナー・ヒットとなっている。
2枚目の全英1位シングルとなった「Devil Gate Drive」以降、スージー・クアトロが首位に返り咲くことはなかったが、困難にも負けることなく彼女はキャリアを歩み続け(チン=チャップマンが手掛けたカントリー調の「Stumlin’ In」は、スモーキーのクリス・ノーマンとのデュエットで1978年にリリースされ、米国で大ヒット)、今日まで注目を浴び続けている。
数々のグラム・アクト
その他、70年代にチン=チャップマンの“ミダス王の手”(※触れるものを黄金に変える魔法の力)の恩恵を受けたアクトには、マッド(Mud)や、前述のスモーキーがいるが、これらは主にポップ・アクトであった。同じように、ゲイリー・グリッターはマイク・リアンダーと組んで金鉱を掘り当て、数々の大ヒットを連発。また彼のバック・バンドだったザ・グリッター・バンドも、1974年に「Angel Face」が全英4位を記録した他、その後2年間で更に5枚の全英トップ10ヒットを飛ばしている。
グラムの影響は、同時代の他のポップ・アクトにも及んでいたことが分かる。例えばスコットランド出身のボーイ・グループ、ベイ・シティ・ローラーズやシルクがそうで、後者には後にウルトラヴォックスのフロントマンとなるミッジ・ユーロが在籍していた。
シルクの「Forever And Ever」は、1976年2月に全英シングル・チャート1位を獲得。この重苦しいバラードを書いたのはミッジ・ユーロではないが、オーケストレーションが施されたウルトラヴォックスのアルバム『Vienna』の壮麗さの起源は、間違いなくここにあると言えよう。
そしてウィザードや、アルヴィン・スターダスト、そしてルベッツも、それぞれ「Angel Fingers (A Teen Ballad)」「My Coo Ca Choo」「Sugar Baby Love」といったグラム指向のポップ・ナンバーで大ヒットを記録した。
ロキシー・ミュージック、大人のためのグラム
ポップ路線を断固拒んでいたアクトの筆頭がロキシー・ミュージックだ。1971年、美大の卒業生ブライアン・フェリー率いるロキシー・ミュージックにシンセの鬼才ブライアン・イーノが加入すると、翌年の終わりにはデビュー・シングル「Virginia Plain」をリリースして全英4位を獲得。その背景には、音楽プレスの幅広い支持があった。
発展途上期にはバンド・メンバーが目まぐるしく交代したものの、バンド名を冠したデビュー作、そして1作目『For Your Pleasure』を始めとするアルバムを通じ、彼らは商業的にも批評的にも着実に勢いを増し続けていく。
バンドと並行して行っていたブライアン・フェリーのソロ活動の方は、より穏やかなものだった(1973年には初ソロLP『These Foolish Things』を発売)が、ロキシー・ミュージックがアートスクール出身であるという信頼性は、時間の経過と共にグラムがポップ寄りの市場を主なターゲットとするようになっていった際、このジャンルの魅力を訴える上で大いに役立った。
70年代が進むにつれ、バンドは次第に円熟味を増して柔和になり、『Avalon』のような後期の作品は、(少なくとも音楽的には)相手の襟首を掴むような初期ロキシーのストンプとはかけ離れたものになる。それでも、バンド結成当初から備わっていた豊かな演劇性により、彼らのファンは大きな違和感を覚えることなくついて来た。ロキシー・ミュージックは大人のためのグラムを生み出し、彼らのオーディエンスは立ち直りの早さと熱烈さを証明することとなったのである。
スパークス、異彩を放つカルト・バンド
パフォーマンスの芸術性に踏み込んだもうひとつのバンドが、スパークスだ。ロンとラッセルのメイル兄弟は、1973年に米西海岸から英国に移住。翌年に発表したアルバム『Kimono My House』は大胆かつ風変わりな作品で、そこからは「This Town Ain’t Big Enough For The Both Of Us」という大ヒットが生まれた。
個性的なスタイルのこの2人は、テレビ番組にとって魅力的な素材で、やがて兄弟は映画にも関心を寄せるようになり、映画『ジェット・ローラー・コースター』を始めとするヒット作に出演。だが、その後も更に「Amateur Hour」や「Get In The Swing」いったヒットを飛ばした。スパークスは現在も活動中で、最も異彩を放つカルト・バンドのひとつであり続けている。
アリス・クーパーのけばけばしい悪名
スパークスとロキシー・ミュージックが、審美眼的に優れたヴィジュアル・センスを発揮していたとすれば、アリス・クーパーはその真逆を行っており、これ見よがしのけばけばしさによって悪名を高めていた。しかし見世物の枠を超えているような存在でありながら、アリス・クーパーは同時に、素晴らしい曲を書くことのできる完璧なショーマンでもあった。
5作目のアルバムに収録されていた「School’s Out」の大ヒットにより、彼は米英の両国でブレイク。同曲は全英1位に輝いた。「School’s Out」の成功を凌ぐことは容易ではなかったものの、続いて「Hello Hurray」や「No More Mr. Nice Guy」といったヒットを飛ばしたことにより、彼が一発屋ではなかったことが証明されている。
米国出身のグラム・ロッカーとして、アリス・クーパーは比較的稀な成功を収めたが、ロンドン・シーンの盛り上がりは、スパークスを始めとする様々なアクトを惹き付け続けていた。
ルー・リードとジョブライアス
1970年8月にヴェルヴェット・アンダーグラウンドを脱退し、RCAと契約した故ルー・リードは、自身の名を冠したソロ・デビュー作のレコーディングのため、英国の首都ロンドンを訪問。同作では大きな前進を果たせなかったものの、デヴィッド・ボウイとミック・ロンソンがプロデュースを担当した2作目『Transformer』は歴史的傑作となり、そこからは名曲ヒット「Walk On The Wild Side」が生まれている。
大西洋を挟んだ米国では、ジョブライアスが、自身のデビューを取り巻く過剰な広告キャンペーンの波に呑まれかけていた。予想通り、やはりロンドンで制作された彼の初アルバムは、このグラム・スターにとっては予想外の不成功に終わり、1975年に彼は引退を発表。しかし、その間に彼がリリースした2作のアルバムは21世紀に入って再評価され、現在は “失われた”グラムの名作と見なされている。
グラム・ロックの拡大
グラムが標榜する“性の政治学”により、米国での売り出しには常に困難がつきまとったが、自立的思考がより強固な東海岸のような地域は、その豊かな基盤となることが証明された。1972年初頭に結成した5人組ニューヨーク・ドールズは、グラムのストンプに過激なソングライティングを融合。トッド・ラングレンがプロデュースした1973年のデビュー・アルバム『New York Dolls』は大成功を収めた。2010年、モリッシーは人生で最も好きなアルバムとして、同作を挙げている。
ストゥージズの作品や、途中で性別が切り替わるキンクスの「Lola」のようなヒット曲が、人々を陶然とさせたグラム作品群の幕開けを示しているとするなら、どこが幕切れだったのか、きっちりとした結末を選び出すことは難しい。
確かに、この時代のポップ指向のヒット曲(例えば、デヴィッド・エセックスの「Rock On」や、エルトン・ジョンの「Bennie And The Jets」等)は、グラム・サウンドに多少の借りがあった。一方、ミュージカル舞台劇として誕生し、1973年にロンドンの劇場街ウェストエンドで初上演された後、1975年に映画化された『ロッキー・ホラー・ショー』は、恐らくグラムがメインストリームに確固たる地位を築いた瞬間であると同時に、その衰退の兆候が現れた瞬間を象徴する作品と言えるだろう。
グラム・ロックの影響
その頃になると、ポップは明らかに先へと進んでおり、グラム・ロックの影響は、間もなく音楽業界を永遠に変えることになるパンクというカウンター・カルチャーに染み込んでいった。ブロンディの初期シングル「Rip Her To Shreds」は、紛れもなく、パンクとグラムのハイブリッドの好例である。彼女達と同じく米国出身のランナウェイズは、カリスマ性を放つデビュー曲「Cherry Bomb」でグラムの要素を借用。
元メンバーのジョーン・ジェットは当時のことを振り返り、スレイドやT・レックスといったバンドのシングルをイングリッシュ・ディスコで聴いていたと語っている。イングリッシュ・ディスコはLAにあったクラブで、グラム・ロック・サウンドのレガシーを後世に伝える上で、大きな影響力を持っていた。
例えばラモーンズの「Sheena Is A Punk Rocker」のような、当時を代表する他の偉大なシングルの中にも、グラムの影響が聴いて取れる。英国では、ビリー・アイドル率いるジェネレーションXがパンクとグラムのハイブリッドを我が物としていた一方、メタルもまた、明らかにその継承者となっていた。
例えばジューダス・プリーストや、後にはデフ・レパード、そしてハノイ・ロックスらが、グラム・サウンドの影響を色濃く受け継いでいる。またアダム&ジ・アンツや、マイク・リアンダーのロックン・ロール曲を初期シングルでカヴァーしていたヒューマン・リーグら、シンセ・ポップの先駆者達による名作の中にも、グラムの演劇性の要素を容易に指摘することが出来よう。
90年代以降のグラム
80年代後半には、ジグ・ジグ・スパトニックの「Love Missile F1-11」のような曲もポップ・ヒットとなった。だが大規模なグラム復興時代が最初に訪れたのは、ブリットポップ・バンドのスウェードとパルプが、過去の時代のからくり箱から多くのものを取り入れた時である。
スウェードが1992年にリリースした2枚目のシングル「Metal Mickey」は全英17位を記録。彼らにとって大躍進となり、翌年のデビュー・アルバムは全英1位を飾った。またパルプは、70年代を舞台に架空のグラム・スターの物語を描いたトッド・ヘインズ監督のカルト映画『ベルベット・ゴールドマイン』(1998年公開)に、「We Are The Boys」を提供している。
20世紀から21世紀への変わり目、ニューヨークのナイトライフではグラムのレギュラー・ナイトが復活。2006年に立ち上げられた<ボウイ・ボール>は、年1回開催の大イベントとなった。
2003年に英国で「I Believe In A Thing Called Love」を大ヒットさせたザ・ダークネス(フロントマンのジャスティン・ホーキンスは、その2年後、スパークスの「This Town Ain’t Big Enough For The Both Of Us」をカヴァー)は、まるでタイムマシンから降りて来たようにも見えた。またゴールドフラップは、グラム・ロックのサウンドを、より現代的なエレクトロの輝きと融合させている。
現代のポップ・アクトの中でも、レイチェル・スティーヴンスは「I Said Never Again (But Here We Are)」でチン=チャップマンのフックを借用。今日、グラム・ロック・ナイトは、米国の東西両海岸とヨーロッパ全土で開催されている。
未来に向けたユートピア宣言
70年代初頭、強大なグラム・ロックが支配した帝国時代は、どんな優れたムーヴメントもそうであるように、あっという間に過ぎ去ってしまったかもしれない。だが、ギラギラと輝くラメに覆われたあのブーツは、後世のミュージシャン達の想像力にしっかりとした足跡を刻みつけた。
かつてスレイドが『トップ・オブ・ザ・ポップス』に出演した際、観覧のためスタジオに詰め掛けていた10代の若者達は、今やその殆どが年金受給者となっている。「若い頃は、どんなことをしていたの?」と、彼らの孫は尋ねることだろう。そう、彼らは踊り、全身をキラキラと飾り立て、現状に疑問を抱き、そして有り余るほどの楽しい時間を過ごしていたのである。
過去に出されたあらゆる類の声明と同様、それが未来に向けたユートピア宣言のように聞こえるなら、そう思うのはあなただけではないはずだ。
Written By Paul Sexton
ロキシー・ミュージック デビュー・アルバム発売45周年記念!
4枚組スーパー・デラックス・エディション2018年2月2日発売!!
- ロキシー・ミュージック、デビュー盤発売45周年盤発売
- アメリカで唯一100万枚を売り上げたロキシー・ミュージックの『Avalon』
- ブライアン・イーノの20曲
- 改名し、時代の寵児となったマーク・ボランと『Electric Warrior』
- T. レックス改名後1発目のシングル「Ride A White Swan」
- T.レックス、2曲目の全英1位「Get It On」の制作秘話
- マーク・ボランの20曲
- ザ・フー 最高傑作『Tommy』
- 史上最高のフロントマンとフロントウーマン50名
- T.レックス、全英シングルチャート1位「Get It On」の制作秘話