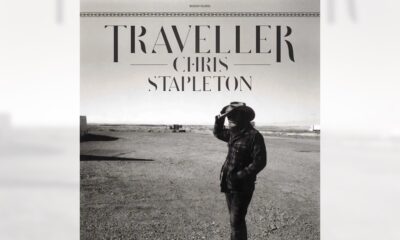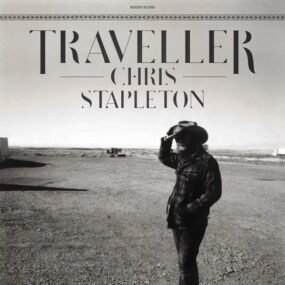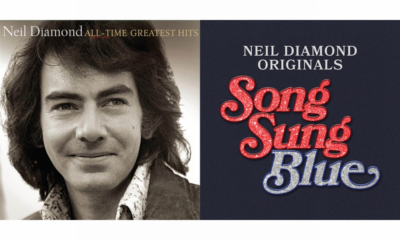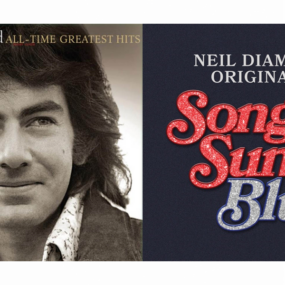Playlists
史上最高のアメリカーナ・アルバム・ベスト10


史上最高のアメリカーナ・アルバム10枚をお勧めする前に、この言葉を定義した方が良いだろう。我々の考えでは、アメリカーナとは、サウンドというよりむしろスピリットであり、間違いなくカントリーとロックの融合をベースとし、そこに反骨的な態度が加えられたものだ。そして恐らくは、コンテンポラリーなカントリー・ポップの大部分よりも、伝統に対するリスペクトが強いだろう。またメイン・ソングライターが、全トラックに影響を与えるような荒いな気質だったとしても、何ら問題はない。こういう言い方をしよう。もしある音楽を聴いて、“ハンク・ウィリアムスならこうしただろうか?”と聞いてみたくなるようなら、それは恐らくはアメリカーナだろう。
と言うわけで、用意はいいかな? さあ史上最高のアメリカーナ・アルバム10選をお届けしよう。
10. クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル『Willy And The Poor Boys』(1969)
クリーデンス・クリアウォーター・リヴァイヴァル抜きのベスト・アメリカーナのアルバム・リストなど考えられない。『Willy And The Poor Boys』は、支配階級を蔑視する一方、共通の価値観を讃えるといったこのバンドそのものを捉えたシングル「Fortunate Son’/‘Down on the Corner」を中心に作られている。その傾向は、CCRの作品中で最もコンセプチュアルなこのアルバム全体に見られる。オリジナル・レコード盤のそれぞれの面には、A面に新しいロックンロール・ナンバー、カントリー/フォーク・カヴァー、インストゥルメンタル、そしてより長くダークな作品が続くという、同一の作りになっていた。最後を飾る3曲は、彼等の最高の瞬間かも知れない。楽しげなゴスペル調の「Midnight Special」、その後にブッカー T&ザMG’sのビートに乗った「Side O’ The Road」、そして最後に登場する「Effigy」は、ジョン・フォガティの最高に時局的で胸騒ぎのするナンバーだ。
9. フライング・ブリトー・ブラザーズ『The Gilded Palace Of Sin』(1969)
もしこのアルバムをすぐに気に入らなければ、アメリカーナはあなたの好みではないのかも知れない。グラム・パーソンズの“コズミック・アメリカン・ミュージック”に対するヴィジョンを具体化したアルバムとして、多方面から称賛された『The Gilded Palace Of Sin』は、完全なるカントリー・ロック・アルバムではなかった。第一に収録されているロックはごく僅かであり、更にオリジナルでない名ナンバー2曲は、スタックス/ヴォルト・カタログからのものだった。また更に、グラム・パーソンズ(そしてバンドの共作者&シンガーの、ずっと過小評価され続けているクリス・ヒルマン)は、混乱の時代のイメージとミステリーが染み渡る、不朽のカントリー・バラードを作り上げている。みなさんはどう感じるだろう? 「Hot Burrito #2」の中の“ジーザス・クライスト”は、単なる叫び声なのか、それとも話し声なのだろうか? アルバムの最後を飾る「Hippie Boy」は、取り上げられることの殆どない曲だが、未来のアメリカーナ・バンド達がみんなやろうとしてきた曲だ。『The Gilded Palace Of Sin』がリリース時に殆ど売れなかったのは、世界の永遠の恥といってもいいだろう。
8. ダグ・サーム『Hell Of A Spell』(1980)
今は亡き偉大なサー・ダグは、自身がロードトリップそのものだった。そう、とにかく…旅だったのだ。いかなるアルバムでもショウでも、彼はカントリー・ミュージック、正真正銘のテキサス・カントリーとメキシコ民俗音楽を融合させた男で、楽しいガレージ・ロック、あるいはその間にあるもの何であれに夢中になっていた。この1980年アルバムは、そんな中でもホーン・セクションでパワーアップしたロック寄りの作品だ。彼はギター・スリムの「Things I Used to Do」といった名作を掘り起こし、自らも数曲書いている。サームは自らが手掛けた名曲を無駄にするのを嫌い「Hangin’ On By A Thread」を、この10年後に発表したダグ自身のバンド、テキサス・トーネイドスのアルバムで、タイトル・トラックにしている。
7. ザ・ネヴィル・ブラザーズ『Yellow Moon』(1989)
アメリカを代表する偉大なバンドは、この1989年作品を発表するまで、ヒット曲を出したことがなかった。プロデューサーのダニエル・ラノワは、雰囲気のある作品で彼等をそんな状態から救済し、ザ・ネヴィル・ブラザーズの潜在的精神性を前面に出した。アーロン・ネヴィルがタイトル・トラックをこっそり用意していたことも、ボブ・ディランの最もヘヴィな2曲で驚くような歌を披露したことも、決してマイナスにはならなかった。しかし見事な腕前を見せたのは、60年代末のリンク・レイのアルバムから「Fire And Brimstone」を引っ張り出したことだった(彼の最も不気味なヴォーカル中心の作品だ)。これはザ・ネヴィル・ブラザーズのブードゥーが詰まったサウンドの理想的な伝達手段になった。彼らは成功し、そして史上最高のアメリカーナ・アルバムとしての地位を維持し続けたが、『Yellow Moon』は彼等のカタログ中では殆ど片手間仕事といったタイプのものだ。その後のアルバムでは、彼等のライヴ・バンドとしてのよりファンキーなサウンドが前面に出ている。そういうこともあり我々は、内容は同様に力強く、雰囲気は遥かにアップビートな『Family Groove』もお勧めしたい。
6. ドライヴ・バイ・トラッカーズ『Alabama Ass Whuppin’』(1989)
何年にも渡り、この作品はドライヴ・バイ・トラッカーズの作品の中で入手不可能だったが、限定版ライヴ・セットが、5年前にようやく再発された。これは好評だった『Southern Rock Opera』や多方面から称賛されたトラッカーズの数々のアルバム発売以前の話だ(そしてジェイソン・イズベル加入前の作品)。しかしこのアルバムからは、強い信念とかなりの非礼でもってオルタナ・カントリーがどのようにして始まったかがうかがえる。今でもパターソン・フッドの代表作のひとつである「The Living Bubba」は、あるミュージシャンのAIDSとの闘いを描いた実話であり、その赤裸々な内容は非常に感動的だ。また「Lookout Mountain」と「18 Wheels Of Love」の両者は、この後に発表されるトラッカーズの抒情詩的な大作を感じさせる一方、ジム・キャロルの「People Who Died」では、彼等のパンク・ルーツにも触れることが出来る。アルバム・タイトルに関するマイク・クーリーの説明だけでも、値段の価値があるだろう。
5. ザ・ロング・ライダース『State Of Our Union』(1985)
このリストに入れた大方のベスト・アメリカーナ・アルバムとは異なり、このアルバムは大ヒットしなかったし、バンドはヒット作に恵まれなかった。ザ・ロング・ライダースはそのことをよく分かっていて、世に受け入れられないことを嘆いていた。グラム・パーソンズとバッファロー・スプリングフィールドを崇拝するバンドにとって、80年代はとにかく良い時ではなかったが、『State Of Our Union』のもつ切迫感はまさにそんなところからきていた。彼等の作品のもうひとつの大きな要素は、パワー全開のガレージ・ロックであり、その全てが12弦に突き動かされた「Capturing The Flag」に集約されている。大げさではなく、ダスティ・スプリングフィールドとフライング・ブリトー・ブラザーズが書いた最高傑作に匹敵するような曲だ。アルバム中もうひとつの聴きどころは、グラム・パーソンズ、ティム・ハーディンと“ルイ・ルイ”が登場する、華やかな「Looking For Lewis And Clark」だ。最終的に成功を収めたザ・ロング・ライダースは、まもなく再結成してニュー・アルバムが発表される予定だ。
4. ロス・ロボス『Kiko』(1992)
『Kiko』は今では、あまりにも誰もが認める名作になってしまった為、発売時の1992年にロス・ロボスのファンにとって、どれほど不思議なサウンドに聴こえたかはつい忘れられがちだ。このバンドがサイケデリアを蘇らせるとは、いったい誰が想像しただろうか? ミッチェル・フルームの、何でも素材にした作品や純粋にオフビートな素材に支えられ、ロス・ロボスはサウンドのコラージュと非線形の物語を思い描き、イマジネーションを駆け巡らせたが、それ全ては幾度かのプレイ後に完全に理解出来るものだった。ここに至るまでには、強烈なブルース・ジャムも何度かあり、最高級のエルヴィス・コステロ調ポップ・ナンバーが少なくともひとつあった(「Short Side Of Nothing」)。これが好きなら、バンドが徐々に現実の世界へと戻って来る前に、次のアルバム『Colossal Head』で、もっと興奮状態に陥ったことをお知らせしておこう。
3. ジョン・ハイアット『Bring The Family』(1987)
ジョン・ハイアットの画期的なアルバム『Bring The Family』は、少なくとも2枚のコンセプト・アルバムがひとつになったものだ。新たに見つけた愛と禁酒を祝った作品だが、彼が再生を果たすまでの混乱ぶりも避けられることなく、「Thank You Girl」や、それから特に「Stood Up」といった曲中に綴られている。これはまた典型的な“オン・ザ・ロード”・アルバムでもある。もし「Memphis In The Meantime」と「Lipstick Sunset」で、窓を開けながら南へと向かう気にならなかったら、何を聴いてもその気にはならないだろう。また『Bring The Family』には、ジョン・ハイアットとギタリストのライ・クーダー、ベーシストのニック・ロウ、ドラマーのジム・ケルトナーから成る偉大なスタジオ・バンドが登場する。リトル・ヴィレッジとしてレコーディングされた、グループ後年のアルバムは、過小評価されることが多いが(主にその非常に軽い感情のトーンゆえ)、見逃してはならない屈指のアメリカーナ・アルバムだ。
2. ルシンダ・ウィリアムス『Car Wheels On A Gravel Road』(1998)
『Car Wheels On A Gravel Road』は、ルシンダ・ウィリアムスのアルバムで押さえておくべき唯一の作品では決してないが、間違いなく最も入手し易いものであり、紛れもない名作が詰まっている。哀歌調の「Drunken Angel」から、堂大胆でセクシーな「Right In Time」やロード・ソング「Metal Firecracker」までと、全て網羅されている。そしてタイトル・トラックには、ルシンダ・ウィリアムスが書いた中で最も印象的なコーラス・フックが入っている。このアルバムが難産だったことが、当時のメディアで多く取り上げられたことで(彼女は納得のいくものが完成するまで3回レコーディングしている)、ルシンダ・ウィリアムスは気難しいアーティストだという認識を持たれるようになった。彼女はそうしたことにもめげず、その後長い間その創造力は衰えることもなく、数多くのベスト・アメリカーナ・アルバムを世に残している。
1. スティーヴ・アール『Copperhead Road』(1988)
このアルバムが登場するまでは、ネオ・トラディショナル・カントリーはクールで、逆に国旗を振るようなサザン・ロックはクールではなかった。スティーヴ・アールは、このふたつを分けておくことが、どれほど馬鹿げているかを指摘した。『Copperhead Road』は嵐を巻き起こした、鳥肌もののカントリー・アルバムであり、厳格で経験豊かな長老のスティーヴ・アールに、こういうのも失礼かも知れないが、この作品の彼はがむしゃらで元気の良い若者のような、素晴らしいサウンドを披露している。この時点でナッシュヴィルに見切りをつけていたアールは、たとえばザ・ポーグスを1曲使ったり、ブルース・スプリングスティーンへの敬意を表して「The Devil’s Right Hand」を取り上げたりと、自分を解放し、気に入った音楽をやるようになっていた。その結果、この史上最高のアメリカーナ・アルバム・リストのトップを、見事に飾るようなレコードが誕生したのだ。見落とされがちなのは、最後を飾る安っぽい感傷は一切抜きのクリスマス・ソング「Nothing But A Child」だ。
Written By Brett Milano
♪ プレイリスト『アメリカーナ・ハイウェイ』