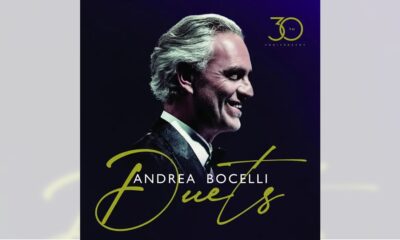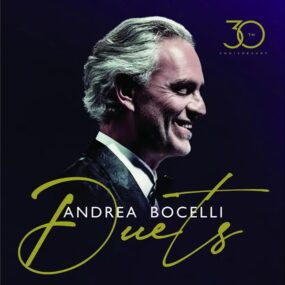Classical Features
ロジャー・イーノ最新インタビュー:新作『The Turning Year』について語る


兄ブライアンとの初のコラボ・アルバム『Mixing Colours』で作曲を担当、そのサウンドはコロナ禍において多くのリスナーの不安や孤独を癒し、大きな反響を呼んだ。その好評を受けて生まれたのが、今回のソロ・アルバム『The Turning Year』だ。シンプルでピュア、親密でありながらも不思議な距離感を保つ音楽の秘密が本人の言葉から見えてきた。
―コロナ禍のご時世、どう過ごされているのでしょうか?
私が住んでいるのは、農地と古い教会がたくさんあるような、まるで産業革命から取り残されたかのようなイギリスの片田舎なんだ。ロックダウンで一時期、車も飛行機も近くを通らなくなった。1940-50年代に戻ったかのようで、とても素晴らしい経験だったね。皆がステイホームしている中、数マイルの近所に住む兄(ブライアン・イーノ)と、前作『Mixing Colours』(2020年)のアルバムカバーを手伝ってもらったDom Theobaldと一緒に自転車を漕ぐのも最高だった。もはや自分には、ガラクタのような安物の携帯も身の回りに置いておく必要がなかったのでロックダウンになって、孤独をより楽しめることができて、自分は何が好きだったんだろう、と考え直すことができたわけだ。
―人前での演奏などはできなかったのでは?
おっと、そのことを言うのを忘れていた。小さいヴェニュー、つまり250人くらいの観衆の前でジョークを交えて演奏するのは好きなんだ。と言うのも、自分の音楽は静かで何も起こらない類の音楽なので、積極的にそうする必要があるんだ。「トイレはあちらです」、とかね(笑)。でも、そういうことは長年やってきたことでもあるし、切望するってほどではないね。
―今回のアルバム『ターニング・イヤー』が生まれた経緯を教えてください。
前述の通り、ドイツ・グラモフォンから兄との共作である『Mixing Colours』をリリースしたのだけれど、今度はソロ作品を出さないかという話になった。試しに作品を聴いてもらったら評判が良くて、ベルリンにある最高のスタジオにて、最高のエンジニア(注:トビアス・レーマン。このインタビューの数週間前に惜しくも急逝)に恵まれ、楽しくレコーディング作業ができた。スコーリング・ベルリンはトップレベルの演奏家集団で、クリスチャン・バズーラは物事を的確に運ぶ、有能なプロデューサーだね。私は一つのことに集中するタイプなので助けられたよ。
―今作の『The Turning Year』ですが、どのような作品を目指して作りましたか?
みんなに何年にもわたって聴いてもらえるような作品を目指したよ。アルバムの最後から冒頭に戻っても、繰り返し聴けるように作ってある。時間をかけて、水の流れが循環するかのような作品にした。
また、情報を詰め込みすぎず、スペース(=余白)作ることを意識したね。元々アルバムタイトルは、各々の曲が物語性を持っているので、ショートストーリーズ(=短編集)にしようと思ったんだけど、受け手が色々と考える解釈の余地があるものにした。また、今回特に日本文化に大変影響を受けている。
―日本文化のどのような点に影響を受けたのでしょう?
西洋にはないアートの捉え方が、本当にたくさんあるよね。物そのものが聖域に満ちている、というアイディアがある。「金継ぎ」のように、少し破損したすることでさらに美しくなるという美学も、本当に素晴らしいと思う。
―サイレントフィルム作品で有名なカール・ドライヤーの『裁かるるジャンヌ』や、劇場のための音楽も作られていますが、そのような経験が生かされているのでしょうか?
特にサイレントフィルムでは、方向性を決めずに即興をするのが好きなんだ。なのであらかじめテーマとなるものを4、5個作っておいて、そのほかはその場で作っていき、長い時間の流れの中で再びテーマを演奏する。すると、オーディエンスは錨を下ろしたような感覚になる。いわば実際にやってみて全体の関係性を考えていくことができるようになる。そのような経験は大きい。

© Cecily Eno
―楽曲について、例えば1曲目の「A Place We Once Walked」ではご自身で新しく作って名前をつけた終止形(注:音楽の段落の終わりを示す、和声進行のパターン。クラシック音楽やジャズ理論に定石がある。Eugenian Plagal Cadenceという名称がつけられている)を使用しています。なんとも不思議な終わり方です。
私の死後、その終止形が音楽の教科書に載っていたら面白いね(笑)。最近はよく古い時期の作曲家たち、レオニヌス、ペロタンを、特にジョン・ダンスタブル(注:中世からルネサンス期に活躍したイングランドの作曲家)を聴く。特にダンスタブルの時代は音楽のルールも違い、終止形も現在とは異なるので、自分の耳を変えてくれるんだ。時代を下って、クープランやラモーらも聴くよ。
どのように終わらせるかは、哲学的な問題だね。本当は永遠に続くと考えている要素を、曲の中でどのように終わらせるか、あるいは何を続けていくべきなのか。曲が順序よく進行するとき、何をフェードアウトさせ、何を拾い上げるべきなのか。
また、宙吊りにさせるような感覚が好きなので、特にピアノをペダルで踏んで鳴らして生じる、倍音がたくさん含まれたアコースティック楽器の響きにも興味があるんだ。
リスナーに未だ受け入れたことのない、オープンチャレンジ(注:開かれた挑戦)をするのは好きではなくて、聴きやすいのだけれど、何か問いを与えられたような気にさせる音楽が好きなんだ。
―時間が宙吊りになっていることに加え、楽曲に、表現に独特の「曖昧さ」があるように感じます。
一般的によくやる手法に、長調や短調を混ぜることがあって、それはもちろんやっている。その上で、雰囲気の曖昧な表現を心がけているんだ。物事が明るい方向になるよう願ってはいるけれど、この血生臭い世界を受け入れること、それらを混ぜた表現がある。また、憂鬱な雰囲気に楽観的な雰囲気を混ぜることによって、何かを強く熱望するような感覚にさせることができたりもする。
一般に、例えば短調には悲しさがあるなんていうけど、何がそうさせるのだろうか?音楽で何を伝えることができるのか、ということをいつも考えているんだ。あまりにわかりやすい音楽は好きではないね。
―リスナーには、どのような環境下であなたの音楽に接して欲しいでしょうか?
ヴィジュアルなものの背後にある音楽が好きなんだ。それは映画でも、ダンスでもね。座って集中して音楽を聴くようなことは滅多になくて、何か作業をしている中で流れる音楽が好きなんだ。エリック・サティの言うような、「家具の音楽」だね。部屋の一部や家の一部であるような音楽だ。

© Cecily Eno
―サティとあなたとの関係についてもう少し詳しく教えてください。何がご自身と似ていると思いますか?
サティを聴いて、初めて自分で作曲したいと思ったんだ。あれほど美しい音楽が、ミニマルな要素だけで作れることに驚いたよ。ラフマニノフのオーケストラ作品のように技巧に満ちたものには惹かれなかった。これを聴かなくてはダメだ、練習は1日何時間、といった拘束に縛られることもない。
サティは、絶妙な作品を作るのに、ほんの少しの音しか使わないんだよね。サティと私とで似ているところは静寂さを好むことと、お酒をたくさん飲むので、ユーモアがあると言うことだね(笑)。
―どういうバックグランドを経て、今のあなたがあるのでしょうか?
私は今62歳だけれど、12歳のときにコルネットに出会って世界は完全に変わってしまった。それから、オーケストラ、合唱、パンクバンドではベースを経験した。また、ジャズバンドでピアノを弾き、フォークバンドでアコーディオンを弾く、なんてこともした。するといろんなジャンルの音楽が見えてきた。あらゆる経験が、今の曲作りに生かされているのだと思うよ。
Interviewed & Written By 大西 穣
■リリース情報

2022年4月22日発売
ロジャー・イーノ『The Turning Year』
iTunes / Amazon Music / Apple Music / Spotify
- ロジャー・イーノ アーティスト・ページ
- ロジャー・イーノ オフィシャル・ページ
- ロジャー・イーノがアルバム『The Turning Year』を4月22日にリリース
- ブライアン・イーノとロジャー・イーノ兄弟による初のデュオ・アルバム『Mixing Colours』発売
- ブライアン・イーノの集大成『Music For Installations』とは何か?
- ブライアン・フェリーがイーノとの音楽制作を望む
- ブライアン・イーノの20曲:アートとアヴァンギャルドの重要性