Stories
カントリーやルーツ音楽はいかにして「アメリカーナ=最もクールな音楽シーン」となったのか


2011年、「アメリカーナ(Americana)」という単語がかの権威あるメリアム=ウェブスター大学辞典に掲載されることになった時、アメリカーナ・ミュージック・アソシエーションのエグゼクティヴ・ディレクター、ジェド・ヒリーはこの単語が胸に大きく書かれたTシャツを発売すると冗談を飛ばし、更にその脇に添えて“Look it up!(検索してみて!)”というタグラインをあしらうのだと語り、そして次のように付け加えて。
「だって、まだピンと来る人は少ない言葉じゃないですか。何しろ我々は決してバカ売れしているというわけではないですからね」
その後、アメリカーナ・ミュージックという名実共にホットな属性の台頭により、アメリカの音楽シーンの景色は変貌を遂げていた。クリス・ステイプルトンのアメリカーナ・アルバム『Traveller』は、150万枚近いセールスを挙げ、2016年の年間ベストセラー・アルバム・チャートにおいてアデルやビヨンセ、リアーナといったポップ界のメガ・スターに迫る堂々の第7位を獲得したのである。
<関連記事>
・テイラー・スウィフトのベスト30:カントリー界から世界的ポップスターへ
・アメリカーナのサウンドを追い求める、12組の若きアーティスト達
・モーガン・ウォーレンはなぜアメリカでここまで爆売れしているのか?
アメリカーナの定義とは?
メリアム=ウェブスター大学辞典の定義によれば、アメリカーナとは「初期フォークやカントリー・ミュージックにルーツを持つアメリカン・ミュージックの1ジャンル」とされる。
これらのルーツが包括する範囲は実に広く、カントリーやウェスタン、アパラチアン[訳注:北米東部のアパラチア地方のローカル色濃い音楽で、主にイングランドのバラッド、アイリッシュ及びスコティッシュ・トラッド(特にフィドルが使用されたもの)、賛美歌、そしてアフリカン・アメリカンのブルースの要素が混ざり合って生まれたもの。モダン・ブルーズの源流のひとつ]、ゴスペル、ルーツ・ロック、フォーク、ブルーグラス、R&B、そしてブルースまでもが含まれている。アメリカーナに分類されるバンドは通常アコースティック楽器メインで演奏を行なうが、フル・エレクトリックのバンドも存在する。
かつてカントリーやアメリカーナ・ミュージックの基盤を形成してきたのはフォークやゴスペル・ミュージシャンたちだったが、現在のような流れに向かう原型は、1920年代から30年代のウェスタン・スウィング・ムーヴメントと、その象徴的存在で、30年代にいかにもテキサス的な音楽性で全米規模の人気を博したボブ・ウィルスにその一部を垣間見ることができる。
ボブ・ウィルスと彼のテキサス・プレイボーイズによる代表曲 「San Antonio Rose」は今日までに何百回となくカヴァーされ、その顔ぶれもジョン・デンバーからクリント・イーストウッドまで錚々たるものだ。ボブ・ウィルスはウィリー・ネルソンにも直接的な影響を与え、彼の中に音楽に対する寛容な考え方を根付かせる助けとなった。
ハンク・ウィリアムズと彼の影響
ウィリー・ネルソン自身、ボブ・ウィルスに対しては惜しみない賛辞を捧げているが、彼がそれより更に大きな影響を与えられた人物としているのが、アメリカ音楽界における正真正銘のパイオニアのひとり、ハンク・ウィリアムズだ。
1953年1月、29歳の若さでこの世を去ったハンク・ウィリアムズは、「Hey, Good Lookin’」や 「Why Don’t You Love Me?」「Long Gone Lonesome Blues」を含む29曲のレコードをヒット・チャートに送り込むなど、その短い生涯で驚くほど多くのことを成し遂げた。1999年、スミソニアン協会が開催した史上初のカントリー・ミュージックに関するフォーラム、その名も『A Tribute To Hank Williams』において、この謎多きアイコンはあらためて先駆的存在として讃えられ、モダン・カントリー・ミュージックの礎の構築に対する功績を認定されたのである。
多くの戦前のミュージシャンたち同様、故郷であるアラバマの教会の聖歌隊で歌うことを覚えたハンク・ウィリアムズの音楽には、ウェスタン・スウィング、アパラチアン・マウンテン・ミュージック、ホンキー・トンク、カントリー・ブルースやゴスペル等、生まれ育ったディープ・サウスの環境特有の様々な音楽スタイルがまとめて凝縮されていた。
だが、彼がとりわけ優れたソングライティングの匠として、その他大勢と一線を画すことになったのは、心乱される「Lovesick Blues」のような告白調の歌を書くことができる、稀有な天賦の才能の賜物である。
ハンク・ウィリアムズはその直截的かつ哀調に満ちた歌詞により、市井の人々の激しい内なる感情や夢、心の疼きを表現したアメリカ最初のシンガー・ソングライターのひとりだった。レナード・コーエンは彼のソングライティングを「至高」と評価し、またボブ・ディランは「ハンクの曲はポエティックなソングライティングのお手本そのものだ」と語っていた。ハンク・ウィリアムズの作品はルイ・アームストロングからエルヴィス・プレスリー、アル・グリーンに至るまで、幅広いアーティストにカヴァーされている。
ハンク・ウィリアムズはまた、数え切れないほどのミュージシャンたちにインスピレーションを与えてきた。例えば一枚丸ごとこのアイコンに捧げるアルバムを出したカントリー界の巨人ジョニー・キャッシュ、シンガーのジョージ・ジョーンズ、グラム・パーソンズのようなクリエイティヴなアーティスト、そしてベックやキース・リチャーズ、トム・ペティらモダン・ロックのスターたちにもハンクの影響は及んでいる。
ライアン・アダムスと彼の一派である80年代から90年代のオルタナ・カントリーのスターたち が進むべき方向を模索していた時、拠り所としたのはやはり「I’m So Lonesome I Could Cry」のような名曲が書けるこの男だった。ルシンダ・ウィリアムスいわく、「私は物心ついた時からずっとハンクの歌を聴いてきた。彼の音楽は多分、私が最初に触れた音楽のひとつだったんじゃないかな」。
大酒飲みで歯に衣着せぬ物言いのウィリアムズは、恐らくカントリー・ミュージック界における最初の反逆児で、その特性はカントリーのメインストリームにパンク・ミュージックのアティテュードを持ち込んだ70年代のアウトロー・カントリー・スターを標榜する面々にこぞって模倣されることになった。その意味ではハンク・ウィリアムスは、アメリカーナという呼称が当たり前に使われるようになる今から70年も前に、既にそれを体現する存在だったと言えよう。
グラム・パーソンズ
複数のジャンルがぶつかり合えば音楽は変化する。時代を先取りして様々な音楽の糸をたぐり、撚り合わせてみせたもうひとりはイングラム・セシル・コナーⅢ世、芸名グラム・パーソンズと名乗った男だ。
フロリダ生まれのグラム・パーソンズは、子供の頃からエルヴィス・プレスリーの大ファンで、60年代初頭に通っていたジャクソンヴィルのバールズ・ハイスクールで最初のバンド、ザ・ペイサーズを結成する。同じ学校に通い、後にユニバーサル ミュージック・ナッシュヴィルの社長となったルーク・ルイスは、レイ・チャールズの1962年のアルバム『Modern Sounds In Country And Western Music』(この作品自体が最初期のアメリカーナ・ミュージックの素晴らしいひとつの原型でもある)を聴いたことが、彼ら2人に絶大なる影響を及ぼすことになったと語る。
「恐らくあれが、我々2人のどちらにとっても、カントリー・ミュージックとは何なのかを多少なりとも知る最初のきっかけだったんじゃないかな」と後にライアン・アダムスやルシンダ・ウィリアムス、ジョニー・キャッシュらのレコーディングに立ち会うことになったルーク・ルイスは語っている。
グラム・パーソンズが最初にシーンにインパクトをもたらしたのは、時代を超えた名曲 「Hickory Wind」を提供したザ・バーズとの仕事だった。彼は未熟だったバンドのアルバム『Sweetheart Of The Rodeo』で重要な役割を果たした後、1969年にはクリス・ヒルマンと共に戦列を離れ、フライング・ブリトー・ブラザーズを結成。
彼らはトラディショナルなカントリー・ミュージックとロックをミックスした音楽をプレイしており、最初の2枚のアルバム『The Gilded Palace Of Sin』と『Burrito Deluxe』で “コズミック・アメリカン・ミュージック”と称されるスタイル誕生のきっかけを作った。クリス・ヒルマンはこう証言している。
「フライング・ブリトー・ブラザーズとグラム・パーソンズが遺した最大の功績は、オルタナティヴ・カントリー・バンドという俺たちの地位だね。俺たちの音楽はカントリー系のラジオでもかからないし、ロック系のラジオでもかけてもらえなかった。ほんの僅かの間ではあるけど、俺たちは正真正銘のアウトロー・カントリー・バンドだったんだ」
フライング・ブリトー・ブラザーズの音楽はカントリー、ロックン・ロール、R&B、フォーク、そしてソウルの影響を見事に結び合わせたもので、これだけポテンシャルの高い音楽を生み出せたことに、グラム・パーソンズは自信を深め、当時のグラム・パーソンズは音楽的に成長するためのあらゆるチャンスを貪欲に求めていた。1971年夏、フランス南部に向かった彼は、当時ザ・ローリング・ストーンズが名盤『Exile On Main St.(メインストリートのならず者)』の制作にかかっていたヴィラ・ネルコートで、旧友キース・リチャーズの客人として短期間滞在していた。
グラム・パーソンズはキース・リチャーズと共にカントリー・ミュージックをプレイし、自身の音楽的視野を広げることを学んだ。ザ・ローリング・ストーンズは自分たちのヴァージョンを発表する前にフライング・ブリトー・ブラザーズが 「Wild Horses」のカヴァーをレコーディングすることを許可している。ミック・ジャガーとバンドは、グラム・パーソンズがソロになる上で大いなる後押しとなったと言われる。「この男は何か凄いことをやらかすんじゃないかって、予感がしてたんだよ。何となくね」とはキース・リチャーズの弁である。
彼のソロ・アルバム、『GP』と『Grievous Angel』はいずれも出色の出来で、シンガーとして参加したデビュー直後のエミルー・ハリスにとってはその後のキャリアの助けにもなった。 彼女はグラム・パーソンズのカントリー・ミュージックに対する造詣の深さに驚いたとこう語る。
「私はあのカントリー・ソングを全部憶えた。まるで改宗者みたいな気分だったね。もっともっと知りたい、覚えたいってね」
クリス・ヒルマンは 「Sweetheart Of The Rodeo」のような曲によって、グラム・パーソンズがカントリー・ロックやオルタナティヴ・カントリーと通じる堰を一気に開け放ち、それが後のアメリカーナ・ブームへと繋がったと分析している。
グラム・パーソンズ自身は、音楽には良いか悪いかの二択しかなく、音楽のタイプについて「定義づけしたり分類したり」することに頭を悩ませる必要はないという考えの持ち主だった。1973年、僅か26歳で訪れた彼の早過ぎる死は、この世界から開拓者魂を持ったミュージシャンを奪い去ったが、彼の影響は他のミュージシャンたちとの仕事や、ザ・グラム・パーソンズ・ファウンデーションでの作品を通して、彼の軌跡に続くアメリカーナ・ミュージックにずっとちらついている。
ライアン・アダムスやウィルコのジェフ・トゥイーディの初期の作品でも、「Sin City」や 「One Hundred Years From Now」といった曲からの影響はハッキリと分かるはずだ。
“ノース・アメリカーナ”なザ・バンド
グラム・パーソンズがハンク・ウィリアムズについて学んでいたのと時を同じくして、ザ・バンドのロビー・ロバートソン、リヴォン・ヘルム、ガース・ハドソン、リチャード・マニュエル、そしてリック・ダンコの面々はザ・ホークスというバンドで腕を磨いていた。
彼らはロカビリー・シンガーのロニー・ホーキンスのバック・バンドとしてスタートしたが、間もなくバンド単体で道を切り拓くことを選択し、ザ・ホークスの初期のファンからすれば予想もしなかったような大物バンドへと成長していく。ロビー・ロバートソンはこう語っていた。
「俺たちはザ・バンドとして、ここまで経験してきたすべてを結集した音楽をプレイしようと決めたんだ。この辺のゴスペルからちょっと拝借、あの辺のマウンテン・ミュージックからも、ここらのデルタ・ブルーズからも、そこらのシカゴ・ブルーズからちょっと戴きって具合にね」
ザ・バンドが1965年から66年にかけてボブ・ディランと行なったツアーは、アメリカのポピュラー音楽史において最も大きく流れを変えるきっかけを作った悪名高きツアーだった。フォーク・ミュージックをエレクトリックの時代に移行させようというボブ・ディランの決断は大いに物議を醸すことになったのだ。ザ・バンドは気持ちよさげに自由な音楽の翼を広げ、アメリカの音楽の進化に彼らなりの貢献を果たした。それから数十年後、ロビー・ロバートソンはこんな告白をしている。
「みんなに言われたよ、お前らはアメリカーナだろって。それに対して俺は、『俺たちはカナダ人だよ。まあ、ノース・アメリカーナかも知れないけど……』なんて応えてたんだ。俺は多分、いまだにそれが何なのか分かってないと思うよ」
彼ら独特の“ノース・アメリカーナ” という言葉にはカナダ人バンドらしい精緻さが宿り、とりわけ「Up On Cripple Creek」「The Weight」そして 「The Night They Drove Old Dixie Down」のような現代の名曲の中には、のどかで抒情的なアメリカ南部の神話の記憶が刻まれている。
ザ・バンドにはロビー・ロバートソンの比類なきソングライティングの技術とリヴォン・ヘルムのソウルフルな歌声、キーボーディストのガース・ハドソンの音楽的万能さがあった。1968年にリリースされた彼らのデビュー・アルバム『Music From Big Pink』は、エリック・クラプトンやグレイトフル・デッドといった同時代のミュージシャンたちを、よりルーツ志向のサウンドへと駆り立てた。
マーティン・スコセッシが監督を務めたかの有名なコンサート・フィルム『ラスト・ワルツ』の中で、彼らはヴァン・モリソンやジョニ・ミッチェル、マディ・ウォーターズからニール・ダイアモンド といったアーティストたちのバックを見事に務め上げ、誰と何をプレイするのも自在であるその実力を見せつけた。
エリック・クラプトンが初めて彼らの演奏を聴いたのは60年代末だったが、それは彼のクリームに対する幻滅へと直結するターニング・ポイントとなった。ちょうどザ・バンドがサイケデリアに対する反動として原点回帰のサウンドを打ち出したように、エリック・クラプトンは反動としてブラインド・フェイスを結成し、更にその後、スライド・ギターの名手デュアン・オールマンを擁するデレク&ザ・ドミノズで、より深くアメリカーナを追求してゆくことになる。
ちなみに2017年、エリック・クラプトンはトロント国際映画祭のオーディエンスに向かってこう述べている。
「その昔、イングランドでアセテート盤の『Music From Big Pink』をもらった私は、それを聴いて芯から揺さぶられるような衝撃を受けたんだ。当時の私はクリームにいて、その時既にバンドが本来行くべき方向に行っていないという感覚があったんだけど、これこそ自分の進むべき道だと思ったんだ。ロビー・ロバートソンという人物を知ってはいたが、その時にはあれが彼のグループだとは知らず、まるっきりポッと出のバンドだと思っていたんだ。てっきりミシシッピ・デルタあたりから出て来たものとばかり……彼らは私の目に威風堂々たるヒーローに見えたんだよ。彼らとジャムしに行ってみると、彼らはこう言った。『俺たちはジャムはやらない、自分たちで曲書いてそれをプレイするんだよ』。私はナンてこった、こいつらは本当に本気だぞ、と思ったものだ」
1999年、運命の輪がようやくひと巡りした頃合で、リヴォン・ヘルムはアメリカーナ・ミュージック・フェスティヴァル・アンド・カンファレンスの一環としてライヴ・アルバム『Ramble At The Ryman’ 』をレコーディング。
このイベントは彼のアメリカーナに対する影響と、ザ・バンドがライアン・アダムス、リー・アン・ウォマック、ロザンヌ・キャッシュやオールマン・ブラザーズ・バンドらに直接的なインスピレーションを与えてきたことを讃えるために催されたのである。
80年代のアメリカーナ
ここまで見てきた通り、アメリカーナのアイコンにはカントリー・ミュージックの父祖や母も含まれており、ボブ・ウィルスやハンク・ウィリアムズ、ウディ・ガスリーにパッツィー・クラインといった偉人たちもそこに数えられる。
だが70年代や80年代に出てきた近代の巨匠たちの中には、自分たち独自のレガシーを生み出そうとする人々がいた。ガイ・クラークやグレン・キャンベル、ドン・ウィリアムズ、ドリー・パートン、ジョン・プラインにアラン・ジャクソンらは、いずれもその溢れんばかりの才能で自分なりのフィールドを切り拓いてきたアーティストたちだ。
一方、アメリカーナ界のスーパーグループと呼ぶに限りなく相応しいものが登場したのは1984年のことだった。当時は既にナッシュヴィルのソングライティング・シーンではベテランの域に達し、ジャンルを超えて現代における最も傑出したミュージシャンのひとりとして認められる存在となっていたウィリー・ネルソンが、カントリー・ミュージックに新たな方向性を示す触媒となり、あえて“アウトロー”としてバンドを作ろうと、自分とほぼ同格であるカントリーの大御所ジョニー・キャッシュ、ウェイロン・ジェニングス、クリス・クリストファーソンを口説き落としたのである。
彼らはザ・ハイウェイメンと名乗り(この名前はジミー・ウェッブの曲のタイトルから取った)、ウディ・ガスリーやハンク・ウィリアムズらの曲のカヴァーばかりを演奏して過去のヒーローたちに敬意を表した。
ザ・ハイウェイメンがしばしば「カントリー・ミュージック界のマウント・ラシュモア [訳注:サウス・ダコタ州西部にある山。ワシントン、ジェファーソン、リンカーン、ルーズヴェルトという歴代アメリカ大統領4人の巨大な像が中腹の岩肌に刻まれていることで有名]」と呼ばれることを受け、エミルー・ハリスは「彼らはあの大統領たちと一緒にあそこに刻まれても何の遜色もないし、実際そうすべき」と発言している。彼らの影響は絶大で、その環は今も連綿と受け継がれている。ザ・ハイウェイメンでスティール・ギタリストを務めたロビー・ターナーは、現在クリス・ステイプルトンと活動を共にしているのだ。
80~90年代のオルタナ・カントリー
ザ・ハイウェイメンが活発に活動していた同じ時期(1984年から1995年)、また新しい形のアメリカーナ・ミュージックが台頭の兆しを見せ始めた。ザ・バンドが既存のポピュラー・ミュージックのトレンドに反発し、自分たちのオリジナル曲とパフォーマンスのスタイルで対抗したように、80年代後半から90年代のいわゆるオルタナ・カントリー・ブームの牽引役となったミュージシャンたちも、カントリー・ミュージックの既存の体制に挑戦を仕掛ける者たちという自覚を持っていた。
ルシンダ・ウィリアムスの言を借りれば、「自分が呼ぶところの、ナッシュヴィルの真っ当なカントリー・ミュージック業界の一員だなんて意識、私にはこれっぽっちも持ってない」。
1986年から1990年にかけて、立て続けに珠玉の4連作(『Guitar Town』『Exit 0』 『Copperhead Road』そして『The Hard Way)』)を出したスティーヴ・アールは、ハンク・ウィリアムズに近い考え方の持ち主であり、ロドニー・クロムウェルやデル・マコウリーらの新星と共に、どちらも80年代末のいわゆる‘反乱分子的カントリー・ブーム’の中心人物だった。
拡大を続けるヨーロッパのオーディエンスが実質的にスティーヴ・アールを知ることになったのは、アルバム『Copperhead Road』からだろう。タイトル曲は密造酒造りが家業の男が商売替えをし、それより更に芳しいもの(麻薬)を育てることにするという物語が見事な独白調で展開され、スティーヴ・アールのソングライティングにウディ・ガスリーやレフティ・フリッツェル、ハンク・スノウといったオールド・スタイルの書き手たちと並べても見劣りしない力があることを示している。
スティーヴ・アール本人は、ルシンダ・ウィリアムスと共に「ザ・ニュー・アウトローズ」と称されてはいるものの、二人がやっていたことは社会に対する謀反などではなく、作り出している音楽も本質的な部分では別物であると主張している。
「 俺たちがあの当時やってたクスリとか、関わってたあれやこれやのトラブルとは何の関係もない。俺たちはただ単にアーティスティックな自由を追求してただけなんだ」
『Guitar Town』がリリースされた1986年は、k.d.ラング、ドワイト・ヨーカム、ライル・ラヴェットらがシーンに登場した年でもある。MCAから自らの名前をそのまま冠した素晴らしいデビュー・アルバムを出したライル・ラヴェットはこう語る。
「あの時期は、昔ながらのナッシュヴィル系アーティストとはかけ離れたような音楽をやっている連中でも随分レコード契約に漕ぎ着けてたね。大勢の人たちがレコードを出すチャンスを与えられていて、それはとてもクールなことだと思ったよ」
そのハーモニーと特徴的なロック・サウンドで、現在のアメリカーナ・ミュージックのひとつの原型を提供したミネソタ出身のバンド、ザ・ジェイホークスも、1986年にデビュー作をリリースし、たちまちヨーロッパにも熱狂的な支持層を確保した。
ライアン・アダムスはウィスキータウンと共にアメリカーナ・ミュージックを作り始めた時、‘グラム・パーソンズと同じくらいイカした’人々が他にもいることに気付いたと言い、中でも影響を受けた存在としてザ・ジェイホークスの名を挙げている。
ウィスキータウンは1994年にノース・カロライナで結成され、3枚のスタジオ・アルバムを出したが、ライアン・アダムスは2000年にソロとしてのキャリアを追求するため脱退し 、その後も様々な興味深い方向性の音楽活動を展開し続けている。
ルシンダ・ウィリアムスは80年代に数枚のアルバムを出したが、しばらく表舞台での活動が取り沙汰されなくなった時期を経て、1998年の名盤『Car Wheels On A Gravel Road』 で音楽界の注目を一気にさらい、このアルバムは彼女に初めてのゴールド・ディスクをもたらした。
アルバムに収められた眩暈がするようなエモーション溢れる歌物語の数々は、21世紀の今聴いてみても録音された当時の新鮮さのままで、サウンドは少しも色あせていない。その後も『Essence and Blessed』のような優れた作品を作り続けているルシンダ・ウィリアムズは、『Car Wheels On A Gravel Road』について後日こう語っている。
「同じようなサウンドのアルバムを繰り返し作るのは嫌だった。私はいつも、それまでの自分のアルバムでやったことのないヴォーカル・サウンドに挑戦したいと思ってる」
そのアルバムがリリースされたのと同じ年に、ジョニ・ミッチェルがインタヴューでこう述べていたのは恐らく偶然ではないだろう。
「以前の私は禁欲的で、まるで修道士みたいだった。今の私はハンバーガーやTVを発見したチベット人みたいなものね。ようやくアメリカーナに追いつきつつある」
アメリカーナの女性達
ハンク・ウィリアムズは現代のカントリー・ミュージックの楽曲にも非常に力強い歌詞を幾つも提供した実績を持つ、アメリカーナが誇る輝かしき女性シンガー・ソングライターの系譜の源流でもある。
キティ・ウェルズ、ジューン・カーター・キャッシュ、ドリー・パートン、ロレッタ・リン、パッツィー・クライン、ボニー・レイット、リンダ・ロンシュタット、エミルー・ハリスといった錚々たる面々の伝統を受け継ぐ形で、80年代から90年代のシーンにはリーバ・マッキンタイア、メアリー・チェイピン・カーペンター、ジュリー・ミラー、メアリー・ゴーサー、アビゲイル・ウォッシュバーン等、数多くの侮りがたい女性アメリカーナ・アーティストたちが台頭してきた。
とりわけ際立っていた個性派のひとりが歌を操る詩人ナンシー・グリフィスで、自ら曲を書くのと並行し、ロバート・アール・キーンやトム・ラッセルといった腕利きのアメリカーナのソングライターたちによる歌詞の解釈にも堂々たる才能を発揮していた。
90年代も引き続き女性タレント台頭の流れで、グレッチェン・ピータースやアイリス・ディメント、シェリル・クロウ、リタ・ホスキング、ダー・ウィリアムズ、リー・アン・ウォマック、ロリー・マッケンナ、アーニー・デフランコ、ギリアン・ウェルチといった革新的なパフォーマーたちが登場し、それぞれ素晴らしいアルバムを作り始めた。
この時期に出て来た中でも屈指の前途有望なソングライターと言えばパティ・グリフィンだ。ボストンのローカル・フォーク・シーンで活動していた彼女が業界のレーダーにかかるようになったのは、1996年にA&Mから出した出色のデビュー作『Living With Ghosts』がきっかけだった。
パティ・グリフィンはその後もパワフルかつソウルフルなアルバムを作り続け、ゴスペルへと進出した『Downtown Church』では2011年のグラミー賞を獲得した。サラ・ジャローズ、イーファ・オドノヴァン、ルース・ムーディ、アンジェリーナ・プレスリー、マディ・アンド・テイ、そしてレディ・Aのシンガーであるヒラリー・スコットといった心躍らされるような新しい才能も次々に生まれ、ますます伸び盛りだ。
しかし、ベテランたちも決しておっとりと後塵を拝しているわけではない。ドリー・パートンは20世紀が終わる頃にブルーグラスへと回帰して目の醒めるような作品を何枚も出しており、またロレッタ・リンの2004年のアルバム『Van Lear Rose』は実にセンセーショナルな作品だった。
このアルバムをプロデュースしたザ・ホワイト・ストライプスの首謀者でありソングライターであるジャック・ホワイトは、ロレッタ・リンのその前のアルバム『A Tribute To Patsy Cline』がリリースされた1977年には僅か2歳だったのだ。そんな2人のペアリングはいかにもミスマッチのように思えたが、この時72歳になっていたロレッタ・リンのカムバック作は高い評価を得、プロデューサーを務めたジャック・ホワイトはロレッタ・リンの音楽に新しいオーディエンスを引き込む手助けにもなった。
『Van Lear Rose』には現代のアメリカーナ・ミュージックにおけるまた別のファクターも反映されている、それはそのオリジナリティと特質性だ。この音楽には、ライル・ラヴェットの辛辣なウィットから、ドライヴ・バイ・トラッカーズのロック・バラード、ジェームス・マクマーティ、ダニー・シュミット、トッド・スナイダー、ジェイソン・イズベルらの社会に対する見解から、ビリー・ジョー・シェイヴァー、ダークス・ベントリー、クリス・ステイプルトン、スターギル・シンプソンやエイモス・リー、更にはまだマイナーだがロビーヘクトやリチャード・シンデルの心揺さぶるエモーショナルな歌まで、何もかもを包み込む懐の深さがある。
広がり続けるアメリカーナ
アメリカーナ・ミュージックの誕生を誘発し、実際に生み出した張本人が誰なのかを明確に指摘することは困難であり、それがまたこれだけ継承されてきた多岐にわたる要素の豊かさの証明にもなっている。
グレイトフル・デッドやロス・ロボスといった多様な音楽性を持つバンドの音楽にも、アメリカーナが脈々と受け継がれていると言うのは決して誇張ではない。ニール・ヤングは、ソロにせよクロスビー、スティルス&ナッシュとの活動にせよ、その音楽性においては必ずしもアメリカーナのバンドだと直截的には言い難いが、彼らがルーツ・ミュージックをベースにしたモダン・ロックの人気拡大に一役買ったことは紛れもない事実である。
加えて、アメリカーナの源流はリトル・フィートの「Willin’」で歌われた南部の砂漠から、 「Dixie Chicken」のミシシッピ・デルタ地帯まで、ジグザグ状に州をまたいでいる。ちなみにアメリカン・ミュージック・トレイル[訳注:アメリカの有名な音楽関連スポットを回るツアーを専門にしている旅行会社]は、そのルーツをひと通り網羅したコースを企画し、観光客をアラバマ州のマッスル・ショールズ・スタジオからナッシュヴィルのカントリー・ミュージック・バー、ニューオーリンズのジャズ・ジョイントまですべてを体験してもらうというツアーを実施している。
時に、カントリー系ではないがソウルフルなアーティストが、過去の名曲のカヴァーを通してアメリカーナ・ミュージックの本質を巧みに捉えることがある。ブルー・ノート・レコードから出したアルバム『Feels Like Home』にてノラ・ジョーンズはタウンズ・ヴァン・ザントの「Be Here To Love Me」をレコーディングし、彼を鼻高々にした。
またグラミー賞にも輝いた大スター、アリソン・クラウスは格別の目利きぶりを発揮し、モダン・アメリカーナのソングライティングの粋を選び抜いている。アリソン・クラウスがカヴァーした曲はウィリー・ネルソンからリチャード・トンプソン、ショーン・コルヴィン、シドニー・コックス、ミンディ・スミス、ジェームス・テイラー、ティム・オブライエン、ジャクソン・ブラウン、そしてトム・ウェイツと、実にヴァラエティに富んでいる。そして比類なき彼女の歌声は、既に数え切れないほどカヴァーされてきたウディ・ガスリーの曲にさえ、また違う味わいをもたらす力があるのだ。
アリソン・クラウスはT・ボーン・バーネットがプロデューサーを務めたコーエン兄弟の監督による大ヒット映画『オー・ブラザー!』のサントラ盤でも欠くことのできない役回りを務めた。このアルバムではアリソン・クラウスのバンド・メンバーであるダン・ティミンスキーが、モダン・クラシックと呼ぶにふさわしい「Man Of Constant Sorrow」のカヴァーを提供し、一方ブルーグラスの巨人ラルフ・スタンリーはいつまでも耳に残る「O Death」を歌い上げている。
ラルフ・スタンリーのナンバーはアメリカーナ・ミュージックの最もシンプルかつパワフルな表現の形を示しており、その声はまるで過去の世紀からまっすぐに響いてくるかのようだ。
同じくT・ボーン・バーネットのプロデュースによるギリアン・ウェルチの『Revival』も、アメリカーナの伝統に則った作品だ。このアルバムのレコーディングが行なわれたナッシュヴィルのウッドランド・スタジオは、ザ・ニッティ・グリッティ・ダート・バンドの傑作『Will The Circle Be Unbroken』をはじめとする70年代の名作が幾つも生まれた音楽ファンにはお馴染みの場所だった。
T・ボーン・バーネットはギリアン・ウェルチの声をレコーディングするのに、かつてハンク・ウィリアムズが使っていたのと同じようなウォレンサックの録音機材まで試してみたと言う。正真正銘筋金入りのアメリカーナ・アーティストであるギリアン・ウェルチは流石の面目躍如ぶりで、過ぎ去りし時代の音楽にも新鮮さを失わせず、今の時代にも通用するような形に仕上げるよう、力を尽くしている。
ところでT・ボーン・バーネットは、現代のデジタル・ミュージックがアメリカーナ・ミュージックの進化を助長したと考えている。何故ならそのおかげでファンはその曲のコンテンポラリー・ヴァージョンを聴いた後、オリジナル・ヴァージョンに興味を持って探しに行くことが多々あるからだ。彼はこう言う。
「最近のオーディエンスは、もの凄く選択肢が多いからこそ、想像以上に情報に精通しているんだよ……古代の音楽だって、いつでも作りかえたり、復活のチャンスはあるんだ」
若手ミュージシャン達
自分たちのヒーローの音楽を讃えると同時に刷新しようとしている若手ミュージシャンの最高峰と言えば、ケーシー・マスグレイヴスかも知れない。2013年、アルバム『Same Trailer Different Park』の成功でシーンを驚かせた彼女は、ビーチ・ボーイズ、リー・アン・ウォマックとジョン・プラインの接点を「理想的な音楽の形」と応えている。
テキサスを拠点に活動するミッドランドは、2017年9月にアルバム『On The Rocks』でデビューを飾り、この時代にコンテンポラリーな「1980年代のジョージ・ストレイト風ニュー・トラディショナリスト・サウンド」を持ち込んだことでBillboard誌上で絶賛された。
ミッドランドと才能豊かなザ・キャディラック・スリーは、厳密にはアメリカーナとは言えないかも知れないが、どちらもアメリカーナ的特性――フレッシュさと親和性――をカントリー・ミュージックに採り入れている。
ザ・キャディラック・スリーは別格の才能を誇るデイヴ・コブがプロデュースを手掛けているが、彼はこれまで他にもクリス・ステイプルトン、リンディ・オルテガ、コルター・ウォール、ブランディ・カーライル、ジェイソン・イズベルにアマンダ・シャイアーズらの作品で素晴らしい仕事をしてきた人物だ。
アメリカーナが今後ますます勢力を拡大していくことになるのは間違いないだろう。Spotifyのようなストリーミング・サービスの浸透が進めば、ラジオでは相変わらずトラシデョナルなカントリー・ミュージック系の局でしかかかっていなくても、このジャンルに対するアクセスのしやすさとメインストリームとしての露出の確保が期待できる。
更に付け加えるなら、ナッシュヴィルで毎年9月に行われるアメリカーナフェストに付随した様々なフェスティヴァルも数多く行なわれることになっている。新しいもののひとつはザ・ロング・ロードで、カントリー、アメリカーナ&ルーツ”と銘打ったこのフェスは、同じ9月に開催される予定だ。これらのフェスティヴァルは今後、新人タレントたちの進化の鍵となるだろう。
アメリカーナはレコーディング・アカデミーからも一目置かれるカテゴリーとなり、2010年には「最優秀アメリカーナ・アルバム賞」が設立。この部門の最初の受賞者はリヴォン・ヘルムで(2012年に2度目の受賞を果たしている)、ジェイソン・イズベルも2度その栄光に輝いた。
メイヴィス・ステイプルズ、ボニー・レイット、 エミルー・ハリス、ロドニー・クロムウェル、そしてロザンヌ・キャッシュも皆受賞経験者たちだ。全てを受け容れるアメリカーナの特質は、2016年にスタックス・レコードのレジェンドであるウィリアム・ベルが受賞者となったことにも表れている。アリソン・クラウスとパティ・グリフィン、両方とレコーディングを行なった経験を持つ元レッド・ツェッペリンのフロントマン、ロバート・プラントの言葉を借りれば「アメリカーナ行くところ、壁も限界もありはしない」のである。
アメリカーナの種々雑多な特性は、音楽が世界中に広がる間もずっと変わらず続いている。英国のオフィシャル・チャート・カンパニーが、アメリカーナに特化したアルバム・リストを発表した際、トップ10にはライアン・アダムス、ルシンダ・ウィリアムスと共に、スウェーデンの姉妹デュオ、ファースト・エイド・キットが入っていた。
今では英国にもオーストラリアにもアメリカーナ・ミュージック・アソシエーションが存在している。1999年、ラジオDJやレコード・レーベルの社員、音楽ジャーナリストたちがサウス・バイ・サウスウェスト・ミュージック・カンファレンスの会場で非公式に集まり、自分たちの愛する音楽をどうやってプロモーションすればいいかを話し合い、ひとつの組織を作ることを決めた当時からすると、実に隔世の感がある。
ザ・ニッティ・グリッティ・ダート・バンドのジミー・ファッデンは、『The Americana Revolution』という本の中でこう語っている。
「アメリカーナは言葉では説明できない様々な形式のルーツ・ミュージックを、オーディエンスに対して簡潔な姿で披露するためにひとまとめにして整理しようという試みだったんだ、それにはひとつの名前があるんだという理解の下にね」
今ではその名前にも明確な意義がある。アメリカーナ・ミュージックは進歩的で最先端で、ことアルバムについてはセールスを挙げている音楽ジャンルだ。Billboard誌によれば、2016年にはR&Bやヒップホップ、ダンスを上回っていた。そしてカルチャー方面の重鎮たちからも評価されている。PEN/フォークナー賞受賞歴のある小説家アン・パチェットは先頃ニューヨーク・タイムズ紙に、アメリカーナは「現在最もクールな音楽シーン」だと語っていた。
ハンク・ウィリアムズがかつて言った通り、「人々に新しいダンスを教えるために」新しいアメリカーナはこれからも続いて行くはずだが、これから先何があろうと、ミュージシャンたちが大切な拠り所とする宝物のような歴史は決して消えることはない。そのことを端的に示しているのが、既に半世紀以上良質なアメリカーナ・ミュージックを生み出し続けてきた達人、ライ・クーダーだ。
ライ・クーダーの最新アルバム『The Prodigal Son』 には、スタンリー・カーターの「Harbour Of Love」のカヴァーが収められているが、この曲のオリジナルは1950年代にマーキュリー・レコードから発売されたものである。「この当時の曲を弾いたり歌ったりすると、何だか敬虔な気持ちになってくるんだよ」と彼は言う。
その敬虔な気持ちと熱意こそが、アメリカーナ・ルーツ・ミュージックがこれからも繁栄し続ける理由なのだろう。
Written By Martin Chilton
- アメリカーナ:アメリカの田舎道の音楽
- 史上最高のオルタナ・カントリー・アーティスト10人
- 史上最高のアメリカーナ・アルバム10選
- グレイト・アメリカン・ソングブック:カントリーのトップ11
- カントリー・ミュージック 関連記事

2023年3月3日発売
CD / iTunes Store / Apple Music / Spotify / Amazon Music / YouTube Music










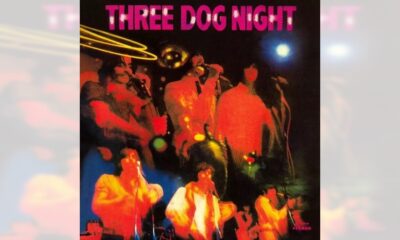
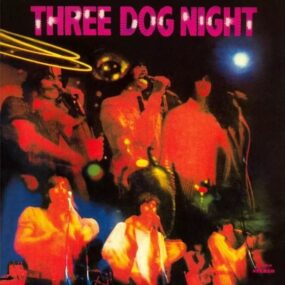
-400x240.jpg)
-285x285.jpg)







