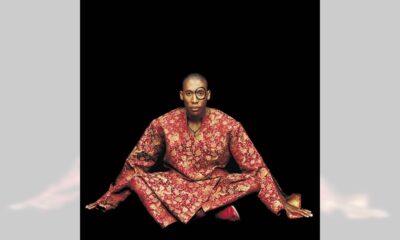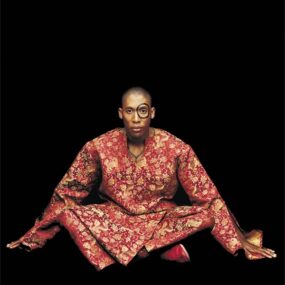Columns
黒人音楽ヒストリーを彩った奇妙な事件ベスト5


ヒップホップやR&Bなどを専門に扱う雑誌『ブラック・ミュージック・リヴュー』改めウェブサイト『bmr』を経て、現在は音楽・映画・ドラマ評論/編集/トークイベント(最新情報はこちら)など幅広く活躍されている丸屋九兵衛さんの連載コラム「丸屋九兵衛は常に借りを返す」の第44回。
今回は、先日実施されたオンラインイベント【ブラック・ミュージック・エピソディック:米黒人音楽ヒストリーの劇的瞬間】を抜粋して文章化したものをお届けします。
<関連記事>
・“嘘つき”ラッパーたち:イメージと実像の耐えがたき落差
・ラッパー達の盛られたイメージ戦略
・ヒップホップと資本主義:なぜ、そこまで金銭にこだわるのか
①ジェイムズ・ブラウン、影武者になる
売春宿で育ち、車泥棒の罪で刑務所に入り、シャバの皆さんとの野球交流戦でボビー・バード(のちの相方)と知り合い、バード家の尽力で釈放され、ドラマーとして参加したはずのグループでいつの間にかリード・シンガーの座を乗っ取り……JBことジェイムズ・ブラウンの人生は、その音楽同様に劇的だ。
そんなJBは、同時代を生きたロックンロールの旗手リトル・リチャードと下積み時代に運命的な出会いを果たしている。それがゆえだろうか……時おりJBはリトル・リチャードとしてステージをこなしていたのだ! いわば影武者!
二人とも声が大きく、シャウト唱法に長け、ピアノを弾き、少なくとも一時期は両者とも髪型がポンパドゥールだった。そこまでは事実だが、冷静に見れば顔はずいぶん違う。
しかし、50年代の人々はアーティストの顔をどうやって知ったのか? 新聞だとすると、当時の新聞に掲載される写真の画質・精度が心許なかったことを思い出そう。ではレコード・ジャケットは? ロックンロールもソウル・ミュージックも(一時期までは)、アルバムではなくシングル主体の音楽だった。で、シングルというものは往々にしてジャケットがついていないのだ。
とはいえ、「この時点で有名人だったリトル・リチャードはTV出演も多々では?」とも思うが、そのTVとて画質は非常に粗い。こんな技術的限界があってこそ成立した「影武者・オン・ステージ」だったといえよう。
ピクセル数膨大、4Kを超えて8Kへと突き進む現代では考えられないような珍妙な事件が、それもソウル・ブラザー・ナンバー1とキング・オブ・ロックンロールの間で起こっていた……と知ると、この数十年の音楽業界とテクノロジーの変容ぶりを思い知らされるではないか。今そんな影武者が登場したら、SNSで拡散&糾弾されること間違いなし!である。
(編註:以下はその二人が共演したクイズ番組)
②ジェイムズ・ブラウン、ブーツィと出会う
音楽史を振り返るような本で「憶測一切なし」「関係者の証言だけで構成」と喧伝している例があるが、わたしに言わせれば関係者の証言ほど当てにならないものはない。いや、そもそも証言というのは全て当てにならないのだ。
「同じ現場にいた人々なのに、言うことが食い違う」という現象は多々あり、それは映画『羅生門』から取った「Rashomon Effect」として世界的に知られている。
ここで検証したいのは「JBとブーツィ・コリンズの出会い」問題。ブーツィによれば、それは1968年4月だったという。地元オハイオ州シンシナティのスタジオにたむろしていたブーツィ少年17歳にJBが声をかけ、その時に録音したものが5月に「Licking Stick – Licking Stick」としてリリースされてブーツィはビックリ!……らしいのだが、音楽史家クリフ・ホワイト認定の同曲演奏陣に彼の名はない。
正史扱いなのはジョージア州コロンバスでの公演である。
「ある日、ボビー・バードから電話があり、“ジェイムズとギグする準備はできてるか?!”と言われてびっくりした。18時にシンシナティの空港で飛行機に乗り、20時からジョージア州で公演。時間がないから直接ステージに上がった」
とはブーツィの弁。とはいえ、面識もない若造にボビー・バードが電話するのは異常なので、それ以前に少なくとも何らかの接触があったのだろう。シンシナティのスタジオで。
この「突然電話事件」の背景にあるのは、JBの暴君ぶりに耐えかねた当時のバックバンドの面々が起こした反乱である。「待遇を改善しろ、さもなくば今夜は演奏しない」、そんなストライキ宣言を出したバンド(メイシオ・パーカーら)に対してJBが取った手段がバンドの総入れ替えだった。こうしてブーツィたちオハイオの若者たちが招かれ、JBファンクを刷新していくのだ。
しかしブーツィはクリフ・ホワイトにジョージア州コロンバス公演に関して「あの時、俺は何が起こっているのかわからなかった」と語ったくせに、別のインタビューでは「バンドメンバーがJBと取っ組み合いしているのが見えて、何か問題があることを悟った」とも“証言”していて、一人なのにラショモン・エフェクトなのだった……。
③エリック・バードンの喘息とWARの旅立ち
喘息はつらい。そして、それがステージで歌唱中に発作となると、目も当てられないディザスターとなることは必至。かくいうわたしもゼンソク持ちなのでよくわかる。
それを体験したのは、ウォーを率いていたエリック・バードン。このステージ上の事件——1970年暮れもしくは翌1971年初頭——がきっかけとなり、エリック・バードンはウォーを離脱する。残されたウォーの面々は、リード・シンガーなしにツアーをやり終えた。
その後は、レコーディング・アーティストとしてもエリック・バードン抜きのウォーとして独立し、「Slippin’ into Darkness」「The Cisco Kid」「Me and Baby Brother」「Low Rider」といった名曲を連発するに至るわけだ。
わたしは時おり、「このゼンソク発作事件が起こらなかったら……」とwhat ifに思いを馳せることがある。つまり、「ウォーがあくまでエリック・バードンのバンドとしての活動を続けていたら」ということだ。
その場合、先に挙げたような名曲群は生まれたろうか?
果たして彼らは、ファンク史に名を残す存在となっていただろうか?
そして、これほどまでメキシカン・アメリカンたちに偏愛されただろうか?
④マーヴィン・ゲイと他人のフンドシ
もちろん、『What’s Going On』は偉大なアルバムである。世界の現状を憂いたメッセージを、ミルフィーユのように重ねた美しいコーラスで聴かせてくれるマーヴィンの神技よ。
だが、そんな『What’s Going On』が、実は決してマーヴィン自身のbrainchild(構想)ではなく他のミュージシャンたちによる発案、要は「持ち込み企画」だったことは忘れないようにしたい。なぜなら、少なくとも70年代の——即ち、最も絶頂期の——マーヴィンは「絶頂期なのにスランプがデフォルトの人」だったからだ。
『What’s Going On』の大元、それはフォー・トップスのオービー・ベンソンがツアー先の各地でアメリカの惨状を目撃し、デトロイトに戻ってからモータウンのソングライター、アル・クリーヴランドに話したこと。そのクリーヴランドが作ったのがタイトル曲「What’s Going On」であり、例によって悩んでいたマーヴィンが、同曲から組曲的に派生させたのがアルバム『What’s Going On』なのだ。
そして、70年代にマーヴィンが出した他の正編(いわば「普通のスタジオ・アルバム」)である『Let’s Get It On』も『I Want You』も、それぞれ他のミュージシャンからのインプットが大きい。詳細は書かないことにするが。
ここで70〜80年代のマーヴィンのディスコグラフィを見ると……
1971年:What’s Going On ◉
1972年:Trouble Man *サウンドトラック
1973年:Let’s Get It On ◉
1973年:Diana & Marvin *デュエット作
1974年:Marvin Gaye Live! *ライヴ盤
1976年:I Want You ◉
1977年:Live at the London Palladium *またライヴ盤
1978年:Here, My Dear *離婚対策大作
1981年:In Our Lifetime *モータウンと衝突
1982年:Midnight Love ◉
正編は2〜6年に1枚、その間に企画ものがたくさん詰まっているあたり、『Tha Carter』シリーズを中心とするリル・ウェインの活動に似ているぞ。
⑤プロデューサーは蚊帳の外:ダイアナ・ロスのケース
ディスコという言葉をどう捉えるのも自由だが、少なくともアメリカ音楽史におけるジャンルとしてのディスコ・ミュージックは1979年に死んだ(だから、その後の同種の音楽はポスト・ディスコである)。
それまでも、流行ったがゆえにさんざん叩かれてきたが、同年7月12日にイリノイ州シカゴの球場にて、MLBダブルヘッダーの試合間に行われたDisco Demolition Night——ディスコ・レコードを持ち寄って爆破するイベント——がディスコ・ブームに引導を渡したと言っていいだろう。
困ったのは、ディスコの巨匠たるChicの二人、ナイル・ロジャーズ&バーナード・エドワーズのプロデュースのもと、ディスコなニュー・アルバムを作っていたダイアナ・ロスである。仕上がった音源をニューヨークの著名DJに聴かせたところ、
「この反ディスコ風潮の中でこれ?! 君のキャリアの終焉となるかもしれんぞ」
とまで言われてしまう。ここに及んで、ダイアナは決断した。「すべてリミックスしてしまおう」と。それも、ナイル・ロジャーズ&バーナード・エドワーズには告げずに。
ディスコ・ミュージックのディスコたる所以は「ダンスを続けるのに適した長い長い前奏と間奏」等にあり、ヴォーカル・パートを相対的に軽く扱う傾向がある。だからダイアナは前奏・間奏を適宜カットした。そして、冗長に聞こえぬようBPMをアップ。さらに、リードヴォーカルを歌い直し&差し替え! これまた、ディスコらしい楽器群に埋もれぬよう、元々のサウンドスケープに比べて前面かつ中心に位置する仕立てとした。いわば、ディスコ音源を「アン・ディスコ」したわけだ、彼女自身の流儀で。
このようにダイアナが改変したマスターを「こうなりました〜」と聴かされたナイル・ロジャーズ&バーナード・エドワーズは猛反発したが、ダイアナは押し切った。そんな紆余曲折を経て1980年3月にリリースされたのが『Diana』。同作は、彼女のキャリアで最大のヒット作となり、記録にも記憶にも残るアルバムとなったのだ。
(編註:上がダイアナ・ロスによる“アン・ディスコ”版。下がChicによるオリジナル版)
さて、ここから続く1980年代も事件は多々あったのだが……続きはオンラインイベント【ブラック・ミュージック・エピソディック:米黒人音楽ヒストリーの劇的瞬間】の本編をご覧ください。
Written By 丸屋九兵衛
【万物評論家の秋:文化祭は補習天国!】
丸屋九兵衛オンラインイベント
(ディレイ視聴&リピート視聴可能:購入期間は2023年11月30日23時55分まで)
9/29(金)①限:文化人類学
⚫︎イモ・病原菌・チョコ:欧州とアメリカが出会って何が変わったか。「コロンブスの交換」大研究
10/7(土)②限:音楽史
⚫︎ブラック・ミュージック・エピソディック:米黒人音楽ヒストリーの劇的瞬間
10/15(日)③限:地政学
⚫︎ミクロネーション大行進! 西川きよし卿からスロウジャム国家まで
10/21(土)④限:文化史
⚫︎オスカー・ワイルドと19世紀の偉人・奇人・変人たち
10/29(日)⑤限:世界史
⚫︎トルコ建国100周年の今こそ、BACK TO オスマン帝国! あの寛容と多様性をもう一度
11/3(金)⑥限:映画史
⚫︎大ヒット映画の続編失敗! 可笑しくて、やがて愛しきハリウッド
プレイリスト: Best Hip Hop Hits | HIP HOP 50 | ヒップホップ生誕50周年
Apple Music / Spotify / YouTube
- 【特集】ヒップホップ・ゴールデン・エイジ
- 「Black Lives Matter 2020」:繰り返される人種問題と抗議運動
- 米国上院にて8月11日を「ヒップホップ記念日」にすることが制定
- 30年前のヒップホップ名作・生誕ラッシュ
- ヒップホップと政治問題の歴史:グランドマスターからケンドリックまで
- カニエ・ウェストと政治、トランプ、右翼、保守との関わり