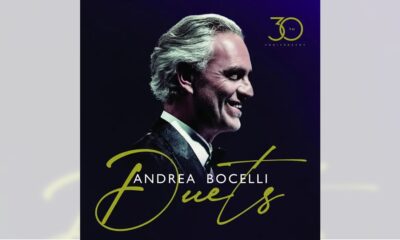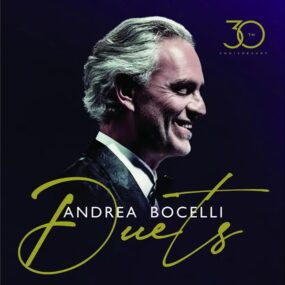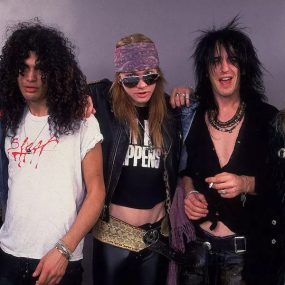Classical Features
アイスランド発、注目のコンポーザー・ピアニスト、ガブリエル・オラフス 最新インタビュー(後編)


詩や文学だけでなく、映画(映画音楽)やゲームからの要素もクラシックの伝統とともに自らの音楽に昇華させているガブリエル・オラフスが、新作『Polar』の核心を語るサウンド&ヴィジュアル・ライター、前島秀国さんによるインタビュー後編。
――いくつかのインタビューを拝見しましたが、もともと映画音楽がお好きだそうですね。
ガブリエル・オラフス:ハワード・ショア、坂本龍一、エンニオ・モリコーネ、久石譲、ジョン・ウィリアムズといった偉大な作曲家の音楽が僕のお気に入りですが、特に好きなのはヨハン・ヨハンソンで、彼の作品をよく研究しています。
映画音楽と文学は僕にとって非常に重要ですが、これまで出したアルバムのほぼすべてが、アイスランドの詩や文学に基づくコンセプトアルバムとして作られています。
――アイスランド文学といえば、日本のリスナーの中には『エッダ』を読んだことがある人も少なからずいると思います。
ガブリエル:『エッダ』はアイスランド人にとって最も重要な文学なので、日本でも知られているのは素晴らしいことです。ワーグナーの《ニーベルングの指環》だけでなく、ゲームにもインスピレーションを与えていますね。
――あなたは熱心なゲームプレイヤーだと伺いました。
ガブリエル:はい。僕は26歳でゲーム世代ですが、クラシックの音楽家でゲームをする人はあまりいないと思います。たぶんそれが、僕がヴィキングル・オラフソンになれなかった理由かもしれません(笑)。
彼はゲームをせずにピアノの練習に打ち込んでいますが、僕はピアノの練習の代わりにゲームに打ち込んでいます。ゲームは消費主義的なイメージが強いですよね。でも、僕はゲームも高度な芸術になり得ると信じています。
クラシックは伝統的で歴史があり、ゲームはとても新しい。その正反対の要素を僕は融合させたいんです。
――あなたがゲームの感覚にインスパイアされて作ったという、最新アルバムの『Polar』と『Traveller’s Log』(注:ナレーションつきヴァージョン。楽曲構成が若干異なる)の両方を聴かせていただきました。これは、一種のSFなんですね?
ガブリエル:普通はSF映画から映画音楽が生まれますが、逆にSF映画にインスパイアされてクラシックを作曲する人はほとんどいないので、少なくとも斬新なコンセプトではないかと自負しています。
最初に、ある架空の惑星の世界観のアイディアがあり、それを「Polar」(極地)と名付けました。それからSF作家を雇い、僕のアイディアを膨らませながら少し長めのストーリーを書いてもらったんです。
――レベッカ・ローンホース(Rebecca Roanhorse)という作家ですね。
ガブリエル:はい。彼女はネイティブアメリカンの作家で、『スター・ウォーズ』シリーズのスピンオフ小説『スター・ウォーズ レジスタンスの復活』なども書いていますが、SF作家としてはニューヨーク・タイムズのベストセラー・リストにも入っています。
彼女の小説『Black Sun』を読み、SF的な環境描写がとても素晴らしいので、彼女なら任せられると確信しました。
そこで何度か会ってミーティングし、僕が希望している要素を伝えたうえで、彼女にテキストを書き下ろしてもらいました。
それが「Traveller’s Log」(旅人の日誌)というテキストで、旅人がたどりついた惑星の様子がとてもドラマチックに描写されています。
――その後、音楽を作曲したのですか?
ガブリエル:いえ、そうじゃないんです。僕の音楽も、レベッカのテキストも、それからアルバムのアートワークも、すべて同時進行で作られていきました。
全員がミーティングに集まり、例えばレベッカが「音楽の長さはこのくらい」とアイディアを出し、僕がアートワークの担当者に「ヴィジュアルはこういう風に」とアイディアを出していくような感じです。まるで、全員で映画を1本作っていくような感じでした。
レーベル担当者は「普通は音楽が先にあるのに、こんなやり方は今まで誰もやったことがない」と驚いていました。
――《The Waves》という楽章では独奏チェロのセクションがあったり、《Whale Variation》という楽章では独奏ピアノのセクションがあったりする一方で、全体としては交響曲のようなオーケストラ作品として構成されているのが非常にユニークだと思いました。時おり聴こえてくるクジラの声は、いわば潜在的な歌手じゃないかと感じましたし、パイプオルガンの凄まじいエネルギーにも驚きました。ものすごい重低音ですね。
ガブリエル:録音に使ったのは、レイキャヴィークのハットルグリムス教会(Hallgrímskirkja)に設置されているアイスランド最大にして最高のオルガンで、非常に低い音域まで出せます。
サウンドスケープの描写や雰囲気を表現するために低音域を多用しましたが、小さな鈴のような音、奇妙なホイッスルのような音、鳥のさえずり、チューブラーベルズのような音もオルガンで演奏していますし、ベース音にはすべてオルガンを使っています。
――全部、自分で演奏なさったのですか?
ガブリエル:MIDIも使用しています。例えば《The True Meaning Of Forever》という曲では、MIDIによってオルガンのオスティナートが永遠に鳴り続けます。
曲名に「Forever」(永遠)とありますからね。そこに、コードを重ねて演奏しました。オルガンの音は、空気でパイプを鳴らすのでとても自然に感じられますが、同時にクジラも彷彿とさせますよね。パイプの中を通る空気は、まるでクジラの噴気孔から出る潮吹きみたいです。
――僕が感銘を受けたのは、この『Polar』の物語がSFであると同時に、人間の生と死のメタファーのように感じられた点です。
ガブリエル:『Polar』に出てくる惑星が架空の惑星なのか、それとも地球なのか、誰にも分かりません。もしかしたら、我々が滅んだ後の地球かもしれない。
雪の中から現れるモノリスやピラミッドは、失われた文明の残骸ですね。かつて、人間が生存していた証なのかもしれません。その意味では、生と死のメタファーでもあると思います。そして曲の最後で、ある種の別れを告げています。避けがたい終末への告別です。
でも、僕は曲を美しく終わらせたかった。自分自身の葬儀かもしれませんが、最後には輝かしい美と、別れが訪れます。
――ナレーションつきの『Traveller’s Log』では、女性がテキストを朗読していますが、旅人は女性という設定なのですか?
ガブリエル:いえ。ナレーションは、旅人に寄り添うAIの声という設定です。リスナー自身が旅人なので、性別は特定したくないんです。
英語のナレーションの録音は、僕の友人でSFドラマ『See 〜暗闇の世界〜』にも出演しているアイスランド人女優ヘラ・ヒルマーにお願いしました。
――旅人ということでいえば、今回が初来日なんですね?
ガブリエル:関西万博のアイスランド・ナショナルデー(5月29日)では、アイスランド大統領臨席の下、アウスゲイルやJFDRと共にステージに立ちました。その後はラーメンを食べたり、居酒屋に行ったり(笑)。
アニメはあまり観ていないのですが、ジブリ作品は大好きです。最近観た日本映画は『ドライブ・マイ・カー』。同じ村上春樹の『ノルウェイの森』もちょうど読み終えたところです。日本文化は初心者ですが、もっと探求したいです。もちろん、日本のゲームも大好きですよ。
次に来日する機会があれば、ぜひオーケストラで演奏したいです。それと、日本とアイスランドは温泉に恵まれた国という共通点があるので、温泉に浸かりながら『エッダ』について語り合いたいですね(笑)。
Interviewed & Written By 前島秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)
■リリース情報
 ガブリエル・オラフス,坂本美雨 / Polar: Traveler’s Log (Japanese Version)
ガブリエル・オラフス,坂本美雨 / Polar: Traveler’s Log (Japanese Version)
2025年10月10日 発売
Apple Music / Spotify / Amazon Music / iTune

ガブリエル・オラフス / Polar
2025年3月1日 発売
Apple Music / Spotify / Amazon Music / iTunes
- ガブリエル・オラフス オフィシャルホームページ
- ルドヴィコ・エイナウディが語る、夏の思い出を詰め込んだ最新作『サマー・ポートレイト』
- Classical News第67回グラミー賞︎®️、ヴィキングル・オラフソンなどドイツ・グラモフォンから3作品受賞
- ショパン・コンクール優勝者ブルース・リウのコンクールでのハイライト録音をドイツ・グラモフォンが緊急リリース
- ショパンの聴くべき作品ベスト10:ロマン派“ピアノの詩人”がつむいだ名曲選
- ショパン国際ピアノコンクール本大会まもなく開幕。優勝から6年、チョ・ソンジンが当時の記憶を語る
- クラシック・ピアノ独奏曲トップ10:バッハ、ベートーヴェン、ショパンなど最高のピアノ独奏曲10選
- ピアノ協奏曲ベスト15:ベートーヴェン、ショパン、モーツァルトなどの偉大なる傑作選