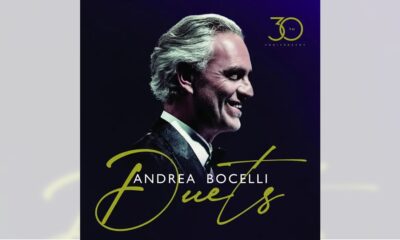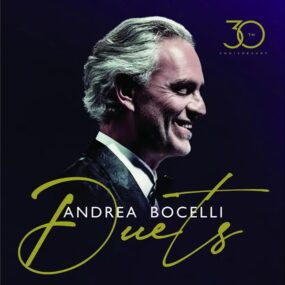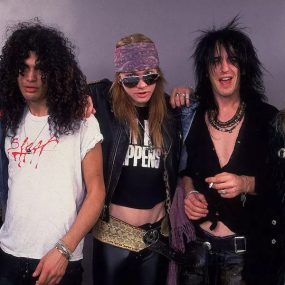Classical Features
アイスランド発、注目のコンポーザー・ピアニスト、ガブリエル・オラフス 最新インタビュー(前編)


ストリーミング再生回数2億5千万回を超えるアイスランド出身のコンポーザー・ピアニスト、ガブリエル・オラフスは、ポスト・クラシカル界において、ヨハン・ヨハンソンの後継者として高い注目を浴びている。
大阪・関西万博の「アイスランド・ナショナルデー」でのパフォーマンスのために来日した彼に話を聞いた。サウンド&ヴィジュアル・ライター、前島秀国さんによるインタビュー(前編)。
――5歳からピアノを始め、ジャズとクラシックを学ばれたそうですが、どうして作曲家になろうと思ったのですか?
ガブリエル・オラフス:ピアノを弾くよりメロディーを作るほうが得意だと気づいたからです。僕が習ったピアノの先生は、ヴィキングル・オラフソンのお母さん、つまりアイスランドでいちばん優れたピアノ教師なのですが、どんなに練習しても彼女を満足させることができず、上達できないと気づきました。
でも、昔から音楽を聴くのが得意で、耳コピで演奏していました。地元のポップスターと仕事をしたり、ジャズに関わったりしていくうちに、メロディーを作って演奏するほうが得意だとわかったんです。
――そのヴィキングル・オラフソン、それから同じアイスランド人のオーラヴル・アルナルズとヨハン・ヨハンソンにも取材したことがありますが、3人ともこう言っていました「レイキャヴィーク(アイスランドの首都)の音楽コミュニティは比較的小さく、とても親密なので、ポップスやクラシックを分け隔てなく演奏できる」と。
ガブリエル:その通りです。そこがアイスランドの強みだと思います。ジャンルにこだわらず互いに助け合うからこそ、何か新しいものを生み出すことができます。ビョークやシガー・ロス、あるいはオーラヴル・アルナルズやヨハン・ヨハンソンについても言えることですが、彼らの音楽はジャンルが多岐にわたっていますよね。
僕の場合も、グラミー賞アーティストである友人のラウフェイとコラボしたり、ジャズトリオで演奏するための曲を作ったり、あるいは自分の曲を作ったり、あちこち出かけて活動しています。
――だから、アイスランドでポスト・クラシカルというジャンルが盛んなのですね。
ガブリエル:アイスランド人がポスト・クラシカルに強いのは、質の高い音楽教育によってクラシック音楽の伝統を熟知しつつ、DIY(自分でやる)というパンクな精神も持ち合わせているからです。とにかく自分たちでやって、小さなコミュニティで活動していくしかないんです。それと、アイスランドは静かで自然が豊かな国なので、ポスト・クラシカルのような静かな音楽も自然と多くなります。
――デッカ・レーベルと契約したきっかけは?
ガブリエル:最初はビョークのレーベル、当時はOne Little Indianと呼ばれていたOne Little Independent Recordsに所属していて、10代の頃に書いた曲を集めたファーストアルバム『Absent Minded』を2019年にリリースしました。それをデッカ・レーベルのA&Rが気に入り、一種のスカウトのような形で契約したんです。
もともとOne Little Indianのために準備していたアルバム『ソロン・イースランドゥス 』を、デッカが2022年にリリースしてくれました。これはアイスランドの詩人ダーヴィズ・ステーファウンソン(Davíð Stefánsson)にインスパイアされた作品です。ダーヴィズは素晴らしい詩集を残した詩人ですが、『ソロン・イースランドゥス』を作ろうとしていた年のちょうど100年前、彼が僕と同じ年齢だったと知りました。そこからアイディアが生まれ、100年後の僕が、彼が詩を書いたように音楽が作れるのではないかと思ったんです。
――『ソロン・イースランドゥス』は、彼が書いた小説のタイトルだそうですね。
ガブリエル:そうです。アイスランドの芸術家セルヴィ・ヘルガソン(Sölvi Helgason)について書かれた小説です。アイスランドで芸術家になることがほとんど不可能だった19世紀、セルヴィは芸術家として活躍しました。ほとんどのアイスランド人は生活のために農民か漁師になりましたが、セルヴィは芸術家の道を選んだので、いわゆるホームレスのような存在、放浪者(ドリフター)になったんです。
アルバムの中にも、まさに《The Drifter》(放浪者)という曲が入っています。セルヴィは放浪しながら、小文を書き、絵を描いた。僕自身もそうでありたいと願い、《The Drifter》という曲名を付けたんです。
――2023年にリリースされた次のアルバム『Lullabies for Piano and Cello』は、ヴァイキングの民謡にインスピレーションを得て作られたそうですね。
ガブリエル:はい。ビャルニ・ソルスティンソン(Bjarni Þorsteinsson)というアイスランド人司祭のフィールドワークのおかげです。彼はデンマークで作曲を学んだ後、アイスランドに戻り、あらゆる教会や町を訪ねて、民謡を収集しました。その成果を『Íslenzk þjóðlög』(アイスランド民謡集)として出版したのですが、古書店で買って読んでみると、そのほとんどは本質的に子守唄なんだと思いました。
その中から5曲を選んでアレンジすると同時に、民謡と同じスタイル、つまりシンプルでキャッチーでミニマルな子守唄を自分でも5曲作曲してみました。作曲家としてはとてもチャレンジングな試みでしたね。
――なぜピアノとチェロという組み合わせを選んだのですか?
ガブリエル:僕はピアノが最高の楽器で、チェロがそれに次ぐ楽器だと思っています。チェロは、まるで人間の声が子守唄を歌っているように感じます。録音ではヴォーカルは使わないと決めていたので、人間の声と同じような質感を持つチェロを選びました。もうひとつ、チェロを弾いてくれた友人のチェロ奏者スタイニー・シグルザルドッティル(Steiney Sigurðardóttir)からもインスピレーションを得ました。ちょうど彼女が妊娠していた時期に、ふたりでライヴ録音したんです。
――その後、オーケストラでセルフカバーした『Orchestral Works』を2024年にリリースされましたが、いわば、それまでのベストアルバムという感じですね。
ガブリエル:10代の頃の自分の音楽に別れを告げたかったんです。そこで友人のヴィクトル・オッリ・アウルナソン と相談し、これまでの曲を室内オーケストラ用に編曲しようと決めました。レーベルには「次はオーケストラでフルアルバムを作りたい」と希望を伝え、レイキャヴィークのハルパでライヴ収録しました。演奏しているレイキャヴィーク・オーケストラは、僕も創設に加わった新しいオーケストラで、創立2年の若い団体です。
――録音専門のスタジオ・オーケストラですか?
ガブリエル:ええ。レイキャヴィークで唯一のスタジオ・オーケストラです。共同設立者のベルガー・ソリソン(Bergur Þórisson)は、ビョークの音楽監督も務めている優秀なサウンドエンジニアで、他にもヨハン・ヨハンソンやシガー・ロスと仕事をしている優秀なスタッフがそろっています。「アイスランドらしい、DIYっぽい感じにしよう」というアイディアから生まれた手作りのオーケストラなんですよ。
――そのレイキャヴィーク・オーケストラや、チェロのスタイニー・シグルザルドッティルも参加して作られた最新アルバムが『Polar』ですね。
ガブリエル:はい。これまではアイスランド文学にインスパイアされたアルバムを作ってきましたが、英語で物語を考え、英語でアルバムを制作したのはこれが初めてです。(後編に続く)
Interviewed & Written By 前島秀国(サウンド&ヴィジュアル・ライター)
■リリース情報
 ガブリエル・オラフス,坂本美雨 / Polar: Traveler’s Log (Japanese Version)
ガブリエル・オラフス,坂本美雨 / Polar: Traveler’s Log (Japanese Version)
2025年10月10日 発売
Apple Music / Spotify / Amazon Music / iTune

ガブリエル・オラフス / Polar
2025年3月1日 発売
Apple Music / Spotify / Amazon Music / iTunes
- ガブリエル・オラフス オフィシャルホームページ
- ガブリエル・オラフスの音響・視覚プロジェクトに坂本美雨が参加。日本語ナレーションを担当
- アイスランド発、注目のコンポーザー・ピアニスト、ガブリエル・オラフス 最新インタビュー(後編)
- ルドヴィコ・エイナウディが語る、夏の思い出を詰め込んだ最新作『サマー・ポートレイト』
- 2021年ショパン国際ピアノ・コンクール優勝、ブルース・リウとは?最新インタビュー公開
- ショパン・コンクール優勝者ブルース・リウのコンクールでのハイライト録音をドイツ・グラモフォンが緊急リリース
- ショパンの聴くべき作品ベスト10:ロマン派“ピアノの詩人”がつむいだ名曲選
- ショパン国際ピアノコンクール本大会まもなく開幕。優勝から6年、チョ・ソンジンが当時の記憶を語る
- クラシック・ピアノ独奏曲トップ10:バッハ、ベートーヴェン、ショパンなど最高のピアノ独奏曲10選
- ピアノ協奏曲ベスト15:ベートーヴェン、ショパン、モーツァルトなどの偉大なる傑作選