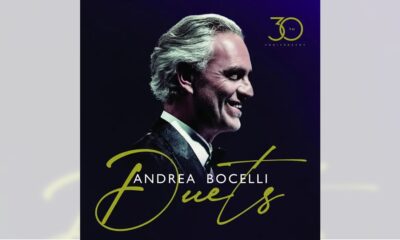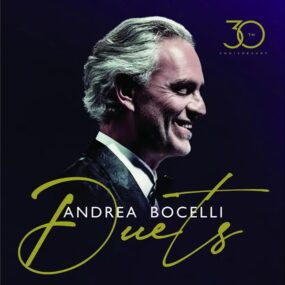Classical Features
ベートーヴェンはロックスターである。その理由を楽曲と生涯から辿る by 水野蒼生【連載最終回】


2020年はクラシックの大作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンの生誕250周年の年。そんな彼は現代でいうとロックスターだった?
巨匠カラヤンを輩出したザルツブルクの音楽大学の指揮科を首席で卒業し、その後国内外で指揮者として活躍。一方で、2018年にクラシックの楽曲を使うクラシカルDJとして名門レーベル、ドイツ・グラモフォンからクラシック音楽界史上初のクラシック・ミックスアルバム『MILLENNIALS-We Will Classic You-』をリリース。今年3月にはベートーヴェン・トリビュートのアルバム『BEETHOVEN -Must It Be? It Still Must Be-』を発売するなど、指揮者とクラシックのDJという両輪で活躍している水野蒼生さんによる寄稿、今回が最終回です。(第1回、第2回、第3回、第4回)
受難の始まり
1816年、まだ9歳の少年だったカール・ヴァン・ベートーヴェンは苦悩していた。父の病死と向き合って悲しむ暇もないまま裁判が始まり、この少年の親権は伯父であるルートヴィヒに半ば強奪され、母親と会うことは禁じられた。最愛の母親は健在なのになぜ共に暮らすという当たり前のことが出来ず、この不潔で強情な耳の聞こえない伯父との地獄の日々を送っているのだろう?そんなカールの嘆きなど一切考えていないベートーヴェンは、この9歳の甥を硬くキツく抱擁した。
それでもベートーヴェンはこの父を亡くした甥っ子のためを思って(それが独善的な押し付けになっているとは1ミリも疑わずに)出来うる限りの準備をしてくれていた。まず自分に万が一のことがあってもカールが困らないようにと高額の銀行券を買いあさり、また彼を自分と同じように優れた思想を持った有能な男にするために名門の寄宿学校に預け、その上で多数の外国語、デッサン、そしてピアノの家庭教師をつけた。超教育熱心なパパになろうとしていたのだ、ベートーヴェンは。
甥っ子のために奔走するベートーヴェンは「強引に親子を離別させたひどいやつ」という風に世間からは見え、このタイミングで古くからの友人たちもベートーヴェンから距離を置くようになってしまう。その上今までベートーヴェンを支援してきたパトロンたちがこぞって急死し、信頼していた音楽仲間の多くもさまざまな事情でウィーンから姿を消してしまった。
これに対するベートーヴェンの精神的ショックは少なくなかった。甥に対する世話や雑務も重なったことでベートーヴェンの体調は一気に悪化してしまう。こうした理由からこの時期に残された作品はあまり多くない。しかしそんな停時期にベートーヴェンは後の時代に大きな影響を及ぼす大きな発明をする。
「アルバム」の起源?
とある日、病に伏せっていたベートーヴェンのもとにひとつの詩が届いた。それは孤独になっていたベートーヴェンの胸を大きく打ち鳴らせた。
――そうだ、こんな詩に出会いたかったんだ、俺は――
そうしてベートーヴェンはこの詩をもとに歌曲《遥かなる恋人に》を一気に書き上げる。この作品は「連作歌曲 (Liederkreis)」という今までにない形式の作品で、複数の歌曲をひとつのコンセプトのパッケージの中に収めるという、これまでに「ありそうでなかった」ものだった。
この形式はベートーヴェン以降の時代、シューベルトやシューマンなどのロマン派の作曲家たちの中に大流行を巻き起こすことになる。その後もこの「連作歌曲」は発展を続け、現代における「アルバム」の形成にも大きく影響を及ぼしているとも言えるかもしれない。
この作品《遥かなる恋人に》にも見られるようにベートーヴェンの作風はこの時期から方向性が変わっていく。《エロイカ》《運命》などで見られた直接的でエネルギッシュな作風は減っていき、より内省的、叙情的な表現が多く見られるようになっていった。
こうしてベートーヴェンの人生における「後期」が始まった。だがそれと同時にウィーンの街は社会的にも音楽的にも今までとは全く違う、新たな局面に向かっていく。
非・文化都市ウィーン
1819年、ウィーンの街にはナショナリズムが大きく膨れ上がっていた。特に若者の間でその動きは顕著に見られ、過激な学生運動があとを絶たない。この動きはまさにナポレオン戦争時代の反動であり、何も前進することがなかったウィーン会議に対する不満でもあった。若者たちの極右運動はどんどんと過激化していき、ついには文化人の暗殺まで起きる始末。
こうした出来事を受け、当時ウィーンを統べていたメッテルニヒはこれを機に壮大な社会統制を企てる。郵便物や書物、そして芸術作品に対するガチガチの検閲はもちろん、街にはスパイや秘密警察が大量に投入され「華やかな文化都市ウィーン」はあっという間に息苦しい監視社会へと姿を変えてしまった。
そんな世間がビクビクしている言論統制の世に一人だけ、何も気にせず大声で自分の意思をあげ続ける男がいた。そう、ウィーンでその名を知らない人はいない我らが大作曲家、ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンである。
実際に彼の派手な政治的発言も監視対象であり、一時はベートーヴェンを逮捕するべきかの論議が政治家たちの中で繰り広げられていた。しかし、あの全ヨーロッパが尊敬するベートーヴェンを逮捕したら世論は黙っていない。それは誰から見ても明白なことだった。ここにきてベートーヴェンは自分が築き上げた名声によって弾圧の手から救われることになった。
言論統制の世が変えてしまったのは街の殺伐とした雰囲気だけじゃない。この「ウィーン体制」と呼ばれる悪名高き政策は、音楽的トレンドもすっかり変えてしまった。市民は生活の現実逃避として歓楽的なワルツやポルカ、そしてただ華やかなだけのイタリア・オペラを好んで選ぶようになり、思想的なメッセージの強いベートーヴェンの作品はウィーン市内ではいつの間にか時代遅れとなっていった。こうした理由からベートーヴェンの中にはウィーン市民に対する失望感が芽生え始めることになる。
内と外の平和のために
「来年、大司教に即位することになった。そこで君に頼みたいのだが、その式典のためにとびきりのミサ曲をひとつ書いてくれないか」
1820年の6月、ベートーヴェンはパトロンであり弟子でもあった友人、オーストリア皇族のルドルフ大公からこんな依頼を受ける。依頼仕事にはあまり気乗りしないベートーヴェンであったが、これはベートーヴェンにとってもはやただの依頼仕事ではなかった。親しい間柄だったルドルフの頼みというだけでなく、ここ最近ベートーヴェンはすでに教会音楽に強い関心を示していたのだ。
――この命もいつまで持つかわからない。ついに俺も神と対峙するべき時がきたのか――
老い先が短いことを悟っていたベートーヴェンはこの作品、《ミサ・ソレムニス》を“人生の集大成” とするべく、全身全霊を注ぎ込む勢いでこのミサの作曲を進めた。しかし“人生の集大成”がそんな短時間で作れるわけがない。
結果的にこの作品はルドルフ大公の大司教即位式典に間に合うことはなかった。それでもお構いなしにベートーヴェンは《ミサ・ソレムニス》の作曲を続け、この作品が完成しルドルフ大公のもとに届くのは即位式典から3年後のことになる。
ベートーヴェンには《ミサ・ソレムニス》の作曲時期に生み出された別の傑作群がある。彼の最後の3つのピアノ・ソナタであるピアノ・ソナタ第30番、第31番、第32番。
ベートーヴェンにおけるピアノ音楽の集大成とも言えるこの3作で、彼は形骸化した古典派のソナタ形式を完璧に破壊し、ピアノ音楽における新たな可能性を明確に示した。
それと同時にベートーヴェンの時代ではすっかり「忘れ去られた作曲家」という扱いだったバッハの作品を引用し、その技法をも踏襲している。そんな、過去と未来両方を見据えた恒久的価値を持った作品群は後の時代の作曲家たちに多大な影響を与え、今現在でも「後期3大ソナタ」として多くの人に愛され続けている。
1823年の3月、“人生の集大成”として5年も費やした《ミサ・ソレムニス》が遂に完成した。しかし、結果的にそれは人生の集大成たる作品にはならなかった。ベートーヴェンがこの作品に最も込めたかったメッセージ、それは「平和」。楽譜やスケッチには「内と外の平和」という走り書きが幾度ともなく現れている。
――神と対峙する音楽であるミサを書けば「平和」を体現する音楽が書ける――
最初はそう思っていた。しかし作曲を進めていく中でベートーヴェンは気付いてしまったのだ、自分にとっての神は「キリスト」ではなかったことを。もちろんベートーヴェンはキリスト教で、出生時はカトリックの教会で洗礼も受けている。それでも彼の持つ次世代的な哲学、思想は知らぬ間にベートーヴェンをキリスト教的思想の枠組みを超えた先に誘ってしまっていた。ベートーヴェンにはノートに自分の心に響いた言葉を書き留める習慣があったが、実際にその大半は哲学者の言葉やインド思想などで、聖書からの言葉はほぼ無いに等しい。
気持ちを新たにしたベートーヴェンは自身の「神」の正体を探るべく次なる“人生の集大成”の創作を始めることになる。こうして次に作曲されるのがあの、全生命のための平和を謳った歓喜の歌「交響曲第9番」となるのであった。
人生の集大成
自身の「神」を探し出す上でベートーヴェンはある一編の詩を思い出す。18歳の時、故郷で大学の仲間たちと熱狂しながら読み漁った一編の詩を。
フリードリヒ・シラー:「歓喜の歌」
――そうだ、あれこそ俺の求める思想じゃないか!――
そうしてベートーヴェンは埃かぶった本棚の奥からしわくちゃになったその詩を取り出すや否や詩の再編を始めた。彼は詩の中から自分の心情とフィットしている部分だけを抜き出し、順番を入れ替え、更に冒頭に自ら紡ぎ出した一節を付け加える。こうしてシラーの「歓喜の歌」のリミックスを作り、オリジナルとは違う新しい文脈を持たせる事を見事にやってのけた。そしてこれまで自分が培ってきた持ちうる全ての表現方法を融合させて壮大な合唱付きの交響曲を作り上げたのだった。
出来上がったその大規模な交響曲はまさしくベートーヴェンの「人生の集大成」というに相応しい内容で、作品の中には確かにベートーヴェンが思い描く「平和」があった。キリストではないベートーヴェンが信じる「神」がいた。このように特定の宗教的思想を持たせなかったことが結果的にこの作品が「時代を超え世界中で歌われる全人類の賛歌」となった所以があるのかもしれない。
作品は完成した、あとは初演の場所が問題だ。先で述べたようにベートーヴェンはイタリア・オペラに浮かれているウィーン市民たちに対しての失望感があった。そのためウィーンでの初演は避け、より思想的に豊かな街での初演を希望していた。それを知ったウィーンにいるベートーヴェンの友人やパトロンたちは「この街を再び芸術の都にするためにも、交響曲の初演はウィーンでやってほしい」となんとかベートーヴェンを説得する。渋々ベートーヴェンはその説得を受け入れるが、まだウィーン市民たちに対する失望感は心の奥に残ったままだった。
歓喜が鳴り響いた日
1824年の5月7日、ウィーン中心にあるケルントナー劇場の舞台裏には大勢の合唱と管弦楽、そして4人のソリストが待機していた。開演を待つ演者たちの中には期待と不安が入り混じったなんとも言えない異様な雰囲気が立ち込めている。開演時間になると、大規模なオーケストラと合唱団、次に4人の歌手と指揮者が舞台袖から入場してくる。そして最後にベートーヴェンも舞台に現れ、すでに指揮者がいる指揮台に我が物顔でズカズカと上がり込んだ。
――指揮者が二人?そんな演奏が成立するのか?――
そんな動揺する聴衆たちのざわつきの中、ベートーヴェン最後にして最大の交響曲の歴史的な初演は始まった。
楽譜を視界の隅に入れながら、奏者たちの手指の動きを目で追う。そうすれば耳が不自由でも音楽が聴こえる。そうやってベートーヴェンは自ら生み出した作品の濁流に流されまいと、指揮台にしがみつく思いで立っていた。どうやら奏者たちの動きや表情を見る限り、演奏はうまくいっているようだ。無事にフィナーレも始まり、合唱も口元を見る限り間違えずに歌っている。音楽は破綻することなくオーケストラも最後の1音まで弾き切った!どうだ、これは成功したんじゃないのか?
しかし演奏が終わった後、ベートーヴェンが感じたのは完全なる静寂だった。歓声が聴こえなくてもその熱気の「気配」くらいは分かるはずだ、ベートーヴェンはそう思っていた。しかしその場に満ちているのは静寂。
――やっぱりウィーンの奴らに俺の演奏なんてわかりゃしないんだ――
指揮台の楽譜に目を落とし、悔し涙で目頭がじわじわと熱くなる。
その時だった。アルト歌手がベートーヴェンの手を取り、彼を聴衆の方に振り向かせた。いきなりのことに動揺するベートーヴェンの視界には紛れもない爆発的な大熱狂が飛び込んできた。会場は満席で、聴衆たちは総立ちになり、涙を流している人も少なくなかった。誰しもが惜しみない拍手と歓声を舞台に、そしてベートーヴェンに送っている。ウィーン市民たちは忘れていなかったのだ、ここが芸術の都であることを。そしてその中心にはいつも、この強情な大作曲家がいたことを。こうして交響曲第9番は「ベートーヴェンの集大成」として堂々と世に送り出されることになった。
人生最大の作品にようやく到達したベートーヴェンだったが、体の衰えも以前に比べ顕著に感じるようになり、以前のような精力的な作曲活動は難しくなっていた。それでも少しずつ、彼の人生最後の作品群となる弦楽四重奏曲を細々と書き進める日々を送る。そこにベートーヴェンにとって最後の悲劇が起きる。
最後の悲劇
第九の初演から2年ほど経った1826年の夏の明け方、ウィーン近郊の美しい谷の中腹で銃声が2発鳴り響いた。そこに倒れていたのは20歳の若者カール・ヴァン・ベートーヴェン。幼い頃に作曲家ベートーヴェンによって半ば無理やりに引き取られた、あの甥っ子カールだった。ピストル自殺を試みたカールだったがそれは未遂で終わり、頭部に大怪我を負うものの致命傷とはならなかった。通行人に発見されたカールはあえて親権を持つベートーヴェンの名前は伏せ、会うことを禁じられていた母親のもとに運び込まれることを望んだ。
そう、カールの精神はずっとベートーヴェンに追い詰められていたのだ。ごく平凡な家庭環境に生まれたカールはベートーヴェンに突然押し付けられたガチガチの英才教育についていける筈もなく、何より母親から無理やり引き離されたストレスは想像を絶するものだった。
「お前は学者になれ」とベートーヴェンに言われて進んだ大学も中退。その後は過保護なベートーヴェンの目を盗んで興じる夜遊びが唯一の憂さ晴らしとなっていた。しかしそれもベートーヴェンにバレてしまい、カールに対する監視の目は益々厳しいものになっていく。こうしたストレスの積み重ねはカールに自殺を決意させるほどに膨れ上がっていった。
この甥っ子の自殺未遂はベートーヴェンに対してどれほどのショックを与えたことだろう。
――これまで身骨を砕いて100%の愛情をカールに注いできたはずだ、なのに俺はいったい何を間違えたんだろう?――
ベートーヴェンはカールが入院する病室に一目散に駆け込んだ。ベッドに横たわったカールは弱々しく虚空を見つめているが、その顔にはどこか安堵の表情がうかがえる。それを見たベートーヴェンはようやく自分の過ちを理解し、二人は落ち着いて話をすることができるのだった。
二人の話し合いの結果、カールは軍人になりたいと願い、ベートーヴェンも不本意ながらも今度はカールの意思を尊重してその願いを聞き入れることにした。そうして二人はカールの入隊までのわずかな時間を共に過ごすことにした。
そんな穏やかな時間も終わりを迎える1826年の晩秋、ベートーヴェンの身体に異変が起きる。顔は黄色に染まり、身体には水が溜まって高熱にうなされる日々が続く。緊急の手術をしてなんとか一命を取り留めるものの、全快になる可能性は極めて低かった。
楽聖の終末、そして完成
1827年の3月、その部屋の前には小さな行列ができていた。それはベートーヴェンの死期が迫っているという情報を聞いて駆けつけた人々だった。これまでの人生を共に駆け抜けたウィーンの音楽仲間やパトロンたち、そして「カール問題」を皮切りに疎遠になってしまっていた旧友たちの姿もそこにあった。そんな彼らを出迎えるベートーヴェンは今ではすっかり痩せ細ってしまったが、その眼差しはウィーンに初めて来た日のそれと変わらず力強く光を放ったままだった。
いつもより寒い3月26日。空には厚い雲がかかり、決して弱くない雨が降り続いていた。この数日前にベートーヴェンの「死という運命」に抗い続けた精神力もついに限界を迎え、彼は昏睡状態となりベッドに横たわっていた。
どういうわけか、その部屋の空気は窓の外の荒れ模様に反していつもより穏やかに流れている。そんな午後の一瞬にその瞬間は訪れた。轟音の雷鳴とともに一筋の稲妻がウィーン市中に降り注ぎ、その光が窓の外を真っ白に染め上げる。その時、昏睡状態だったはずのベートーヴェンは目をカッと見開き天高く拳を突き上げた。そしてその力強い拳がベッドに下ろされたのと同時にベートーヴェンの心臓は鼓動を止めたのだ。
――諸君、喝采を。喜劇は終わった!――
1827年3月26日、世紀の大作曲家ルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェン逝去。
革命や戦争といった大波乱の世の中で、音楽界に収まらないとてつもなく大きな爪痕を歴史に残した大作曲家の人生は57歳で幕を閉じた。その報せは一晩のうちに街中に広まり、ひとつの時代が終わったことをウィーン市民たちは実感していた。
ベートーヴェンの葬儀は彼の死後数日のうちにひっそりと行われる筈だった。しかし死んで尚ベートーヴェンという巨大すぎる存在は、また一つのセンセーショナルな出来事を巻き起こす。ベートーヴェンの自宅から墓地へと棺が運び出されると、それを待ち焦がれていたかのように数多くの市民が葬列に加わり始めたのだ。
葬列は進むごとにどんどんと大きくなり、結果的に2万人を超える超大規模な葬列がウィーン市中に出来上がった。それは言論統制の敷かれた都市にとっては「事件」といっても過言ではない出来事だった。たとえオーストリアの皇帝が亡くなろうとこんな巨大な葬列になることは決してない。現代にもこれだけ壮大な葬列を自然発生させるアーティストが何処にいるというのだろう?当時のウィーンの人口はおよそ30万人で、単純計算でも15人に1人という途轍もない人数の人がこの偉大な英雄の死を弔ったことになる。
こうしてルートヴィヒ・ヴァン・ベートーヴェンという「存在」は完成された。その存在は音楽界における革命を意味し、「古典派」と呼ばれる時代を終わらせ「ロマン派」という新しい時代の碑を音楽史に打ち立てた。そしてベートーヴェン以降の音楽家たちは皆ベートーヴェンという巨大すぎる存在に苦しめられながらもそれを様々な形で継承、発展させて新しい音楽表現を生み出していくことになる。
ベートーヴェンが存在しなかったら、現代僕らが身近に接している身近な音楽も違う様相をしていただろう。それはそれで興味深いが、僕らが生きる世界線はベートーヴェンが存在した世界線なのだ。生後250年経った今でも《運命》の冒頭や《エリーゼのために》の旋律を知らない人はいなく、年末には街中に「第九」の歓喜の歌が溢れる、そんな世界線なのだ。そしてこの、ベートーヴェンが生きた世界線の音楽を僕らはいつまでも愛してやまないのだ。
敬愛なるルートヴィヒ。あなたの音楽はあなたが生まれた250年後の世界でも、この空の下で堂々と、そして高らかに鳴り響いています。
2020年12月29日
Written by 水野蒼生

水野蒼生『BEETHOVEN -Must It Be? It Still Must Be-』
2020年3月25日発売
CD / iTunes / Apple Music / Spotify
- 水野蒼生 アーティスト・ページ
- ベートーヴェンはロックスターである。その理由を楽曲と生涯から辿る by 水野蒼生【第1回】
- ベートーヴェンはロックスターである。その理由を楽曲と生涯から辿る by 水野蒼生【第2回】
- ベートーヴェンはロックスターである。その理由を楽曲と生涯から辿る by 水野蒼生【第3回】
- ベートーヴェンはロックスターである。その理由を楽曲と生涯から辿る by 水野蒼生【第4回】
- ベートーヴェンの聴くべき作品ベスト10
- ベートーヴェン生誕250周年記念サイト“ベートーヴェンを聴こう!”
- ベートーヴェン「運命」に合わせて聴覚障害のヒップ・ホップ・ダンサーが躍るMV公開